人の優しさに触れたとき、異なる二種類の気持ちが心をよぎる。
ひとつは安心。純粋な感謝の気持ち。もうひとつは不安。自分がその優しさに値する人間か、折角の相手の思いを無駄にするような考え方や生き方をしていないかという不安。
これは誰にでもあることだろう。
感動の裏には孤独への恐怖がある。自分以外の人が自分という存在を忘れずにいてくれたことに胸が一杯になる。
不安の裏には自己批判がある。生きたい自分を生きていれば不安は無いはず。自分の道徳観に問題が無ければ。
にんげんは社会的生物。蟻も蜜蜂も狼も象もイルカもみんな集団でなければ生きていくことが出来ないと知られているように、人間も同じ。なのに、一人きりで生きていけると勘違いしてしまう人がたくさんいる。特に都会ではそういう人が多いように感じる。
都会という存在そのものが人の手によって作られ維持されているものなのだから、そこにいるだけで人と間接的に関わっている。
技術が発達して人と触れ合う機会が減っているのは、そもそも人と触れ合わずに暮らせるようにするためではなかったはずだ。人の手がかかる部分をなるべく自動化、効率化して運営維持のコストを下げることが目的だったはずだ。しかしその副産物として、直接人と接しなくても生きていける環境ができた。やがてそこに価値を感じる人たちが現れて、需要が生まれた。今は人と触れ合わずにサービスを受けられることがひとつの価値になってしまった。
逆に人と触れ合うほうが煩わしい、手間がかかるという。
人と触れ合うには人件費がかかり、人の温もりが感じられるサービスはプレミアムになった。
だから都会人は人の温もりが無償で提供されることに慣れておらず、まず始めに疑いの目を向ける。それば無償の愛であると信じることがなかなかできないのだ。
やがてなにも裏がないとわかると、感動する。こんな優しさが人にはあるのだと。と同時に、汚れてしまった自分の心に罪悪感を覚える。そして、今までも一人で生きてきたのだと思っていただけで実はそうではなかったことに気づく。
愛とは人生の中で初めて無くなってその存在に気がつくものだ。それは大抵の場合、親から与えられるものだ。私たちは呼吸をするのに酸素の存在を気にしない。
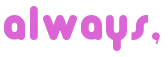

コメント