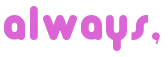一生懸命やっているのに…
「おじさんがどんなにスゴイことをしてきたのか知らないけれど、私おじさんみたいな人大嫌い! どうしてそんなに偉そうにいばってばかりいるの? おじさんの会社で働いている人たちはかわいそう。でも今頃みんな伸び伸び楽しく仕事してるでしょうね。だって、おじさんは今ここにいるんだもの」
中学3年生の女の子にそう言われたおじさんの体に激しい衝撃が走った。それまでの居丈高な姿は瞬時にして消え去り、おじさんの目から涙がこぼれ出た。そしてまもなくそれは号泣に変わった。
女の子は立ち上がり、おじさんにピッタリ寄り添った。
「今のおじさんは大好きよ!」
女の子も泣いていた。周りにいたみんなも…。
苦労に苦労を重ね、不屈の精神をもって今や社員1000人を擁する大会社をつくりあげた50代半ばの経営者が裃(かみしも)を脱ぎ、ただのおじさんに戻った一瞬であった。
これはセミナーでの一場面です。
誰もが一生懸命生きている。少しでも今より良い状況をつくろうと。良くしようと思っているのに、なぜか結果は良くなるとは限らない。いくらやっても誉められるどころか逆に非難を浴びることさえある。
あなたもそんなやりきれない思いをしたことがあるのではないでしょうか。
私たちは家庭や職場など自分が所属する集団の中でさまざまな役割を背負います。そしてその役割を果たすことに没頭するあまり、あたかもそれが自分のすべてであるかのように思ってしまう。
それは私たちが何か人の役に立ちたいと考え、またそれによって自分の価値を認めてほしいと願うところからきているのだといえましょう。それをいけないなどと言うつもりはありませんが、もしあなたが「自分から仕事をとったら何も残らない」などと思っているとしたなら、これは大きな問題です。その発想自体がすでにズレているのです。
能力の功罪
あなたは過去多くの人と出会い、そしてその人たちから良きにつけ悪しきにつけ、多くの影響を受けてこられたことでしょう。
それらを振り返ることも大切なことですが、今日私たちが考えるべきことは、自分がどれほど他人に影響を及ぼしてきたかということなのです。
人には誰にでも能力があります。あなたが経営者もしくはリーダーという役割を担っているとするならば、きっと、あなたには他の多くの人たちよりも優れた能力があるからに違いありません。
リーダーに能力がなければ、経営目的の遂行はもちろん人を育て活かしていくこともできないからです。
しかし、もしあなたが優れた能力を発揮して良い結果を出したとしても、手放しで喜んでばかりはいられない。
良く効く薬ほど副作用が強いように、また核燃料が高度のエネルギーを出すと同時に有害な核廃棄物もつくってしまうように、人間の持つ能力というものも大変なクセモノであるからです。
「沈香(じんこう)も焚かず屁もひらず」という諺があります。
良い香りも出さないかわりクサイ臭いも出さないという、いわば毒にも薬にもならない人のことを言うのですが、能力があればあるほどあなたは「沈香も焚き屁もひる」存在になってしまうということ。
あたかも振り子のように、プラスを100出せば否応無しにマイナスも100出してしまうということを私たちは知っておかねばなりません。皆の幸せを願って、一生懸命やったからといって、必ずしも良い結果が出ないのは、その辺に理由があるからだと思います。
あなたは「くさや」
臭いものには蓋をするように、私たちは本当に見なければならないものや知らねばならないことから目をそらしてしまいがちです。
なぜなら、それらのことはけっして綺麗なものではないことをあなたは薄々知っているから、できれば見たくない。ことに自分自身の姿や体臭については。
「自分のことは自分が一番知っている」と断言する方もいますが、果たしてそうなのでしょうか。
私たちがいかにものを考えて生きているといっても、1日の中で意識して行動しているのは5%で、残りの95%は無意識の行動だといわれます。
言っていることとやっていることが違う、と周りからの批判を受けるのも、自分の無意識の行動がなせる業なのかもしれませんね。
自分のことなんて実はほとんどわかっていない、そう思っていたほうがイイ。御身のためですぜ。
ひどい言い方かもしれませんが、まあ自分は「くさや」(アジの干物)だと思っていればよろしいのではないでしょうか。クサくて鼻がひん曲がります。でも、味は抜群! ウマイのです。それがあなた。
美味いが、やはり臭い
そういうわけで、あなたは諸刃の剣です。切れる刃で目的を達するけれど、返す刃で切らなくてよいものまで切ってしまう。
だが、そのことにはほとんど気づかない。
たとえば、能力が有るとか無いとかいうことは、通常、人との比較の上で評価されるために、有る人は無い人に対してどうしても優越感を持ってしまう。いわゆる「うぬぼれ」というやつです。
また、能力の有る人は、自信があり自分の考えを正しいと思っているから、他人の意見をよく聞こうとはしない。これを「ひとりよがり」といいます。
そして、能力の有る人は主義主張が強く、自分がこうだと思ったら頑なに変えようとはせず、むしろ人をねじ伏せてでも自分の意見を押し通そうとする。つまり「がんこ」です。
とにかく、有能であればあるほどタチが悪い! ゴメンナサイ…
骨身を削りつつ懸命に生きておられるあなたに向かって、「あなたは、頑固でひとりよがりでうぬぼれている」などと面識もない私が言えば、切れるあなたはキレてしまうかもしれませんね。
でも、もしかしたらあなたは自分の気づかぬうちに周りにそのような毒ガスをふりまいているかもしれません。自分の体臭を自分では感じないように。
できることなら人に悪い影響は与えたくないと誰もが思います。
しかし、良いと思ってしたことが裏目に出たり、小さな親切大きなお世話になってしまったり、何の気なしに言ったことが深く人を傷つけてしまったり、そんな経験あなたにはありませんか?
「何回同じことを言ったらわかるんだ、そんなことはできて当たり前だろう」なんてことを言ったことのある方、これは大変なことですよ。
自分の内側を覗いてみよう
目を外に向けて知識や情報を得ることはリーダーのあなたに必要なことですが、それ以上に大切なことは目を内にむけること。
つまり、目を自分自身の内面に向けることです。
ちょっと、ここで赤ちゃんについて考えてみましょう。
あなたはたぶん「暗い赤ちゃん」など見たことがないはず。
「格好つけてる赤ちゃん」や「頑固な赤ちゃん」、「うぬぼれた赤ちゃん」などもみたことがないはず。そんな赤ちゃんいるはずない!
あなたも赤ちゃんのときは、愛らしい澄んだ瞳をもっていた。
でもいつからかその瞳に陰りや曇りが出てきて、知らず知らずのうちに変わってしまったのでしょう。
誰もそうなりたいわけではないのに、臭ってくるんです。
その臭いがいわゆる欠点というやつなんですね。
無意識を意識にリンクする
欠点といえば、あなたにはそれがいくつあるのでしょう。
10個? 100個? いえいえそんなものではありませんよ。ある学者が人の持つ欠点を挙げていったら、何と3000個にもなったそうです。信じるかどうかはともかく、もし3000個の欠点を直そうなんて思ったら、10日に1つ直しても優に80年はかかってしまう。
自分の欠点を直していきたいと思っている方には、身もふたもないことを言ってしまってごめんなさい。
私事で申し訳ありませんが、私自身が今まで欠点を自分の意思で直したという実感が一度もないのです。いくら自分に言い聞かせようと、ついに自分の意思で直すことはできませんでした。
でも、そうは言っても自分の欠点が放つ悪影響は抑えたい。
それにはどうしたらよいのか。
「自分の欠点を出さないようにすればいい」で済むなら世話はないのですが、しかし出さないようにするということ自体が実は不可能に近い。なぜならそれらは無意識の所産で、気づかぬうちに出てしまうものだからです。
じゃあどうする。
それは無意識の中にあったものを引きずり出して、意識の中にしっかりと植え付けること。
いかに自分がわがままでうぬぼれて頑固でひとりよがりであるかを深く感じいることだと私は思っています。
身を修めるということは、自分の欠点を出さないよう努力することではなく、自分の欠点がどれほどあって、それがどれほど周りの人たちに影響しているのかを知ることではないでしょうか。
「知らぬが仏」のあなたと、「知るが地獄」の周りとの意識のギャップを思い知ることこそ、リーダーの必須条件だといえるでしょう。
バランスの崩れに気づこう
いまや能力主義真っ盛り。ことに不況になるとその傾向は顕著になります。資本主義と能力主義はどうやら不可分の関係にあるらしい。
この社会で生きるには能力が必要だからと、小さい頃から知能教育の漬物になってきた私たち。知育ばかりが幅を利かせて、体育がおまけのようにくっついている。徳育なんて死語になってしまった。
「仁・智・勇」も、智だけが残って仁も勇も消え失せてしまった。
どこかおかしいと思っていた人はいたはずなのに、そしてその結末を憂いていた人も多くいたはずなのに、時代の波と体制に飲まれてしまってその叫びは結晶しなかったのです。
バランスを崩した私たちがバランスのとれた社会をつくることなどできるはずがありません。
(知的)能力主義の社会においては、知力の優れた者は人間性も優れているという錯覚が横行します。だから、リーダーという役割を担う人の多くは、自分が周りから信頼され尊敬されるべきだと思っているし、そうでない現実に直面すると権力をもって他を服従させてしまうのです。
「…知識はすすンでも心はすすまンベ。心すすまンのに知識だけすすンだらどうしていいか判ンなくなるべさ。…」(倉本聰「ニングル」理論社より)
また、能力主義は放っておけば人間無視を呼び起こします。能力のない者を「役に立たない存在」として社会から締め出してしまうのです。それも当然のごとく平然と。
そうして、いつの日か、能力を誇った人もその見返りを十分に受けて失意の日々を送るはめになってしまうのです。
「子供怒るな 来た道じゃ
年寄り嫌うな 行く道じゃ」(曹洞宗・良興寺)
比較社会の罪
自分を知るということは、自分の人格のバランスの崩れを知ることだとも言えるでしょう。
何事も他と比較され評価される社会にあって、私たちは幼い頃から大なり小なり心に傷を受けてきました。
家庭にあっては兄弟姉妹との比較、学校では学力や体力の比較、社会に出れば能力の比較というふうに、いつもできる者とできない者のレッテルを貼られ、優越感と劣等感の狭間を行き来してきた私たち。
たとえば学力に劣等感を持つ子が、優れた運動能力を発揮して体力で優位に立ったとします。彼は体力に自信を持つことができると同時に優越感(うぬぼれ)も持ってしまう。しかし体力では優越したものの学力では相変わらず劣等意識からは解放されないのです。
優越感がうぬぼれを生み出すように、劣等感はひがみや妬みを生み、ひいては自己否定を誘発してしまいます。
そして、この比較社会は優位に立つ者にとってさえ安全ではなく、いつ優位から落とされるかわからないという大きな不安を抱え込む人を多くつくってしまうのです。
最近、トラウマ(Trauma)という言葉をよく耳にしますが、多くの人たちが過去受けた激しい精神的ショックで心に後遺症があることを問題にし始めたからなのかもしれません。
私たちの人格は過去から今日までの生きざまの結晶体であるとも言えます。
とすれば、自分を形成してきた過去を振り返るということは、自分という人間を知るためには欠かすことのできない大切なことだと言えましょう。バランスの崩れもそこから発見できるかもしれません。
過去を振り返る
純粋無垢な赤ちゃんの心は真っ白なキャンバスです。
それが月日とともに、さまざまな色に塗りつぶされていく。自分で描いた夢という絵に突然ポタリと真っ黒な墨が堕ちて絵を台無しにしてしまう。泣きながらも、またその上に夢を描いていく。
私は今まで多くの人々の生い立ちと生きざまを聴く機会に恵まれました。事実は小説より奇なりといわれます。正にその通りでした。1人ひとりの生きざまが、どれほど想像を絶するような絶望と感動で織りなされていたことか。
消し去ることのできない過去を、あらゆる種類の涙とともに吐き出したとき、私はその1人ひとりが間違いなく勇気をもって自分の足で力強く踏み出していく姿を見ることができたのです。みんな輝いていました。彼らは消せない過去をすべて真正面から受け入れたのでした。
でも、どうしてこんなにも人生って辛いことや悲しいことが多いのでしょうか。誰もが楽しくて喜びに満ちあふれた生き方を願っているのに、そして誰もが暖かで思いやりに満ちたかかわりを持ちたいと思っているのに……。「神様ってイジワルだな!」って思いませんか?
たしかに、磨くというのは摩擦することですから、私たちに辛い体験がふりかかってくるということは、そのとき自分が磨かれているのだということなのでしょうね。
大きな苦難に遭遇すると、私たちは「なぜ自分ばかりこんな目に遭うのか」と天を仰いでしまいますが、けっしてそうじゃないんですね。
私は行き詰まると、「あなたがたの遭った試練で世の常でないものはない」という聖書にある言葉を口ずさみます。
これくらいのことで負けてたまるか、そう、今日までいろんなことがあったけれど、何とかやってきたじゃないかと自分を励ましたりするのです。
自分の価値は自分で認める
人間が人間らしく生きていける社会をつくっていくためには、「自分で自分の価値を認める」という姿勢を持つことが大切です。それなくして自分らしい生き方を追求することは不可能だから。
今の社会で、私たちはあまりにも自分の価値評価を他人に委ねすぎてはいないだろうか。人間関係の中で嫌われたくない、良く見てほしいという意識をあまりにも大事にしすぎてはいないだろうか。
もしそうだとしたら、本音で人とつきあうことなど到底できません。
絶えず周りの動向を気にしつつ自分を調節して迎合していかねばならないから、そしてそこでは馴れ合いやら媚び諂いがはびこり、取り繕いや背伸びが当然のように行われてしまうからです。
これはいわば狐と狸の化かし合いで、本当が何だか分からないから相手のことをどこかで疑ってしまうことになります。そういう状況下で、信頼関係を結べと言ったってこれは無理というもの。職場では当然の帰結として人は沈滞し活力を失います。
さらに問題なのは、常に自分がどう評価されているかに神経を使い、その時々の評価に一喜一憂しなければならず、心の底にいつも不安を抱えていなければならなくなることです。
こうして自分の価値評価を他人に委ねてしまったために、他人の目を怖れ神経症にまで至る人がどれほどいることでしょうか。
「自分で自分の価値を認める」には、自分はいつ消えるのか分からないたった1つの命をもって一度限りの人生を歩んでいるのだ、ということを深く考えてみることです。そして、誰のために生きているのかをトコトン考えることだと、私は思っています。
人間性回復の経営学(全12回)
| 回 | テーマ | サブテーマ |
|---|---|---|
| 1 | 第1回講義 心の枷(かせ)をはずしてみよう | 常識との対決...思い通りの人生を歩むために |
| 2 | 第2回講義 自分は一体何者なんだ | 自分の臭さに気づいていますか |
| 3 | 第3回講義 人間関係の極意教えます | (極意につき極秘) |
| 4 | 第4回講義 人間尊重こそ繁栄の原点 | 手間暇惜しまず "one to one" |
| 5 | 第5回講義 感動と絶望について | 説得では何も変わらない |
| 6 | 第6回講義 不安と孤独について | お触りサロンのお勧め |
| 7 | 第7回講義 犯人は誰だ! | 犯人は◯◯だ! |
| 8 | 第8回講義 停泊中の船舶に告ぐ…直ちに出航せよ | 経営とリーダーシップについて |
| 9 | 第9回講義 決別の決断 | 1本の命綱を誰に投げるのか |
| 10 | 第10回講義 一流の条件 | "らしさ" の追求と発揮 |
| 11 | 第11回講義 文化の発信基地として | これこそサロンの使命だ |
| 12 | 第12回講義 もっと儲けよう、そしてもっと使おう | 愛と奉仕の実践 |