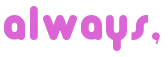期待という言葉
まわりの多くの人たちから期待されて生きているあなた。あなたがリーダーとして力を発揮すればするほど、またかかわる人が多くなればなるほど、あなたへの期待は高まっていくことでしょう。
期待されるということは精神的な快感をもたらしますが、一方では大きなプレッシャーをも生み出します。
あなたにとって「期待」という言葉はどんな意味があるのでしょうか。
①期待されなければ人生意味がない。期待に応えることこそ周りへの役立ちであり、自分の価値を自他が認める重要なことだ。
②期待されないなんて自分の存在感がないようでさびしい。家族や友人、職場のスタッフから期待される人間になりたい。
③期待にうまく応えられないと、期待ハズレだとか期待を裏切ったと非難されることになるから期待されるのは重荷になる。
④周りからの期待に応えるために生きるなんてご免だ。自分の人生は他人のためにあるのではない。
上記はあなたの人間観・人生観を問うもので、どれが正しいのかという判定をするものではありません。
私があなたに問いたいのは、「まわりの期待に応える」ということがあなたの毎日の生活の中でどれほどの比重を占めているのか、ということ。
「期待」を人間関係上、重要だと考える人は①か②を、そうでない人は③か④を選ばれたはずです。
「期待」という希望的な響きの良い言葉は、時として人を奮い立たせ生きがいにまでなることもありますが、一方では人を死に追いやるほど残酷な面を持ち合わせているのです。まさに精神的麻薬というべきものと言うことができるでしょう。
親の期待に応えられなかった子、あなたの期待を裏切ったスタッフ……彼らはどんな思いで、どんな末路をたどったのでしょうか。
①の考え方をする人、すごくカッコイイ。でも傲慢で無残な人。期待に応えられない人を人間として認めないのだから。
②の考え方をする人、あなたは自分を見失う危険大いにあり。集団の中での自分の存在の不安を常に抱えていて、認めてもらうためなら自分を捨ててしまうことも厭わない。
③の人、あなたは人を怖れ尻込みしながら生きている。無難を好み、自分の弱さをカバーしようとうまく立ちまわるずるさを持つ。
④の人、わがままで冷徹な人。開き直っている。だが、ある意味、真理をつかんでいるともいえる。
誰のために生きているのか
私は今、期待されることが自分の価値ではないと思っています。とはいえ、人は誰もが生まれ落ちたときから期待をかけられる。
期待に応えたときの相手の喜びを知ると、「期待」を無視して生きることができなくなってしまう。
まわりの期待に応えようという一心から無理をしたり、本当に自分がやりたいことを捨ててしまうことすらある。
親のために、妻(夫)のために、子どものために、会社のために、お客のために……。
そうしてある日、フッと心に穴があいたような空しさに襲われる。
一体自分は何のために、誰のために生きているのだろう。
…唐突だが 奈々子
お父さんは お前に 多くを期待しないだろう
ひとが ほかからの期待に応えようとして
どんなに 自分を駄目にしてしまうか
お父さんは はっきり 知ってしまったから
…吉野弘『奈々子に』(詩集・贈るうた)より抜粋
私は「期待」そのものを否定しているのではありません。
期待はしてもいい。ただそれはあなたが勝手に相手に望んでいることなのだ。そこを十分わきまえておくべきだと思うのです。
勝手に望み、勝手に喜び、勝手に失望落胆しているだけの話なのだから。
あなたの期待に応えるために子がいるのではない。
あなたの期待に応えるためにスタッフがいるのではない。
期待という麻薬にあなた自身が中毒しないことだ。
そうしないと、犠牲者を次々と生んでしまうことになりますよ。
比較という毒薬
オーナーが店長に話している。
「昨日訪問したAサロンの店長はさすがだね。売上げもすごいがスタッフをやる気にさせて引っ張っていく力は抜群だと思ったよ。あそこの繁盛は店長のおかげだな。一度君も彼に会ってみてはどうだ?」
オーナーは屈託なく話しているが、店長は猛烈に傷ついていた。そして間もなく、このオーナーに見切りをつけて退社してしまった。
オーナーは店長がなぜ辞めてしまったのかわかりませんでした。
この世はまさに比較によって成り立っているといってもいいほど比較が当たり前のように横行しています。
物と物との比較はともかく、人と人との比較は一体どうなんだろうと私は思います。
競争意識やライバル意識、それはそれで向上心をかきたてて互いの成長を促すということではOKと言えるでしょう。
しかし、学生時代は学力で比較評価され、学校は一流・二流といったラベルを貼られ、社会に出れば能力で比較評価を受ける。
社会がそういう体制なのだから仕方ないじゃないかと言われるかもしれませんが、果たしてそれでいいのでしょうか。
人も物も何もかも一緒くた。「人間」なんてどこにも見えない。
人間を人間として意識しないところに人間関係など正常に営まれるわけがない。
昨今の人間関係の不毛や困難を生み出した大きな原因の1つに、この「人と人との比較」という毒薬の存在がある、と私は思うのです。
いのちへの畏敬
人間を人格と個性のある存在として見なくなり、人間関係を組織や企業の事業目的の達成手段として使ってきた結果が、人間関係を破壊してきたことを私たちは深く反省しなければなりません。
20世紀を生きてきた私たちの最大の罪は人間無視の世界を造りだしてしまったこと。
イギリスの女性ジャーナリストが来日しTV番組を見て憤慨し嘆きました。ドラマや映画のシーンで毎日100人を下らない人の命が殺人などで奪われていく。これほど生や死に麻痺していて、どうして子どもたちに「いのち」の大切さを教えることができようか、と。
人間なのに、人間のことをあまりにも学ばずにきてしまったのだ。
人間関係をうまい世渡りをするための技におとしめてしまったのもこの私たちなのだ。
あなたは今、自分の「いのち」を感じているでしょうか。
あなたは、人間関係を「いのちといのちのふれあい」であることを実感しているでしょうか。
「いのち」を慈しみ合い、育み合うことこそが人間関係。
人間のいのちへの畏敬の気持ちなくして人間関係のスキルばかりを身につけようとすれば、かえって人を傷つけてしまうのです。
人とどういうふうにかかわるかを考える前に、人の「いのちの尊厳を守ること」が人間関係の根本(秘訣)だと私は思っているのです。
いのちの実感
それはまず、いちばん身近ないのち、つまり自分のいのちを大事にするということから出発します。なんていうと、いのちを大事にするなんて当たり前じゃないか、抹香臭い話はやめてくれよ、という声が聞こえてきそうですが、イーエ、このお説教イヤでも聴いていただきますぞ。だって、これを抜いたらこの連載の意味はまったくなくなってしまうのですから。ということで、さて……。
いのちはいつ消えるのか誰にもわかりません。だが、必ず消える。あなたもあなたの大切な人たちも、そして私も。片足を棺桶につっこんでいる私のこの連載も私の死で消える。だから今、生きているうちに伝えたいのです。どうしても。
いのちの実感、それは普段の生活の中ではなかなか得られません。というより、身近な人の死とか重い病に出会わない限り、ほとんど「いのち」のことなど無頓着に生きているといったほうがいい。
ある会合で、小児科に勤める若い看護師さんが涙をこぼしながら叫ぶように訴えました。「私は毎日いたいけな子どもたちが死んでいくのを見なければなりません。半狂乱のように取り乱すご両親に対して、そして死にゆく子に対して私は何もしてあげられません。どうすることもできないのです……。そのたびにもう辞めたいと思ってしまいます」。
聴いていた誰もが絶句してしまいました。
いのちといのちのふれあい
話が重くなってきました。いや、これはいのちの重さなのでしょう。
こういう問題に直面したときに、「人には寿命というものがあるのだから」なんて他人事のように一般論を言ったらコロサレますよ!
なぐさめも同情も、百害あって一利なしと思っていたほうがいい。
この看護師さんの話をきいて、あなたはまず何を考えましたか?
①死にゆく子とその親にどう対処したらよいか。
②看護師さんにどう対応するか。
大変失礼な推測ですが、多くの方は看護師さんの話の内容にとらわれて、①の子と親への対処を考えられたことでしょう。それはそれで間違っているわけではありません。あなたが考えた対処の仕方は、きっと看護師さんの今後に大いに光を与えることになるだろうからです。
しかし、ここで私たちはよく考えなければならない。
看護師さんとあなたの人間関係は、彼女が投げかけた死にゆく子とその親への対処策を示すことで完結したのだろうか。
人間関係は「いのちといのちのふれあい」だと言いました。看護師さんはあなたが一生懸命考えてくれた対処策に感謝をしてくれることでしょうが、あなたのいのちとふれあったという実感はきっと得られなかったと思うのです。
看護師さんは看護の中で自分の非力さを訴えていたが、なぜ涙をこぼしたのだろう。なぜ辞めたくなるなどと叫んだのだろう。
私たちは往々にして話の内容に引きずられて真の問題を見失うことがあります。
あなたの目の前にいる人が悲しみと苦しみをぶちまけている。
そんなときに何を考える必要がありましょうか。今あなたがすべきことは、彼女の悲痛な気持ちを真正面からドーンと受け止めること。
彼女は看護の辛さを訴えたのではなく、その辛さを誰にも打ち明けられない孤独を訴えていたのです。
孤独に打ち震える彼女は、ひとりぼっちの淋しさを涙とともに私たちに訴えていたのです。
彼女のは話し終え体を震わせて泣いていました。1人の男性が立ち上がり彼女に近づきました。彼の目にも涙が浮かんでいました。
彼女に向かい、「辛かったね。でもよく頑張ってきたね」と言って彼女をきつく抱きしめたのでした。
「いのちといのちがふれあった」一瞬でした。
7つの言葉
人間関係は人と人との「出会い」であるともいえるでしょう。
人生……いのちのいとなみ……は出会いによってつづられていきます。
多くの新しい人格との出会いもあえれば、一度出会いを体験した人格との間にも何度も新しい出会いが繰り返されるのです。
出会いは「いま・ここで」起こる。出会いはいまここで、いのちといのちがかかわること。つまり、「あなた」と「わたし」のいのちといのちのかかわり合いが出会いを呼び起こすのだ。
ふたつのいのちが「ともに」そこで一緒に「生きて」その場に「いる」ということが感じられたときに、出会いが実感となるのです。
『いま・ここで・あなたと・わたしが・ともに・生きて・いる』……この7つの言葉は、私たちが人とのかかわりの中で焦点がズレたりボケたりしたときに原点に引き戻してくれる、これも人間関係の根本(秘訣)と言ってよいかと思います。
人間関係はテクニックではありません。だから、上手だとか下手だとか本来的な問題ではないのです。
私自身、よく誤解されるのですが、これほど生き方がへたくそで人間関係に不器用なやつもいないと思っています。けっして謙遜などではありません。人間関係の極意などと偉そうなテーマを掲げたのは、円滑な人間関係を持てる人を羨み、それができない自分を呪い、散々転んで生きていく価値を見出せなくなるほど悩んだ末に行き当たった、一種の開き直りのようなものを、私と同じように不器用に生きておられる方にお伝えしたかったからです。
自分自身と対決する勇気を持とう
人間関係は「あなた」と「わたし」とのかかわりですが、「かかわる」ということは常に勇気を必要とすることなのだと申し上げたい。
自ら勇気をもって人にかかわる人というのは、自分が自分らしく生きるために自分の真実を主張する勇気がある人だと言えます。
ありのままの自分、本来の自分で人にかかわる。そこには取り繕いも遠慮も馴れ合いもありません。自分から逃げず、自分自身と向き合って対決できる勇気がなければ人間関係は不毛にならざるを得ない。偽りの自分、見せかけの自分では、人を偽ると同時に自分のいのちの輝きさえも捨てて自らを抹殺してしまうことになるのです。
いま、あなたは自分をどこかで粗末に扱ってはいないでしょうか。
そういう人は人間関係を「うまくやっていく」ことが最も大切なことだと位置付けるため、トラブルの発生を極度に嫌う傾向があります。
自分の所属する社会(職場や家庭)でトラブルを避け、うまくやっていくためには自分を押し殺すことはやむを得ないと考え、自分の真意を訴えることを放棄して、周りの期待に沿うようイイ子を演出する習性を身につけてしまう。習性になってしまうと、もはや苦痛も感じない。
そうなると、人間関係はかかわりではなく「憶測」によって始まることになってしまう。
「きっとあの人はこう思っているに違いない」とか「あの人は頑固だから聴き入れてくれるはずがない」というふうに、実際にかかわる前に決め込んでしまう。勝手に結論を出してしまって、かかわりを持てない理由を相手のせいにしてしまう。
人間関係は相手があって成り立つのに、一人相撲をとっている人がどれほどいることでしょうか。
自分を守ったつもりで、実は自分で自分に刃を突き刺している人がどれほどいることでしょうか。
かかわることは生きること
人間関係が「いのちといのちのふれあい」であるならば、それはまさに「生きることそのもの」だと言うことができます。
1人では生きられないことを十分知っていながら、自分の本当から目をそらし、他人との関係をあやふやにごまかしてしまうならば、「いのち」の存在など実感できるはずがありません。
誰もが死に限界づけられた生を生きている。
明日をも知れないいのちなら、出し惜しみせず思いきり火花を散らして生きてみよう。
誰のためでもない、自分自身のために。
この章の締めくくりに、前掲の詩の続きを記して人間関係の極意、いきいきと自分らしく生きていくための極意を、あなたにお伝えしたいと思います。
…お父さんが
お前にあげたいものは
健康と
自分を愛する心だひとが
ひとでなくなるのは
自分を愛することをやめるときだ。自分が愛することをやめるとき
ひとは
他人を愛することをやめ
世界を見失ってしまう自分があるとき
他人があり
世界がある…吉野弘『奈々子に』より……前掲の続き
人間性回復の経営学(全12回)
| 回 | テーマ | サブテーマ |
|---|---|---|
| 1 | 第1回講義 心の枷(かせ)をはずしてみよう | 常識との対決...思い通りの人生を歩むために |
| 2 | 第2回講義 自分は一体何者なんだ | 自分の臭さに気づいていますか |
| 3 | 第3回講義 人間関係の極意教えます | (極意につき極秘) |
| 4 | 第4回講義 人間尊重こそ繁栄の原点 | 手間暇惜しまず "one to one" |
| 5 | 第5回講義 感動と絶望について | 説得では何も変わらない |
| 6 | 第6回講義 不安と孤独について | お触りサロンのお勧め |
| 7 | 第7回講義 犯人は誰だ! | 犯人は◯◯だ! |
| 8 | 第8回講義 停泊中の船舶に告ぐ…直ちに出航せよ | 経営とリーダーシップについて |
| 9 | 第9回講義 決別の決断 | 1本の命綱を誰に投げるのか |
| 10 | 第10回講義 一流の条件 | "らしさ" の追求と発揮 |
| 11 | 第11回講義 文化の発信基地として | これこそサロンの使命だ |
| 12 | 第12回講義 もっと儲けよう、そしてもっと使おう | 愛と奉仕の実践 |