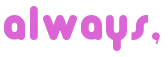大切なものを失ってしまった
ビジネスに人間尊重の思想を吹き込むのは、実は大変難しい。資本主義体制下のわが国では、常に「経済」が優先されるからです。資本主義の本質は「金」主義であって、けっして人間主義ではない。この社会で幅をきかせるのは財力と権力。つまり金持ちと偉い人。
オットット、こんな言い方ちょっとひがみっぽいかな。
金も権力も欲しければ追えばいい。それを得たときになすべき責任があることを忘れさえしなければ。
成功、名誉、富、権力を手に入れることはいわば社会正義として認められるし、それを貪ることも是とされる。
だが、追えば追うほどに、得れば得るほどに、不安と貪欲さは増すばかり。際限のない欲の世界にはまり込み、結局「持てる者の責任」なんて考えもしなくなるのが落ちなのです。
だが、貪り得たものと引き換えに大切なものを失ったことに気づく人もいないわけではありません。
ある日彼は幸せでない自分に出会う。鏡に写った「亡者」のような自分を見て愕然とするのです。
金も力も、本当は幸せになるための手段だったはずなのに、いつの間にかそれを得ることが目的になってしまっていた。
そして、自分だけならともかく、まわりの人たちをもこの空虚な世界に引きずり込み、人間らしく生きることがきわめて難しい社会をつくってしまうという大罪に気づくのです。
ちっぽけな自分でも
そんな社会に生まれ育った若者たちを、あなたは心の奥底でどこか否定的に見てはいないでしょうか。
今の若者を否定するのはやめましょう。彼らは冷ややかに現実を見ているのです。その直観は少なくともあなたより正しいと思ったほうがいい。若者がどれほど苦悩しながらこの生きにくい世を生きているのかを私たちは身をもって知らねばなりません。そして私たちは改めて「金と人」とのはざ間にシッカリ立って、何が本当に大切なのかを真剣に考えなければならないのです。
こんな社会を無反省のままにつくってしまったのは、けっして「持てる人」だけではありません。手をこまねいて放り出していた私たち自身にも間違いなくその責任があるのですから。
次代を背負って立つ子どもたちや若者たちに人間のいのちの大切さを、そして心のありようを伝えていかねばならない。
どんなに私たち1人ひとりがちっぽけな存在であろうとも、私たちが投げた小石は波紋をつくり、それが真実ならば、きっと大きく広がっていくに違いありません。
自分の住む町をきれいにしたいと、1人の若者がゴミを黙々と拾い集めていた。ある日彼は、ゴミを拾うのも大事だが「ゴミを捨てないで」と人に訴えることも大事だと、自ら経営する理容室のお客様を中心に働きかけだした。そしてその輪は静かに広がり、町は少しずつきれいになっていった。彼は言う。「僕の訴えを一番素直に受け止めてこの運動に参加してくれたのは、あの良識がないと鼻つまみになっている若者たちと学校に通う子どもたちでした」。今彼は、町のゴミ拾いにとどまらず、川岸のゴミも除き、海洋投棄の中止を訴え、また人気コミックの作者やTV局のプロデューサーにまで、タバコを捨てるシーンの排除などを訴えている。
(大分県佐伯市城南町:ヘアカラー・シャンプー 秋吉質広氏)
心の時代といわれて久しく時が過ぎました。その訴えがいかに空しいものであったかは、現実を見れば誰にでもわかります。
何を大切にして生きているか
無邪気な姿で駆けまわる子どもたちが、いつの日かこの砂漠のような社会でずたずたに傷ついていくであろうことを思うと背筋が寒くなります。いやいや、もうすでに傷だらけになっているかもしれない。
私は、時が許す限り若者たちと話し合います。どんなに意見が違っても拒絶されても、けっして諦めずに。それでも対話の中で私は、若者たちの多くが私たち「オトナ」に対して非常に強い不信感を抱いていることを知り、呆然として言葉を失うことがたびたびあるのです。彼らは心の中を見せようとはしない。家庭でも学校でも一個の独自性ある存在として遇された経験を持たず、受け容れてもらえず否定ばかりされてきた彼らは、社会に出てみれば、さらに強い枠組みに縛りつけられて、何かをするという前にすでに挫折感に満ちあふれているのです。
「職場で思いきり自分を出しているか」という問いかけに、「ハイ」と答えた若者に私はまだ1人も出会ったことがありません。
「あなたの人生で最も大切なものは何か」という問いに、自信をもって答えた若者に私はまだ1人も出会ったことがありません。
この社会にあって、生きていくための、そして自分を確立していくための意識の「核」を若者たちは持ち得ないのです。それなくして自分の行くべき満ちもなすべきことも明確になろうはずがない。強固な社会の枠組みにはめ込まれて「個」の独自な生き方を無視され否定されつづけ、若者は失意の中でその特質たる自己主張を放棄してしまったのです。
あなた自身の若い時はどうだったのでしょうか。
そして今のあなたはどうでしょうか。
今でも、もしあなた自身が意識の「核」を持てないでいるとしたなら、人を育てることも、仕事の上で真の繁栄をもたらすことも、とても難しいと言わざるを得ません。だからこそ気づいた今が出発点なのです。
気づきに遅すぎることはけっしてありません。
理性の修練
21世紀は、明らかに20世紀とは違う波が打ち寄せてきています。「真に大切なものは何なのか」を誰もが見出そうとしているのです。自分が「人間らしい人間として生きる」ために。
そのために、私たちは何を学ぶべきなのでしょうか。
失われた人間性を回復するために、私達には今「理性」を深める学びが必要だと、私は思っています。
「理性」ときいて、何だそれは? と頭をかしげる方もおられることでしょう。学校では学ばなかったけれど、とても大切なことです。
理性とは、人間(じぶん)が人間(じぶん)らしく生きるための能力であり、
人間(じぶん)の真実を主張する勇気である。
私たちはこの社会で生きていくための智慧を親をはじめとして多くの人たちから教わってきました。特に学校生活を終えて社会人になろうとするときには、社会で生きるにはこうしなければならない、ああしなければならないとさまざまな戒めを与えられました。常識とか社会通念を知り、おかげで何とか社会人としてやってこれたのですが、しかし、何だかいつもどこかが不自由な自分をも感じてもいたのです。
怖いのは、その不自由に慣れて不自由に麻痺してしまうこと。社会なんてそんなものさ。思い通りに生きようなんて望むこと自体が間違いだ、なんて言い出すこと。
若者は言います。「職場で自分らしさなんて出せません。出せばまわりの人たちに迷惑をかけてしまうから……」と。
「オイオイ、そんな生き方で本当にいいのかい?」
と私は頭に血をのぼらせながら叫んでしまう。
こんなに若者を白けさせてしまったのは誰なんだ!
オーナーが自分の夢をかなえるためにスタッフを手足のように使う時代は終わったのだ。しかし、悲しいことに、スタッフを手足どころか雑巾のように使い捨ててしまうオーナーもいまだに少なくはない。
21世紀は、スタッフ1人ひとりの夢の実現をバックアップするのがオーナーの責務だと私は思っています。
スタッフの夢を買い取って、それを実現に向けていくのがオーナーの最大の仕事なのだと申し上げたいのです。
ワン・トゥ・ワンの真髄
ひとりの人間を尊厳をもって遇すること、つまり「人格と個性」のある存在としての個人に丁寧に接することが、人間関係におけるワン・トゥ・ワンです。
ワン・トゥ・ワンの思想なしにはもはや何事も成就しないでしょう。
ワン・トゥ・ワンは「あなたのいのちとわたしのいのちのふれあい」だからです。そしてこれこそが「理性」の学びともいえるでしょう。
言葉で言うのは簡単ですが、行うのはそう簡単ではありません。そこで、人間が人間らしくあるための「権利」というものにふれてみたいと思います。
①「へっぽこ人生、失敗だらけ」を地でいく権利
何の失敗も挫折もせずに成功した人を私は知らない。ドジでマヌケでトンチンカンなあなた(ごめんなさい)が失敗を繰り返し、挫折を繰り返して現在に至ったことを、そしてそんな自分をいつも暖かく見守ってくれた人がいたことを忘れてはならないのです。
「できて当たり前」という言葉は辛い。できない人をさげすんでいるから。「できなくて当たり前」なのが人間。どんなに修練を積んでも、私たちは生涯未完成な「へっぽこ」野郎でしかないのだから。
年々、失敗を恐れる若者が非常に増えています。不況下危機感におびえた経営者が失敗を許さなくなったからでしょうか。そういうサロンを見ると、毎日の仕事が習慣化し作業化してしまって、変化も新しい風も受け容れようとしない。そして例外なく衰退の道をたどっている。
あなたが繁栄を望むなら、「失敗する権利」をぜひあなた自身が行使し、またまわりに伝えていただきたいのです。
②「辛いときには辛い顔をする」権利
悲しいときにも苦しいときにも笑顔でいよう!なんて人間じゃないよ!
あるサロンの店長がセミナー中、突然うずくまった。どうした? と聞くと腹痛だとニコニコ笑って言う。薬で収まるかと思っていたら、今度は床に突っ伏した。痛みを体全体で表しながらも彼は依然として笑顔なのだ。救急車を呼んだ。搬送中も笑顔でいる彼に、私は思わず「痛いときには痛い顔をしろ」と怒鳴ってしまった。結局入院。
回復後、彼は語った。「小さい頃から親に、人とうまくやっていくには嫌なときでも笑顔にしていることだと徹底して教えられました」と。そうしているうちに彼は自分の感情がわからなくなり、他人の気持ちもわからなくなってしまい、ひたすら笑顔で取り繕うしかなくなったといいます。
自分の感情を持ち、それを表現することは人間の大切な権利。この業では「プロは常に笑顔」が常識。だが、その笑顔を無理につくり続けたために感情にもつれを起こし、心のバランスを崩してしまったスタッフがいることを、あなたはご存知でしょうか。
③「ちゃんと聴いてくれー!」という権利
あなたが真剣に話をしようとしているのに聞き手がそれを茶化したり、軽く流そうとしたり、あるいは無視されたらとてもイヤでしょう。聞き手が不利な立場に陥りそうになったり、あまり深入りしたくないと話をあぐらかしてしまいがちです。そんな仕打ちを受けて深く傷つき、心も口も閉ざしてしまう人も少なくありません。しかし、そこでひるまず「まじめに聴いてくれ」ときちんと主張することが大事です。
④「お願いだから私の望みをかなえて!」と要求する権利
私たちは多くの場合、他人の援助なしでは何もできません。また人に甘えたくなることもしばしばあります。でも、断られることを恐れたり、嫌われはしないかと心配したり、押しつけになることを恐れたりして頼むことをやめてしまうことってありませんか?
心配ご無用!どのようなことでも求めることは全くOKなのです。ただし、ここが肝心、それを相手が断ることも完全に個人の権利であることもちゃんと知っておいてのことですよ。
⑤「いやなものはいやー!」と断る権利
私たちの多くは、断ることが下手。断る理由がないと断ることができないと思ってしまうし、時たま断ったとしても後味の悪い思いをしてしまう。また、目上の人や職場の上司に対してはさらに断りにくい。
しかし、ここも肝心、断るための理由なんか全く必要がないのです。相手がだれであろうと、理由が何もなくとも、私たちは「罪の意識なしに、イヤだと断る」権利をもっているのです。
要求することも自由だが、断ることも自由だというわけです。
この④と⑤の権利を知らないで、どれほど窮地に追い込まれる人がいることでしょうか。
⑥「今は言わない」と自己主張をしないことを選ぶ権利
自己主張というものは、すればいいというものではありません。自己主張すればすべての問題が解決するわけでもありません。
私たちは、自己主張をしないときを見定めることも大切で、現実を見ないで解決しようとするような自己主張は、かえって妨害的になることもあるのです。自己主張を避けるのではなく、自ら選んでしないことも大切なことでしょう。
プロと顧客のさびしい関係
私たちは、仕事の上での繁栄を願うとき、当然のことながらプロと顧客との関係に意識がいってしまいます。プロとしての自分はどうあるべきか、顧客の満足とは何か、に始まってさまざまなコンセプトが生み出され、それに基づく経営戦略が考えられ実施されます。
それはそれで重要なことで、否定するつもりなど全くありません。
だが、私はここで一言苦言を呈したい。客の1人として。
まずは「顧客のニーズ」というやつ。ニーズに応えるというけれど、何十年も客をやっている私がニーズなんて問われたことがない。客に聞かないでどうやってニーズを察知しているのでしょうかねぇ。
顧客のニーズという大義名分を掲げて、実はサロン側のニーズを客に押し付けているだけではないのかという気がしないでもない。特にあのキャンペーンと称する怖いイベント。技術にせよ商品にせよ、一生懸命薦めてくださる。その姿に心打たれて(?)苦笑いの購入と相成るのだが、私は過去一度たりとも「この人は本当にオレのことを考えてくれているんだなぁ」なんて感じたことはないんだゾー! でもまあ、これは私の不徳の致すところなのでしょう。スミマセン。
もうひとつは、あまりにもマニュアル化・システム化しすぎてはいないだろうか、ということ。素敵な空間を演出しているのに、いざ始まると私はあたかも髪処理工場のベルトコンベアに乗せられたような気持ちになってしまう。「ここにいるのはオレではなくて、オレのアタマがいるだけなんだ」と、失礼ながらかなりひねくれた考えになってしまうのです。と言って会話がないわけじゃない。しかしここでも私の心は文句をタレる。「オレは、天気の話や、ニュースの話をしに来たんじゃないんだゾー。そんなのオレのニーズじゃないゾー!」と。
そんなわけで、私は時々淋しくなってしまうのです。
花咲けば人集う
プロと顧客の関係は、その根本が「取引関係」ですから、顧客は希望通りにやってもらい、プロはその報酬を受取る。そこではプロとしての技量が大いに影響するから、その修練に力をいれることはわかります。だが、どれほど技量がすぐれていても、今の時代はそれだけで客を呼ぶことはできない。それだけではいかにもサビシイ。
プロはプロ以前に人間であるし、顧客もまた客以前に人間であるのです。ビジネスを越えた目に見えないところに重大な接点があるのです。
1対1の人間の間で「いのちのふれあい」ができるかどうかが、これからのサロンの繁栄のキーポイントになるでしょう。
顧客のニーズとあえて言うならば、顧客はこの殺伐とした社会にあって、間違いなく「いのちのふれあい」を求めているのだと私は思います。そのニーズが潜在意識下におあって顕在化していない顧客も多くいますが、どんな笑顔でいようが顧客という人間も孤独や不安約のうを抱えて生きているのです。私たちみんながそうであるように。
「ビジネス」というこtばですべてを割り切る時代は過ぎ去りました。
ハッキリ言わせていただこう。
健常人を相手にする数あるサービス業の中で、これほど人間関係が必要とされる仕事はこの業をおいて他にない。
理美容業界は人間性回復の先導者なのだ。
21世紀は「いのちの時代」。
桜の花が開けば、人はそこに集う。
桜は集客などしない。その魅力に惹かれて人が自然に集まってくるのだ。
あなたのいのちが輝けば、その輝きにふれたくて、人は自然に集まってくるのです。
裕隆コメント:
さらに突き詰めて価値と価値の交換を考えた末に、プロと顧客の関係や「ニーズ」について再定義してきた。
ほんもののニーズとはなにか。それは本質的に顧客が理解しているものなのか。
いずれ自分の言葉で書き直したい。
人間性回復の経営学(全12回)
| 回 | テーマ | サブテーマ |
|---|---|---|
| 1 | 第1回講義 心の枷(かせ)をはずしてみよう | 常識との対決...思い通りの人生を歩むために |
| 2 | 第2回講義 自分は一体何者なんだ | 自分の臭さに気づいていますか |
| 3 | 第3回講義 人間関係の極意教えます | (極意につき極秘) |
| 4 | 第4回講義 人間尊重こそ繁栄の原点 | 手間暇惜しまず "one to one" |
| 5 | 第5回講義 感動と絶望について | 説得では何も変わらない |
| 6 | 第6回講義 不安と孤独について | お触りサロンのお勧め |
| 7 | 第7回講義 犯人は誰だ! | 犯人は◯◯だ! |
| 8 | 第8回講義 停泊中の船舶に告ぐ…直ちに出航せよ | 経営とリーダーシップについて |
| 9 | 第9回講義 決別の決断 | 1本の命綱を誰に投げるのか |
| 10 | 第10回講義 一流の条件 | "らしさ" の追求と発揮 |
| 11 | 第11回講義 文化の発信基地として | これこそサロンの使命だ |
| 12 | 第12回講義 もっと儲けよう、そしてもっと使おう | 愛と奉仕の実践 |