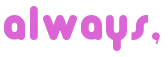蝕まれる心
人がこれほど不安に脅かされる時代がかつてあったのでしょうか。
人がこれほど疎外感に拉(ひし)がれる時代がかつてあったのでしょうか。
そう言いたくなるほど不安感や疎外感に悩まされる人が多くなっていることは、私の身辺を見ただけでも十分過ぎるくらい感じます。
一昔前のことですが、米国では2人に1人は精神科や神経科に通うか、カウンセラーを付けているといわれ、それは先進文明社会のステータスなのだ、というような記事を読んだことがあります。
心の病がステータスシンボルだなんて冗談じゃないよと、それは今でも思っていますが、しかし私たちの国も神経症大国とか精神病大国といわれてもおかしくない状況になってきているようです。
そして、そういう国で生きる私たちも、自覚症状の有無を問わず、すでに心はかなり蝕まれてしまっていて、あちこちで障害が発生していることも間違いないようです。
この偉大な自然の中で病いと向かい合えば
神様について ヒトについて 考えるものですね
やはり僕たちの国は残念だけれど何か
大切なところで道を間違えたようですね……
診療所に集まる人は病気だけれど
少なくとも心は僕より健康なのですよ
僕はやはり来てよかったと思っています
辛くないと言えば嘘になるけど しあわせですさだまさし「風に立つライオン」より
(ケニアへ巡回医療に赴いた医師を歌った詩)
多忙にかまけて
どうしてこのような事態になってしまったのでしょうか。
不安が他の時代よりも多いとか増えたとでもいうのでしょうか。
そうかもしれない。だが本質は量や種類の問題ではないのです。
私たちが不安に怯えるのは、人間として生きる力の1つである「不安に立ち向かう力」が衰えてしまっているからに他なりません。
世相は確かに激しく変化しています。その変化の大きさと速さにはついていくことすらできない。それがまた不安を大きくさせてしまう。
これも人間力のひとつである「変化に対応する力」が衰えてしまった結果であるということができるでしょう。
今あなたは、何もしないでただ過ぎ行く時を味わい楽しむゆとりをお持ちでしょうか。あるいは人生について、人間としての在り方についてなどの深い思索に時を費やすことをされているでしょうか。
そんなことをする暇があったら仕事か趣味か何かをするよ、と答えられる方もきっと多くおられることでしょう。
それはなぜ? と私は聞きたいのです。
この社会では、多忙であることが善しとされ、暇であったり何もしないでいることは基本的に許されません。
だが、私に言わせれば、いかに勤勉を装っても、いかに趣味など好きなことに没頭しようとも、結局は何かをしていないと不安でたまらなくなるから時を埋めてしまうのではないか。
いくら時を埋めたって、不安はなくならないのに……。
便利と即席のツケ
現代の科学技術の進歩を見て、私はふと思うことがあります。これらの多くは人間の不安解消をテーマにしているのではないかと。
欲しい情報は簡単に入手できるようになりました。先々のことも予測できるようになりました。テレビをつければ、本屋に行けば、インターネットを開けば、知りたいことへの答えがほぼ何でも用意されています。
そんな中で私たちは、未知の事柄に対して考えをめぐらすことをしなくなってしまった。難しい問題を、苦しみながらも自分で解決しようとしなくなってしまった。どこかに答えがあるはず、誰かが答えてくれるはず。
そうして私たちは、いち早く答えを探し出すことの能力ばかりを身につけることになってしまったのです。
不安に耐えられないから、とにかく早く答えを知ろうとする。
そうして答えを導き出すプロセスを軽視するようになり、即席の答えを得ることによって不安や孤独や苦悩といったものに立ち向かう力を失ってしまった。
だから、答えのない問題や他から答えを得られない問題に出くわすとパニックを引き起こし、精神や身体に異常をきたして、いとも簡単に病気になってしまうようになったのだと、私は思うのです。
心の病が文明病だと言われる所以はこの辺にあるのでしょう。つまり、自分の不安や孤独や苦悩の解決を他に依存してしまったことによって、温室育ちの植物のように、動物園で飼育される動物のように、私たち人間も自然の中で生きる力をなくしてしまったのです。
便利は楽です。だが、楽になったぶんだけ私たちは大切なものも多く失ってきてしまったのだ、ということにも意識を向けなければならない。
私たちが真に人間として生きようとするならば、安易に他に答えを求めるのではなく、不安や孤独や苦悩に立ち向かう勇気を培わなければならない。
そうしなければ心の病は根本的に克服されることもないし、また人間性回復もなし得ないのですから。
S君のこと
元美容師S君32歳。最愛の女性に去られ、失意の中で退社。アパートに引きこもった末に服毒自殺をはかる。早期発見で一命をとりとめ、退院直後、元上司に腕を引かれて私の主宰するセミナーに参加した。
憔悴しきった彼からは、かつて美容師として活躍していた姿を想像することもできなかったし、むしろ形相は異様なほど歪んでいた。
事情を知らない他の7人のメンバーは当初S君に何かを感じつつも無関心を装っていたが、セミナーも3日目に入り、1人孤立を続けるS君にたまりかねてグループは彼に対して真剣にかかわり始めた。
彼はとうとう自殺未遂の件を打ち明け、そして今も死にたいと言った。
21歳の女性Mさんが彼に問いかけた。
「なぜ、彼女にふられたくらいで死にたいなんて言うのですか?」
「彼女は僕が心から愛した初めての女性です。彼女もぼくを愛してくれました。3年の間、僕は彼女を大切に大切にしてきました。彼女は僕にとって唯一の生きがいでした」
「大切って、どのように大切にしてきたのですか?」
「それは僕が彼女に指一本触れたりしなかったことです」
「エッ!」とMさんは目を丸くして驚いた。
「どうしてそれが大切にすることになるの? 愛する人から手も握ってもらえなかったら、私ならとても悲しい。大切にしてもらっているなんて絶対に思えない!」
S君は苦渋に満ちた顔でいたが、やがてこう言った。
「僕が彼女に触れれば、彼女は他の男に気を移してしまう。それがとっても怖かった。でも、触れないのに彼女は去ってしまった。どうしてそうなったか、僕は今もわからなくて苦しいんです」
Mさんをはじめ他のメンバーは、S君の言わんとすることが理解できなかった。もちろんこの私も。
不安の根っ子
何度も深呼吸をした後、意を決してS君は過去を語り出した。
『小学5年生の頃、ある日学校から帰った彼が目にしたものは、父ではない男と戯れている母の姿だった。現場を見られて狼狽した母は、彼に「この人はお母さんの大好きな人」と言い、父への口止めを命じた。母を愛する彼はそれに応じた。父はまじめな会社員だった。
しかし、母の行状はそれで止んだわけではなかった。開き直ったように次々と男を変え、そのたびに息子には「大好きな人」だと言った。母の相手は日頃家に出入りする配達人や検針員などで、息子は男がどこの誰だかをみな知っていた。
彼が6年生になったとき、遂に母は夫と息子を捨てて出奔した。息子が知る限り、それは8人目の男であった。
愛する母に捨てられ、彼の母への思いは強い不信と憎しみに変わっていった。』
美容師になった彼に愛する女性ができたのは20代の終わりの頃。彼に訪れた初めての幸せを、彼はいつまでも持続したいと願った。そして、それは彼女に触れないことだと思い至ったのだった。
◇ ◇ ◇
S君の心の傷は癒えてはいなかったのです。愛する女性と母の像が重なり合い、彼は強烈な不安にとりつかれてしまいました。彼の母は「大好きな人」と触れ合った後、その男を捨てて別の男と触れ合うことを繰り返しました。
S君の不安と葛藤は彼女に「大好き」といわれたときから始まりました。1人の男として彼女を抱きしめ触れ合いたいという衝動と、それをしたら彼女は他の男に走るという不安を超えた恐怖感との闘いの中で、彼は触れないことを選択せざるを得なかったのでした。
彼女を失うかもしれないという不安の根っ子に何があったのかと言えば、彼女を信じきれない自分、つまり女性不信の自分がいて、さらに掘り起こせば、「自分のような男ではだめになるかもしれない」という自分自身への不信と懐疑があったのだということができるでしょう。
そして、自己不信と懐疑の根には「母と子の関係」があったのです。
執着からの開放
さて、このS君はその後どうなったでしょうか。
セミナーで残された時間は2日間。
S君はもとより他のメンバーも散々悩みました。S君にしてみれば3日前までは赤の他人で2日後には再び離れ離れになる人たちが、どうしてここまで自分のことを一生懸命思ってくれるのかが理解できませんでした。
同時にMにさんたち7人のメンバーも、今までの人生の中でこれほどまで他人のことを自分のことのように思ったことはなかったという不思議な実感の中にいました。
S君の話を聞き、声をあげて泣くメンバーを見て、S君は激しい感動に襲われました。それがS君が立ち直り、生きようとする出発点になったのです。仲間としての強い連帯感が生まれました。だが、それだけではS君が本当に立ち直ることはできないと誰もが感じていました。
彼が克服すべき課題は、母を赦(ゆる)すことでした。
この課題をS君は断固として拒絶しました。セミナーを放棄して帰ろうとしたのです。そのとき、あのMさんがS君に向かって叫びました。「あなたはお母さんを人間として認めていない。お母さんのことをわかろうともしない。自分が捨てられたからって、いつまでいじけたら気が済むの? そんなに弱いあなただから彼女は去って行ったんだ。今度は私たちのことも捨てるのね。そんなあなたは人間じゃない!」
彼は思いとどまりました。
それから丸1日、苦悶を重ねながらも彼はもう逃げたりはしませんでした。
涙と汗にまみれた彼が最後の大波にぶつかり、そして遂に乗り越えたのでした。
それは、肉親の情愛を断ち切るということでした。誰でも陥ることですが、子は母を母としか見ようとしないし、また子にとって都合のよい母親像のみを要求してその期待に応えてくれなければ憎むことさえはばからない。子にとって母は人間ではない。肉親の情愛は、2人が1人になってしまったような癒着を生み出し、互いを一個の人格として認めることがなかなかできない。癒着は醜い執着を呼び起こす。
S君は、母が1人の人間として苦悩の果てに、世間の非難を浴びながらも自分の生きる道を選んだのだ、ということを自ら感じとったのでした。自分が今こうして死まで考えるほど悩んでいるように、母も人間として同じように転び傷つき、悩みながら生きてきたのだと……。
何に安心を求めているのか
私たちは不安から逃れようと安心の対象を求めてしまいがちです。財産や地位や名誉、事業の成功、そして親子や夫婦もしくは恋人同士の相互依存、さらには宗教。
とにかく、それさえあれば安心だと血眼になって追い求めたり、あるいは何か絶対的なものを自らつくり出してそれに依存する。
依存関係は、この場合、助け合いではなく凭(もた)れ合いでしかない。
だから、安心をもたらしてくれるはずの対象が無くなったり、凭れる相手がいなくなると天地をひっくり返したようなパニックにおちいるのです。
さらに考えてみれば、こうして私たちは今生きているけれど、いつ来るかわからない死というものを必ず迎えなければなりません。
死の不安は、それに立ち向かって克服できるものでしかありません。だから、死の不安に対しては、そこから逃げたり意識せずにいるのではなく、むしろ死の不安をはっきりと自分の意識に置いて「引き受けなければならない」ものなのだということができるでしょう。
では、私たちがこうして生きている意味、やっていることの意味は何かあるのでしょうか。誰しも自分の存在が無意味だなんて思いたくない。
だが、私たちは自分の意思とはかかわりなく生まれ、自分の意思とはかかわりなくやがて死んでゆく。
自分が今こうして生きていることの根本的な理由はどこにもない。
毎日忙しく仕事をしているが、それに意味があると思っているのは自分の単なる思い込みで、客観的には何も意味がないかもしれない。
私たちは、この根本的な自分の存在の無意味性というものから目を背けて、どこかに自分の存在の意味をもたせようと一生懸命になってしまいます。しかし、私たちが外側に向かって人生の意味を求めていく限り、そこには意味がないのだ。
外側にはまったく意味がないにしても、だが、私たちは一回限りの人生の中で、自分自身の生きてゆく態度に意味と価値を実現することができるのです。
『生まれつき病弱で、学校にも満足に通えない少年がいた。クラスでやる行事や活動には何も参加できず、体育も校庭の隅で見ているだけ。彼の願いは「人の役に立てる自分になること」だった。だが彼の願いとは裏腹に悪化する病魔の前に、彼は人の世話になって生きるしかなくなってしまった。しかし決してあきらめずに病と闘った。死が彼を訪れる直前、彼は日記に書いた。「とうとう人の役に立つことはできなかった。でも、ぼくがこうして生きていること、それしかできないけれど、これでいいんだよね。」
生きていることの喜びを抱きしめながら、少年は静かに死を迎えた。11年の人生であった。
人間元来無用者
役に立つこと、つまり役割を担うことが私たち人間の根本的価値ではありません。なぜなら、いかに重要な役割といえども、それは私たち1人ひとりの固有のものではなく、すべてが代理可能なものであるからです。
自分の存在の根拠を役割に置くと、その役割に執着するようになります。しかし、私たちは常に役立っているわけではない。役に立っているときはいいとしても、役に立たなくなったときには、自分の存在根拠を失って混乱してしまう。そして、何かにしがみつこうとして不毛かつ不合理な行動に走ってしまうのです。
役割や能力、業績や富、そして地位や名声、そんなものがすべて無くなったとしても、私たちはこうして生きている。それぞれが、この世にたった1人。かけがえのない「いのち」をもって生きているのだ。
自分に意味や価値がなければ生きられないような考え方が、この社会にカビのようにはびこっている。それに惑わされてどれほど悩み苦しんできたかを、しかもそれがいかに不毛な苦悩であったのかを、私たちはハッキリと意識をしなければならない、と私は思う。
私たちは今こうして存在してしまっているけれど、存在しなければならない理由なんてどこにもない。いなくてもかまわない。存在すべき価値とか意味とか、そんなものは本来何もない。
人間だれひとり有用の者なんていないのであり、根本の意味においては、みんな無用者なのだ。
そういう存在である自分をきっぱりと引き受ける。
そして、今晩にはもう死ぬかもしれないという可能性をもつ自分をそのまま引き受ける。
それが、錯綜した現代を生きる私たちが、本当に人間としての感覚を取り戻すただひとつの態度ではないか、と申し上げたいのです。
(今回の副題「お触りサロンのお勧め」は連載の最終回に組み込ませていただきます)
人間性回復の経営学(全12回)
| 回 | テーマ | サブテーマ |
|---|---|---|
| 1 | 第1回講義 心の枷(かせ)をはずしてみよう | 常識との対決...思い通りの人生を歩むために |
| 2 | 第2回講義 自分は一体何者なんだ | 自分の臭さに気づいていますか |
| 3 | 第3回講義 人間関係の極意教えます | (極意につき極秘) |
| 4 | 第4回講義 人間尊重こそ繁栄の原点 | 手間暇惜しまず "one to one" |
| 5 | 第5回講義 感動と絶望について | 説得では何も変わらない |
| 6 | 第6回講義 不安と孤独について | お触りサロンのお勧め |
| 7 | 第7回講義 犯人は誰だ! | 犯人は◯◯だ! |
| 8 | 第8回講義 停泊中の船舶に告ぐ…直ちに出航せよ | 経営とリーダーシップについて |
| 9 | 第9回講義 決別の決断 | 1本の命綱を誰に投げるのか |
| 10 | 第10回講義 一流の条件 | "らしさ" の追求と発揮 |
| 11 | 第11回講義 文化の発信基地として | これこそサロンの使命だ |
| 12 | 第12回講義 もっと儲けよう、そしてもっと使おう | 愛と奉仕の実践 |