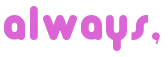回復の世紀
私たちが今まさに体験している百年に一尾の世紀の変わり目は、例えるなら振り子がいっぱいに振れて向きを変える瞬間だということができるでしょう。この偉大なる転換期、振り子はどこに向かって行くのでしょうか。
(問い) その行き先は誰が決めるのでしょうか。
(答え) それは、あなた自身です。
(問い) 行き先には何が待っているのでしょうか。
(答え) それは、あなたが心から願っていることです。
(問い) 私は何をすればいいのでしょうか。
(答え) あなたが本当にやりたいことです。
◇ ◇ ◇
前世紀、私たちは願い通り欲しいものを手に入れることができました。経済的・物質的豊かさです。だが、その代償は計り知れないほど大きいものでした。環境破壊、戦争、貧困と飢餓、多くの生物の絶滅等々、力のある者が無い者を支配し、結局は人間が人間として生きられない世界を造ってしまったではありませんか。
今、こうして新世紀が始まり、あちこちで前世紀の膿(うみ)が噴き出している中で、振り子の行方をまるで他人事のように傍観しているだけならば、私たちが本当に望む世界などけっして造ることはできません。
自分に都合の良い事態は当然のようにぬくぬくと享受し、都合の悪い事態が起こればここぞとばかりに当事者を糾弾してしまうようなご都合主義から足を洗って、自分の決断と責任の中で生きる姿勢を取り戻さなければ、振り子は永遠に行方不明になってしまいます。
失った大切なものを回復し修復していこうとするならば、もう「見物」をやめ、人の為すことの「評論」をやめて、私たちが自ら動き出さねばならないと私は思っているのです。
あなたが主役!
今、私たちに必要なことは「自立」。自分の足で立つこと。
つまり「自分で考え、自分で決断し、自分で行動して、その行動に責任を持つ」という生き方をやっていくこと。
これが新しい時代を生きるキーワードなのだ、と申し上げましょう。
「赤信号みんなで渡れば怖くない」時代は過ぎ去って、「赤信号みんなで渡れば集団自殺」の時代になったのです。
じっと耐え、沈黙を守ってきた若者たちが立ち上がり、動き始めました。彼らは古い秩序を崩壊に導き、形骸化した体制や仕組みを粉砕して、「本物」を見出していくに違いありません。
このような転換期は、新旧の価値観が激しくぶつかり合う時代です。古い価値観に固執し、新しいものを受け容れられないでいるならば、そのような方々は一刻も早く意識を転換するか、それができないのならすみやかに第一線から退くべきだと思います。
過去の栄光や成功は、却って現在及び未来の癌になるということを、私たちは心得ておかねばなりません。
これからの世の中は「何がどうなっていくのだろう」と不安な気持ちでいる方に申し上げます。これからは「あなたが何をどうしたいのか」が問われる時代なのです。
けっして受身一方にならず、また誰に対しても服従することなく、また誰をも支配せず、私たち1人ひとりが自分の唯一の人生を「主役」で通し切ることを、何より大切にしていただきたいと思うのです。
どんな人生を歩もうと、たとえそれが悲惨を極めたものであろうと、けっして他人のせいにすることはできません。なぜなら、私たちの人生は、原作も脚本も主演もすべてが自分自身だからです。
また、生まれ育った境遇にしても、生まれ持った才能や容姿にしても、それが他より劣るからといって親のせいにしたり、世を恨んでみたところで何の解決にもならないばかりか、自ら人間性を歪めてしまっていることにも気づかねばなりません。
私たちに大切なことは、いかなる境遇を与えられても、いかなる悲惨な体験をしようと、常に「そこからどう生きるか」ということなのではないでしょうか。
自分ほど厄介な者はない
大げさに聞こえるかもしれませんが、前述の通り、新時代の行く先を決めるのは、あなた自身。しかも、あなたの願った通りになる。
とすれば、あなたの願いというものが重大なカギになってきます。
まさか、そんな自分の願いが世界を動かすなんてあり得ない、と多くの人は思っています。そして、自分ではない誰かが世界を動かしているのだと思っています。それが誰なのかも確かめないままに。
もし世界を動かす誰かがいるのなら、それは誰なのでしょうか。
それを「神」だというならば、神は人の心を映し出す鏡であるという意味において、私は信じるでしょう。
やはり、それは私たち1人ひとりなのだと言うしかありません。
あなたが毎日生きている世界は、あなたが直接かかわり会うことのできる小さな世界。限られたごく少数の人たちと生きているのであって、けっして地球上の63億人や日本の1億3千万人を常に意識において生きてはいないはずです。
だからこそ、あなたが日頃かかわる身近な人たち、あなたの影響が直接及ぶ人たちとともに、人間らしく生きられる世界の実現を願って勇気ある行動をしていくことが大切なのだ、と私は叫びたいのです。
より良い世界を造るためには、より良い人間関係を造ることが必要だし、そのためには何といっても自分自身を磨かねばなりません。
なぜ、自分を磨かねばならないのか!
それは、この世で自分ほど厄介で手の焼ける存在はないから!
そして、この厄介者が周りに多大な影響を及ぼしてしまうから!
自分の垢を落とさなければ、臭くて人迷惑になります。おしゃれが他人への思いやりであるように、心もおしゃれでいたいもの。
あなたが、もし人とのかかわりの中でうまくいかないことがあるとするならば、そしてそこで苦境に陥っているとするならば、それはけっして相手のせいでもないし、状況のせいでもないのですよ。
もし、理不尽な相手にあなたが苦しめられているとするならば、それはあなたが自分の「いのち」を守るために立ち向かっていないからです。あなたが屈して自分の真実を放棄してしまっているからです。
自分を悲劇の主人公にしている限り、そしてそんな自分をわかってほしいと同情を求めている限り、あなたは自分で自分を衰退させ破滅に導いているだけだということを知らねばなりません。
事実を事実として認める
とは言っても、これまた言うは易し行うは難しで、困難にぶつかると私たちはどうしても他人のせいにしたくなってしまうし、そこから逃げ出したくなってしまいます。そうしたところでけっして困難は克服できないのを重々承知しているにもかかわらず。
そうして、私たちは往々にして出来ない自分を責め、自分をダメな人間に仕立て上げてしまうのか、反対に、相手を非難しているうちに自分のほうが手のつけられないほどの傲慢さを身につけてしまうのです。
このようなことを偉そうに書いている私自身をみれば、長く生きてきた分だけ垢も多くてうんざりしていることも事実です。
今までの人生を振り返れば、確かにいろいろな経験もしたし、苦難にも出会いました。数え切れないほどの失敗、そして挫折。そのおかげで少しは強くなったかもしれない。だが、それが何だというのでしょうか。幼い頃の情けないほど弱かった私は、しかし、今の私よりはるかに人間的だった。泣いてばかりいたけれど、やさしかった……。
自分を磨くということは、一体どういうことなのでしょうか。
どうやら、いかに人生を長く体験しようとも、人は自然に磨かれるものではないようです。
しかし、私たちの心には「ありたい自分」や「あるべき自分」があってそこに近づきたいという願望が少なからずあります。
しかし、それが落とし穴になって人間性を損なうこともあるのです。
Aさんは優秀な成績で学生時代を終え、前途を嘱望されて社会に出た。仕事でも期待通りの能力を発揮し、結婚もしてすべてが順調に運んでいるように思われたが、彼にとっては予想外の結婚生活の破局を機に、仕事も歯車が合わなくなり成果も上がらず低迷することになった。挫折から立ち直れなかった彼は、酒と女に逃げ込む自堕落な生活に溺れた。何度か仕事を変えてみたが状況は変わらず、鬱状態に陥って神経科に通う身となった。
彼はいつも思っていた。「今の俺は本当の自分ではない」。
彼にとっての本当の自分は、あの若き日の輝かしい姿の自分だった。
私がAさんに会ったのは、彼が精神安定剤を服用して10年が経った頃でした。穏やかな笑顔を見せてくれたものの、目にはまったく生気がなく、言動は緩慢でした。彼は自分のことを嫌っていました。
私は彼に問いました。
「財布に1000円あった。900円の買い物をした。帰って財布を見たら10円しかなかった。本来100円あるべきなのに、実際は10円だけ。さて、あなたにとって本当は100円と10円のどちらなのか」
彼は「本当は100円です」と答えました。
私は「あなたは、あるべき100円、あるはずの100円が本当だと言う。あなた自身についても、あの溌剌(はつらつ)としていた若い頃の姿が本当の自分だと思っているのですか」と問うと、彼は「その通りです」と答えました。
彼の病気が治らない原因はここにありました。
あるべき自分もありたい自分も、それはあくまでも架空の自分であって現実の自分ではありません。架空の自分を本当の自分(正しい自分)だと位置付けている以上、現実の自分は常に否定され続けることになるのです。
事実を否定しての問題解決はあり得ません。
問題解決は、どんな場合も事実を事実として受け容れることを前提としてなされるのだ、ということです。
Aさんは、虚像でしかない過去の輝かしい自分にしがみつき、現実の自堕落な自分の実像を否定していたのでした。
Aさんは、気づきました。自分はもっと優れた人物のはずだとウヌボレていたことに。そして、酒と女に溺れるだらしない自分が真の自分であることに。
そんな自分を認めた瞬間、Aさんの肩から力が抜け、目に輝きが戻り、体全体に生気が蘇ってきたようでした。
自分磨きの旅
自分を磨くための第1は、事実を事実として受け容れることです。大きくなりたいと願う自分は小さく、強くなりたい自分は弱い。その小さく弱い自分をそのまま肯定する。良し悪しの評価をしないこと。
そして第2は、自分磨きには完成はないことを知ることです。特に年齢や経験が増すほど、固定観念が強くなり、ウヌボレも強くなることを自覚したほうがいい。仕事の能力が向上したり、重要な地位についたりすると、人間性まで高まったような気になるが、それはあくまでも錯覚であることを知っておくべきです。
先にも述べたように、この世で自分ほど厄介な存在は他にないと言えるでしょう。とにかく最高に手の焼ける駄々っ子なんです。
でも、このわがままでいいかげんで甘ったれの駄々っ子を放り出してしまうと、迷惑するのは周りの人たちです。
能力のある人ほど、地位の高い人ほど公害を至るところでまき散らしてしまう。この私の拙文をお読みくださっているあなたも、間違いなく公害製造元ですよね。しかも高性能の……(失礼!)
だからこそ、自分を磨かねばならないのですが、これまた残念なことに生涯かけても磨ききれるものではありません。死ぬまで公害をまき散らしていくしかない。じゃあ、どうすればいいのか。
「ごめんなさい」と謝るしかないのです。それしかないのですよ。
自分を磨くということは、「謙虚に生きる」ことを学ぶことだと言ってもよろしいかと思います。
犯人は誰?
私たちは、人とかかわりながら生きています。普通、自分が嫌いな人とのかかわりは難しく、好きな人とのかかわりはスムースにいくと思われています。
だが、よく考えてみれば、嫌いな人とはかかわりを持とうとはしないし、むしろかかわりを避けようとするのですから、難しいという以前にかかわりは生じないのです。
問題は、好きな人です。愛すれば愛するほど深いかかわりが生じます。愛する人とのかかわりは、共に生きるよろこびや幸福感を生み出す一方、独占欲に根ざした支配や嫉妬などでかかわりを損ねてしまうこともよくあることです。かかわり、つまりいのちといのちのふれあいは本音の中で表現するものゆえに、互いの公害をもろにぶつけ合う関係にもなってしまうのです。
「この世でもっとも愛する人こそ、かかわることがもっとも難しい」と言うのは、私の経験から生まれた苦い教訓なのですが、あなたの場合はいかがでしょうか。
近年、離婚が急増しているそうですが(実は私もその1人なのです)、この現象は相手の吐き出す公害に耐え切れなくなってのことと、それが元で夫婦がかかわらなくなったことが原因になっていることが多いようです。
女房1人うまくリードできない者が、他人など使ってやっていけるはずがない、と言われますが、私は声を大にして反論したい!「女房ほど難しい相手なんてどこにもいないゾー!」と。
これをお読みの奥様方、ごめんなさい。でも本当なんです。
外で偉そうに人間のことなどを喋りまくっている私なのですが、妻の前ではまったく形無しなんでございます。
話がそれてしまいました。
とにかく、家庭においても、職場においても、そこにいる人たちの楽しくない状態でいたならば、「なぜ楽しくやらないのか」などという愚かな叱責をやめて、誰がそうさせているのかを考えてみましょう。
聡明なあなたは、もうおわかりのことでしょう。
そうです。「犯人は自分」なのです。
どんな問題でも、探っていくと必ず自分にもその原因があることに気づくはずです。全部の原因があなたでないにせよ、あなたがその問題の責任は我にありとキッパリ引き受けたときから、事態は好転し問題は解決していくことでしょう。これが大人の決断です。
しかし、大人であることを意識しすぎると、物事はこんがらがってしまいます。そんなとき、幼い頃に戻ってみれば、きっとあなたは自分らしい自分を見出すことができるでしょう。
人間、どう生きるか、どのようにふるまい、どんな気持ちで日々を送ればいいか、本当に知っていなくてはならないことを、わたしは全部残らず幼稚園で教わった。人生の知恵は大学院という山のてっぺんにあるのではなく、日曜学校の砂場に埋まっていたのである。
わたしはそこで何を学んだろうか。
●
何でもみんなで分け合うこと。
ずるをしないこと。
人をぶたないこと。
使ったものはかならずもとのところに戻すこと。
ちらかしたら自分で後片づけをすること。
人のものには手を出さないこと。
誰かを傷つけたら、ごめんなさい、と言うこと。
食事の前には手を洗うこと。
トイレに行ったらちゃんと水を流すこと。
焼き立てのクッキーと冷たいミルクは体にいい。
釣り合いの取れた生活をすること……毎日、
少し勉強し、少し考え、
少し絵を描き、歌い、踊り、遊び、そして、少し働くこと。
毎日かならず昼寝すること。
おもてに出るときは車に気をつけ、手をつないで、
はなればなれに
ならないようにすること。
不思議だな、と思う気持ちを大切にすること。
●ロバート・フルガム「人生で必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ」
人間性回復の経営学(全12回)
| 回 | テーマ | サブテーマ |
|---|---|---|
| 1 | 第1回講義 心の枷(かせ)をはずしてみよう | 常識との対決...思い通りの人生を歩むために |
| 2 | 第2回講義 自分は一体何者なんだ | 自分の臭さに気づいていますか |
| 3 | 第3回講義 人間関係の極意教えます | (極意につき極秘) |
| 4 | 第4回講義 人間尊重こそ繁栄の原点 | 手間暇惜しまず "one to one" |
| 5 | 第5回講義 感動と絶望について | 説得では何も変わらない |
| 6 | 第6回講義 不安と孤独について | お触りサロンのお勧め |
| 7 | 第7回講義 犯人は誰だ! | 犯人は◯◯だ! |
| 8 | 第8回講義 停泊中の船舶に告ぐ…直ちに出航せよ | 経営とリーダーシップについて |
| 9 | 第9回講義 決別の決断 | 1本の命綱を誰に投げるのか |
| 10 | 第10回講義 一流の条件 | "らしさ" の追求と発揮 |
| 11 | 第11回講義 文化の発信基地として | これこそサロンの使命だ |
| 12 | 第12回講義 もっと儲けよう、そしてもっと使おう | 愛と奉仕の実践 |