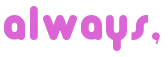トップの言い分 〜笛吹けど踊らず〜
経営トップの皆さん、あなたは下記のような問題にぶつかってはいませんか?
- 経営理念や目標がスタッフの間に浸透しない。語れば語るほど空回りしてしまう。
- スタッフと気持ちを分かち合えなくなっている。スタッフの本心がわからない。
- いくら教えても、人に気遣いや配慮ができるスタッフがそだたない。
- これから会社をよくしていこうという会議なのに、士気は上がらず、意見も出ない。
- 会議の目的は、会議を早く終わらせることになってしまっていて、目標だとか解決だとかはどうでもよくなってしまっている。
- 小さな集団なのに派閥のようなものができてしまって、互いに反目し合いチームワークがうまくとれない。
- 問題が起きると、まずは責任逃れ、人のせいにしてしまう。また、重要な問題がどこかで闇に葬られ、自分のところまで届かない。
- 危機感を感じているスタッフがいない。いたとしても対応策を提案できる者がいない。
- 技術ばかりでマネジメント意識が足りない。目標設定や実行政策などはほとんど無関心。
- 信頼しようにも「引き受ける」という姿勢を持つ者がいない。だから任せることもできない。
スタッフの言い分 〜そんな笛では踊れない〜
上記のような笛を吹いても踊ってくれないもどかしい状況が生まれたとき、あなたはどのように対処されるのでしょうか。
それを考える前に、スタッフ側の意見も聞いてみましょう。
- トップは自分の夢を語れるけれど、私の夢は聞いてくれない。
- ワン・トゥ・ワンを推奨するトップが私たちスタッフに十把ひとからげの対応しかしてくれない。
- トップが私たちスタッフにどれだけ気遣いや配慮を示してくれただろうか。
- 会議はいつもトップの独演会。ただ聞いているのは疲れます。
- 「どうしたらもっと楽しく仕事ができるか」というような会議ではなくて、マンネリを承知で義務感だけでやるような定例会議は意味がない。早く終わらせたいから発言はしない。
- 上意下達ばかりで、自由に意見を交わすことができない職場だから、どうしても本音や愚痴は裏で吐き出すことになる。
- 問題が起きるとトップの怒りにふれて当事者が責め裁かれるから、ついつい問題を隠したり責任逃れをしたくなってしまう。
- 危機だ危機だと躍起になっているトップの姿に対して危機感を感じてしまう。
- トップは、人が大事と言いながら結局は金を一番大事にする。私たちスタッフは所詮金を稼ぐための道具でしかないようだ。
- まずは私のことを信頼してください。信頼されていないのに引き受けることなどできない。信頼されないことほど淋しいことはない。
確かに笛の音は聞こえているのです。でも、スタッフはつぶやきます。「いつも同じ曲ばかり。聞きすぎてもう耳にたこ。もし踊っても、踊り方までいちいち指図されるからたまらない」。
「はず」と「つもり」の世界
どうしてこんなに互いの意識がズレてしまうのでしょうか。
「いつも伝えているからスタッフはわかっているはず」とトップは言います。スタッフは「ちゃんと聞いているし、トップの言いたいことはわかっているつもりです」と言います。
ところが何事もあきれるほどに伝わっていないのです。
「伝はあっても達がない」、つまり言葉は行き交っているけれどもその意味合いは「はずとつもり」の確認のない世界で相手に達しないまま放り出されてしまっている。
簡単に言えば、気持ちの通い合わないところにコミュニケーションは存在しえない、ということです。
コミュニケーション(意思疎通)がとれないと、憶測や偏見がはびこり、互いが不信の中で反目し合うようになってしまいます。
そうなると何をやってもうまくいかないし、それを修復するのに何から手をつけたらいいのかさえもわからなくなってしまうのがオチです。
そうなってしまったとき、私たちは何をすべきなのでしょうか。
原点に立ち戻ってみる
集団の状況が固着して身動きできなくなってしまったならば、その集団が形成された時点に立ち戻ってみましょう。そこにきっと解決の糸口がみえてくるはずです。
夫婦で仕事をしてきて行き詰まっている方は、なぜ2人は結ばれたのか、そして今何が欠けてしまっているのかを考えてみることです。
スタッフと共に仕事をしてきて行き詰まっている方は、なぜスタッフを必要としたのかを考えてみることです。
トップである自分と相手の間に意識の隔たりができてしまったとき、その隔たりを吹きぬける寒々とした風は「不信」という風。
冒頭のトップの言い分をもう一度ご覧ください。
どこかであなたはスタッフに対して不信感をもってはいないでしょうか。どこかでスタッフを見下しているあなたはいないでしょうか。
あなたは、自分が思っている以上にスタッフから疎まれているということに気づいておられるでしょうか。
それは、あなたがスタッフを疎ましく思っているぶん、しっかりとお返しをしてもらっているということなのです。
スタッフの意識はトップであるあなたの意識の反映なのですから。
人を疎むということは、存在を否定すること。そこにはすでに人間尊重(人間愛)の思想などないと言ったほうがよいでしょう。
人間尊重のベースの上でのみ「信頼」が生まれ、その信頼があって初めてコミュニケーション(心のやりとり)が成立するのです。
信頼関係の回復
上下の信頼関係の失われた職場では、スタッフ間の横の関係もぎくしゃくしてしまいます。目標に向かって互いが心を合わせる「協力」が成り立たず、したがってスタッフの団結もなされず、夢や可能性を実現に導くことは到底無理になってしまうのです。
信頼関係の失われた職場では、スタッフが「自分なんかいなくたっていいんだ」というような意識に陥りやすくなり、白けたり投げやりになったりするのも当然のことだということができるでしょう。
それほど集団においては信頼関係が重要なファクターとなります。
ではどのようにして信頼関係を回復していくのか。
蛇足とは思いますが、その手順の一例を示してみましょう。
①このような状況を引き起こしたのはトップである自分の責任であることを認める。
②今日までこの状況を放置していたことを心から詫びる。
③1人ひとりと対面し、本音をぶつけ合う。互いの心が触れ合うまで徹底して行う。
④自ら相手に対する信頼を表明する。改めて協力を依頼する。
この手順はとても手間がかかります。特に③は1人に対応するのに1時間や2時間では決して済まないということもご承知おきください。
しかも、この手順通りやったからといって、結果が常によい方向に出るとは限りません。が、やるだけの価値は十分あります。
組織盛衰の鍵はリーダーシップだ
しかし、組織もしくは集団というものはどうして状況が固着してしまうのでしょうか。その答えとして、組織や集団を形成するのは「人間」だから、というのはあまりに乱暴すぎるでしょうか。
先にも述べたように、わがままで頑固でいいかげんで独り善がりな存在が私たち人間です。とりわけ、この世でもっとも手の焼ける厄介な存在が自分自身。そして他人のことはよく見えても自分のこととなるとほとんど何も見えないのが私たち人間。常識や世間体に縛られ、習慣にどっぷり漬かり、過去にこだわり、未来に不安をいだき、多くのことに執着して自らをがんじがらめにしてしまう私たち人間。
そういう私たちが集まって何かをしようとするときに、もっとも必要とされているものが「リーダーシップ」というやつなのです。
問題解決は「策」を練ることではない
リーダーという名のつく人はたくさんいますが、リーダーシップのとれるリーダーとなるとその数はグーンと減ってしまいます。
厳しい言い方になりますが、冒頭のような問題に手をこまねいているならば、経営者であってもリーダーシップがとれない状態にあるとしか言いようがありません。
はっきり言うならば、組織(集団)の盛衰は、まさにリーダーシップの有無にかかっているのです。
まずは、下の文章をお読み下さい。
S店長は、最近アシスタントのA子さんの何か思いつめているような姿が気になっていた。「大丈夫か?」と声をかけると、今にも泣き出しそうな彼女に危機を感じた店長は、即仕事を中座して面談の場を設けた。涙をこぼしながらの彼女の第一声は「もう辞めたい」という叫びだった。「あんなひどい人を重要なポストに置いておく会社も社長も信じられません」と言う。事の真相は、彼女が同じ店で働く実力ある技術者B男にセクハラを受け、脅迫的なストーカー行為をも繰り返し受けていたのであった。
苦渋に満ちた顔で一切の話を聞き終えたS店長は、A子さんに向かい「本当に申し訳ない、毎日一緒に仕事をしながら君がそんなに辛い目にあっていることに気づきもしなかった。B男についても彼の表の顔しか見ていなかった。この件は、2人を預かる店長としての僕の責任だ」と両手をついて謝ったのである。
A子さんはもう泣いてはいなかった。「店長が私を受け止めてくれたこと、すごくうれしいです。もう辞めるなんて言いません。店長についていきます。B男に対しては私がもっと強くなります。もう大丈夫です」。目に輝きを取り戻した彼女は微笑みさえ浮かべていた。
私たちは今考えなければなりません。S店長がとった言動は、目の前にいるA子さんに100%向けられたのであり、そこにはいないB男の非道ぶりを非難したのでもなく、またB男の今後の処分について検討し約束したわけでもなかったということです。
つまり、過去に起こった問題を今後どう解決するかという策を提示することではなく、「今」傷つき苦しんでいるA子さんの気持ちをシッカリ受けとめることこそが問題解決の第1歩であり、すべてであったのだということなのです。
経営とリーダーシップの関係
リーダーシップについては、多くの書籍が発行されており、読者の皆様もかなりの研究をされてきたことと思います。しかし、書物をいくら読んでもリーダーシップは身につかない、というのが私の持論です。ハサミの使い方を書物で学んだとしても、実際に体験してみないとわからないように、リーダーシップというものも体験を通してみないと会得はできないものだからです。
経営とリーダーシップはどのような関係にあるのかをみてみましょう(図参照)
船(経営)が川(社会情勢・経済環境)を航行しています。
川は逐次その状況を変えていきます。船はクルー(スタッフ)の働きによって転覆や沈没を会費しながら目的地へと向かいます。
そして船は点検や修理、燃料等の補給のため淀みに停泊します。停泊中、クルーは役務から開放されて、心地よい日々を送ります。しかし、停泊している船には錆びがつき、蛎殻がつき、放っておくとこれからの航行に支障が出てしまいます。それを察知したリーダーはクルーの反対があろうと、エンジンをかけて再び船を川に押し出すのです。
船は泊まると腐ります。船は常に動いていなければならない。
それが船の使命なのですから。
状況が固着し、マンネリに陥ったり、無機能状態になったときこそリーダーシップというものが必要かつ重要になってくるのです。
状況を変化させる力=リーダーシップ
以前私はある会社でトップを任命されていました。幹部会議を招集したところ、ほとんどの幹部がうんざりした表情で集まってくる。当然のごとく会議はお通夜状態。にもかかわらず誰も声を出して不満を言わない。「こんな会議楽しくなーい!」と叫べばいいのに。
私は会議が始まって10分もしないうちに会議を中止しました。そして「今後すべての会議を禁止する」と幹部に申し渡して会議室の扉を即座に釘付けしてしまったのです。驚いたのは幹部たち。狐につままれたような顔をしながら解散したのですが、その後会議ができなくて一番困ったのはその幹部たちでした。
数ヶ月後、幹部からの申請があり会議は復活しましたが、それからの会議が活発に行われたことは言うまでもありません。
リーダーシップをふるうには「勇気」がいります。
周りからの非難を覚悟していなければなりません。
一旦できあがった状況というものは、たとえそれが不快なものであっても、慣れてしまうと新しい状況を拒絶する傾向が私たち人間にあるからです。そこを敢えて破ろうとする力がリーダーシップなのです。
任せて待つ
経営者の大きな悩みのひとつに「右腕づくり」があります。
特に力のある経営者の下では、右腕がそだちにくいという現実。
百戦錬磨の経営者は現状認識にせよ、先見性にせよ、問題解決能力にせよ、スタッフの誰よりも優れているゆえに問題を1人で抱え、1人で解決してしまいがちです。
幹部がいても経営者ほどの能力はないし、仮にあったとしても出番がないからその能力は使われずじまいになってしまう。経営者に任せておけば間違いないし、責任をとることもないから、幹部のリーダーシップはなかなかそだたないのです。
もし、あなたが本気で右腕をつくろうとするならば、あなたのリーダーシップはまず自分自身に向けてふるわなければなりません。
つまり、自分の状況を変化させるのです。もう自分の力だけではやっていけないことを自覚し、思い切って「任せる」勇気をもつことです。
任せても、最初からうまくいくわけではありませんから目を覆うような事態が次々と起こるでしょう。そのとき、あなたは口も手も出してはならない。目を覆っていなければならない。
任せて待つ。つまり任待です。任待には忍耐がいります。
しかし、忍耐とは「希望を持って待つ」ことだと理解すれば、それはとても楽しみなことになるではありませんか。
リーダーシップとは、自分自身を生かす力であると同時に、他人を生かす力でもあるのです。
「変化」というキーワード
最後に、これだけは忘れないでくださいね。
- 経営とは『変化への対応力』である。
- リーダーシップとは『状況を変化させる力』である。
人間性回復の経営学(全12回)
| 回 | テーマ | サブテーマ |
|---|---|---|
| 1 | 第1回講義 心の枷(かせ)をはずしてみよう | 常識との対決...思い通りの人生を歩むために |
| 2 | 第2回講義 自分は一体何者なんだ | 自分の臭さに気づいていますか |
| 3 | 第3回講義 人間関係の極意教えます | (極意につき極秘) |
| 4 | 第4回講義 人間尊重こそ繁栄の原点 | 手間暇惜しまず "one to one" |
| 5 | 第5回講義 感動と絶望について | 説得では何も変わらない |
| 6 | 第6回講義 不安と孤独について | お触りサロンのお勧め |
| 7 | 第7回講義 犯人は誰だ! | 犯人は◯◯だ! |
| 8 | 第8回講義 停泊中の船舶に告ぐ…直ちに出航せよ | 経営とリーダーシップについて |
| 9 | 第9回講義 決別の決断 | 1本の命綱を誰に投げるのか |
| 10 | 第10回講義 一流の条件 | "らしさ" の追求と発揮 |
| 11 | 第11回講義 文化の発信基地として | これこそサロンの使命だ |
| 12 | 第12回講義 もっと儲けよう、そしてもっと使おう | 愛と奉仕の実践 |