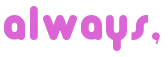人生はマラソンか駅伝か
人生80年、寿命が延びたことは喜ばしいことですが、反面、「死」というものが日常の意識から遠のいたぶん、人の生き方も間延びしてしまったのではないでしょうか。
昔50年だった人生が80年に引き延ばされ、そのぶん中身も薄まってしまったといった感じです。
病あり、飢饉あり、戦いありで、常に死と隣り合わせで日常を送っていた昔に比べ、今やすこぶる良好な生活環境の舌でのうのうと暮らし、戦争の危機にも脅かされず永い平和を得た結果、皮肉なことに私たちの「人間力」はそれらに反比例するがごとく低下してしまったのではないか、と思わずにはいられません。
歴史をたどれば多くの事例がありますが、たとえば、江戸から明示に変わる維新前夜、世を動かしたのは20代から30代の若者たちであったではありませんか。若者たちが生かされたのは、彼らの先見性と推進力を信じた先代の人たちが、自ら退いてリーダーの座を明け渡したからでした。そして若者たちの先導と活躍で日本は大きく変わっていったのです。
そして現在(いま)、長生きすることによって「退き際」を逸してしまった多くのリーダーたちは、人生にせよ経営にせよ、それがリレーであることを知りながらも、バトンを渡そうとせず1人で走り続けている。
次の走者はいつバトンをタッチされるのかもわからず、出番を待っているうちに気力も体力もなくしてしまうのです。
人生はよくマラソンにたとえられます。それはこの世で唯一無二の存在である個としての自分が、死というゴールを目指して独自の道を走りつづけるという「存在の次元」で理解されること。
一方、人間社会で役割を担う一員としての自分、つまり「社会的次元」の自分を見たときに、私たちは今改めて、人生は「駅伝」(長距離リレー)であることを意識することが必要なのではないかと思うのです。
間延びした人生、間延びした経営に決着をつけるためにも。
執着は衰退を呼ぶ
高齢化の大きな弊害は、老後の不安と心配に脅かされることです。
老後の自分に惨めさを感じる人は多くいても、老後にばら色の人生を思い描ける人はどれほどいることでしょうか。
若いときには考えもしなかった生老病死という四苦を日々実感するようになると、どうしても過去に執着してしまう。
振り返れば、夢と希望に胸躍らせた若き日、転び傷つき悩みながらも輝いていた。しかし、先を思えば、周りから見向きもされなくなり、夢も希望も生きがいも見出せず、老いの醜さを抱えながら孤独の日々を送る自分が見える。今日までこんなに頑張ってきたのに、あんなに面倒をみてきたのに……、誰も自分を顧みてくれないような気がして、つい経済力や地位・名誉、あるいは経験・実績などを誇示することで自分の存在を他に認めさせようとしてしまうのです。
役割がなくなることは、人間としての価値もなくなることだと考える人は多い。だから、歳がゆくにつれ役割にしがみついてしまうのです。
経営権を譲り、第一線から退いたからといって人生が終わってしまうわけではないし、人間としての価値が消え去ってしまうのでもない。
むしろ、譲った後にこそ大きな仕事が待っているのです。
それは人間としての生き方を、在り方を後世につたえていくこと。
私たちは、昔50年で達した人間としての域(レベル)に80年かけて達すればいいのではなく、延びた30年の命をどこまで高めていくことができるかに挑戦しなければならないのです。
それを現代の人間の使命だといっても過言ではないでしょう。間延びして、すでにかなりの退化をしてしまった私たち人間が、もうこれ以上人間力を失わず、人間として退化をしないためにも。
執着は、自らを衰退させるだけではなく、周りを傷つけ、周りを抹殺してしまうことを、私たちは深く思い知るべきです。
あなたがもし、退き際を決することができないでいるならば、何かに執着しているはず。そして、その執着が周りにどれほど多大な執着を生み出しているかということに気づかなければ、あなたはあなたのもっとも大切にしているものを必ず失うことになるでしょう。
後継とは何か
理美容業界をみると、経営を家族に継いでもらおうとする「世襲」意識を持つ人が多い。店を張り、努力の賜物としてそこで食うに困らぬ収入が得られるようになれば、そう易々と暖簾を他人に渡すわけにはいかないし、自分一代で終わらせるのはもったいない、と思うようになるのが自然な人情。世襲は当然の成り行きと言えるでしょう。
しかし、世襲にこだわって、多くの執着も生まれ出てしまいます。築いた財と、財を生み出す店の経営権を守ることが後継の第一義的目的になると、多くのことが財の保全を果たすための必要条件になってしまうからです。
子を他店に修行に出すのは将来自店を継がせるためであったり、子の結婚相手を同業者に限ろうとしたり、たとえそれらを子が自ら望んだとしても、私には何か本末転倒のような気がしてなりません。
さらに、世襲の弊害と思われるものが、親子関係の癒着。
修行中の子を親の都合で呼び戻そうとしたり、戻って来たら来たで、この店はお前のものになるのだからと暗に将来の利得をほのめかせ、だから親の面倒をみろと取引をもちかける。子は子で「親孝行」という大義名分を盾に取引に応じてしまう。しかし、親は子の未熟を理由に経営の実権をそう簡単には渡さない。バトンタッチの時宜を逸すると親子の間にひびが入り、憎しみさえ生まれ、遂には子が親の死を待ち望むというようなドロドロな関係に陥ってしまう。このような事例が跡を絶たないのは、「後継」についての考え方に無理や狂いがあるからだと、私は思わざるをえないのです。
後継というものを考えてみれば、財を継ぐ、店を継ぐ、業を継ぐ、家名を継ぐ、精神を継ぐ、命を継ぐなどを挙げることができますが、あなたにとっての後継とは何なのでしょうか。
ある問答
Y君は美容歴6年、大都市にあるサロンで中堅として活躍していた。地方都市で美容室を経営する母親は、老化や体調不良をY君に訴え、さらにY君の父親たる夫との折り合いが悪くなって孤独をかこっていることを涙ながらに訴えてY君の早期の帰郷をうながした。
Y君は将来大都市で自立し出店する夢をもっていた。そして、Y君には将来を約束した恋人がいた。しかし、母親はY君だけに帰って来てほしいと懇願した。
Y:母に会ってきました。母の憔悴は想像以上で、このまま放っておけない状態でした。帰ろうと思います。
――あなたの夢は諦めるのですか?
Y:自分の夢ばかり追っていてはいけないと思ったのです。
――お母さんの夢に乗り換えるのですね。
Y:……。
――ご両親の関係は?
Y:父は母を顧みず好き勝手をして母を苦しめています。
――だから子であるあなたがお母さんを助けるのですか?
Y:他に誰が母を助けてくれるというのですか!
――お母さんはあなた1人の帰郷を願っているそうですね。
Y:それには応じられないので、彼女ともども帰り結婚します。
――嫁姑のいさかいが起こったらどうしますか?
Y:両者に大人の付き合いをするよう説得します。
――それでも両者の仲が決裂してしまったら?
Y:そのときの状況を見て判断します。
――どちらか1人を選ばなければならなくなったら?
Y:ウーン、そんな難しい質問をしないでくださいよ。
◇ ◇ ◇
この問答、あなたはどう思われましたか?
相談を受けた私は、Y君の帰郷に反対しました。
その理由は以下の4点です。
①Y君が自分の夢を諦めてしまったから。
②母親が息子に甘え、依存していたから。
③両親の不仲のとばっちり(母の孤独)を子に負わせてはならないから。母を支えるのはあくまでも父であるから。
④Y君にとって恋人(妻)と母親のどちらが大切なのかがはっきりしていなかったから。
結局、Y君は帰郷し、結婚して母親の店で働きだしました。しかし、父親は息子が帰ってくるとそれをいいことにますます家庭を顧みなくなり、当然のように嫁姑問題も起こって、Y君は自分の帰郷がけっして良い結果を生まなかったことに今更ながら気づいたのでした。
後悔先に立たず
ことの大小を問わず、私たちの目の前には選択と決断をしなければならないことが日々次々と起こってきます。右に行こうか左に行こうかと決断を迫られるとき、私たちの心には葛藤がおきます。
葛藤は苦しいものですから、できれば避けたい。葛藤を避ければ決断もできません。
私たちが、「あのときああすればよかった」と悔やむのは、あのときキチンと決断をせぬままにいいかげんに選んでしまったからだということができます。
上図のように、ある行動をして悪い結果が出ても、それが決断による行動なのか、決断せぬままの行動なのかによって、心には納得できる「受容」が残るか、納得できない「後悔」が残るかという大きな違いが生じるのです。
決断には勇気がいります。決断とは何かを選び、何かを捨てることであり、その結果がどうなろうと状況のせいや他人のせいにはけっしてできず、自ら受け入れ自ら責任をとらざるを得ないからです。
私たちは、自分の人生の中では誰もが主役であり、脇役であったり見物人(傍観者)であってはなりません。
主役で生きるには、「自分で考え、自分で決断し、自分で行動し、その行動に責任を持つ」という、つまり主体性を持った姿勢が不可欠だといえます。
「決断」という権限の委譲
経営者やリーダーの最大の権限であり最大の責任は「決断」すること。決断が成功を呼べば最高の快感を得ることができますが、反対に失敗を招けば大きな苦悩を背負わねばならなくなります。
未知の世界に向かっての決断ゆえに、どうしても慎重にならざるを得ず、「決断」という権限の委譲を行えない経営者も非常に多い。店長会とか幹部会を設けていながら、そこは何事をも決定できない機関である組織も多い。談話会かよくても提案機関でしかない会に配属された名ばかりのリーダーたちは、経営者から任せてもらえないことを嘆きながら、次第に経営者に対して不信感を募らせていくことになってしまうのです。
会議がお通夜になってしまっている、という経営者の方に申し上げましょう。お通夜にしてしまったのはあなた自身だということ。
何を語っても、何を論じても、最後は経営者の鶴の一声で決まってしまうような会議で、誰が積極的に意見を出すでしょうか。
つまり、幹部の力量を下げているのも経営者自身であるということ。意識の上ではリーダーを育てたいと思いつつも、現実の中では逆に育成を阻止している経営者が多くあることも事実です。
理美容業界での経営形態の多くが機能的な組織運営に限界を生じています。私はその大きな原因として「師弟関係」を挙げたい。
経営者の多くが「先生」と呼ばれるこの業界では、伝統的に先生である「師匠」以外は皆「弟子」として位置付けられています。
基本的には技術の伝授に当たっての師と弟子の関係ですから、技術での後継者たる一番弟子、二番弟子という位置付けは納得がいくのですが、問題は技術の後継者が必ずしも組織運営のリーダーとして機能できるわけではないということです。
また、スタッフ間でも入社順で先輩後輩の序列が決まり、後輩が先輩の上位に立つようなことはまずあり得ないというサロンも多いのです。
そういう「師弟関係」の中で、私がもっとも懸念しているのは「服従」的意識です。師が言うこと為すことは絶対であって逆らえないという暗黙の不文律。しかもそれは技術だけでなく、生きることすべてについてと言ってもよいでしょう。弟子であるスタッフは常に師である経営者の顔色を見ている。組織の基本構造が師と弟子という2階層しかないので、中間にリーダーを置いても機能しにくいのです。
決断のためのバックボーン
師弟関係のすべてが悪いと言っているのではありません。現代の人たちが忘れてしまった師弟愛は、師と名のつく仕事に携わる人々が改めて掘り起こすべき大切なことだと言えるからです。
教師、医師、看護師、そして美容師、理容師、マッサージ師など人間を相手に直接手をかけ目をかける人たちにもっとも大切なことは、人間の尊厳を守ること、人間愛を伝えることだと言えるでしょう。
師は人に大きな影響を与えるゆえに、師と呼ばれる人は特に自分を磨く修練を怠ってはならないと、私は思うのです。
だが、悲しいことに現実の世界では、師という社会的地位にあぐらをかいて周りの人々を支配しようとする人も少なくありません。
この業界は、他の産業に比べてスタッフが職場で過ごす時間が圧倒的に長く、そのぶん人間的なかかわりも密になり、相互に影響しあう度合いも高くなります。
そしてスタッフは師である経営者を見ている。だからこそ、経営者は人間としての自分の生き方に目を向け、それを伝えていくことが大切な仕事になるのだと私は思います。
決別の決断
私たちは、愛する人や子ども、地位や名誉や富などを手に入れると、それを失うことの恐れから、それらに執着し守ろうとします。
執着心が強まると、人であれ、物であれ、金であれ、すべてを自分の所有物化して、それらを支配しようとしてしまいます。
物や金の執着心も人を狂わせますが、こと人に対しての執着は相手も自分もともに人間性を崩壊させてしまうことに私たちは気づかねばなりません。
親が子をペットのように溺愛してしまったり、恋人や夫婦の間では嫉妬や不信で相手を束縛し、あたかも自分の所有物であるかのような扱いをしたりする。そしてそれを「愛」だと言い切る。
これら親子や夫婦の依存関係は、本来別々の人格であるものを一体化させようとすることで、どろどろな人間関係を生み出し、互いを破滅に導くのです。
孤独社会がなせるわざなのか、あるいはあまりにも恵まれすぎた生活環境の中で、何でも簡単に手に入れることができるという風潮のせいなのか、人も物も金もみんな一緒くたになっている。
私たちは、どんなに多くのものを得ても、死とともにすべてを失うのです。自分の死とともにすべてが消えるのです。
死を目指して歩む私たちは、こうして生きている今、自分にとって何が一番大切なのかを見極めなければならない、と私は考えるのです。
何が大切なのかを曖昧にしておけば、私たちはいざというときに必ずうろたえ、自分を見失い、人生を台無しにしてしまう危険にさらされることになってしまうからです。
死はすべてのものとの訣別ですが、私たちは生きている今、相互の人間性を尊重するために、敢えて訣別しなければならないものがあることを知るべきでありましょう。
人間性回復の経営学(全12回)
| 回 | テーマ | サブテーマ |
|---|---|---|
| 1 | 第1回講義 心の枷(かせ)をはずしてみよう | 常識との対決...思い通りの人生を歩むために |
| 2 | 第2回講義 自分は一体何者なんだ | 自分の臭さに気づいていますか |
| 3 | 第3回講義 人間関係の極意教えます | (極意につき極秘) |
| 4 | 第4回講義 人間尊重こそ繁栄の原点 | 手間暇惜しまず "one to one" |
| 5 | 第5回講義 感動と絶望について | 説得では何も変わらない |
| 6 | 第6回講義 不安と孤独について | お触りサロンのお勧め |
| 7 | 第7回講義 犯人は誰だ! | 犯人は◯◯だ! |
| 8 | 第8回講義 停泊中の船舶に告ぐ…直ちに出航せよ | 経営とリーダーシップについて |
| 9 | 第9回講義 決別の決断 | 1本の命綱を誰に投げるのか |
| 10 | 第10回講義 一流の条件 | "らしさ" の追求と発揮 |
| 11 | 第11回講義 文化の発信基地として | これこそサロンの使命だ |
| 12 | 第12回講義 もっと儲けよう、そしてもっと使おう | 愛と奉仕の実践 |