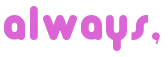一流は幸せの切符?
比較評価の体質を濃厚にもつわが国では、とかく何事にも序列をつけたがる傾向が強いといえます。私たちも幼児の頃から、他より優れているとか劣っているとか比較され評価され続けてきました。
何を基準に決めるのかハッキリしないけれど、どの社会にも一流二流があり、一流と言われる集団に所属すればそれだけで自分も一流の評価を受け、一目置かれる存在になります。
自分の人格や実力が一流だと認められたわけではないのに、一流といわれる集団に所属する人の多くが自分自身をも一流だと思い込んでしまい、二流三流に位置づけされる集団とそこに属する人たちに対して優越感をもってしまうのです。
たとえ、他に対して優位を保つことがこの社会を生き抜くために必要なことだとしても、一流ブランドの服に身を包んでいるから中身も一流だというような錯覚は、独自で個別の存在としての人間を無視し、真の人間関係を破壊するものだと言わざるをえません。
しかし、残念ながらそういう社会の風潮を無批判に受け入れ、長いものには巻かれろとばかりに「一流どころ」を目指す人も多いのです。
一流の集団に所属することが幸せの切符を手にすることだと思っている人が多くいる以上、学歴社会や学閥は消えることはないでしょう。
美人と言われる人がそれだけで得をするように、「一流どころ」に所属した人はそれだけで得をすることが多いと思うからなのでしょう。
経済的バブルは崩壊しましたが、権威的、精神的バブルはまだ壊れてはいません。権威崇拝の意識は依然として強く残っているのです。
一番は一流か?
この錯覚、この妄想、何とかしなければ社会の狂いは直せません!
地域一、日本一、世界一というように「一番」を目指す人は多い。
一番になればいろいろなものが寄ってきます。金も権威も名誉もついてくるし、その利得は通常、二番以下を遥かに引き離すものです。
一番を目指すのは結構。しかし、どのような一番になりたいのか、何のために一番を目指すのか、そこが漠然としてはいないでしょうか。
個人的利得のためだけに、あるいは自分の満足だけのために一番を目指すなら、それは大変貧しい発想だと言わざるを得ません。
一番は人々の注目を浴びます。一番は社会が認めた地位ゆえに、一番は社会の期待に応えなければならないのです。
一番の影響力は強大です。一番になったとき、あなたはその力をもって何をしようとしているのでしょうか。あなたはその力で社会に何を訴え、何をどうしたいと思っているのでしょうか。
一番には一番の使命があるのです。一番ゆえにやらねばならないことがあるのです。それを顧みず、私利私欲に走ったなら、社会から厳しい制裁を受けることになるでしょう。
しかし、一番が一番の使命を果たしたときに、初めて「一流」という称号を与えられるのです。
毎年随所で開かれる技術コンテストで生まれるチャンピオンのように、私たちのこの業界には一番は腐るほどいます。しかし、一流となるとどれほどいるのでしょうか。指折り数えていると、何やら淋しくなってしまいます。
立ち遅れを回復しよう
また、企業として一流を目指すのならば、越えなければならないハードルがあります。これまで、業界の特殊性とか何とかという理由をつけて、その改善改革にまともに目を向けず放置してきた問題のことです。
たとえ一流ブランドで身を包んでも、垢だらけの体でいたのでは遠目にはいくらカッコ良くても、近づけば臭くてたまらない。こびりついた垢を落とさなければ、本当の一流になどなれるはずがありません。今あなたが垢取りをやらずして、いつ誰がやるというのでしょうか。
昔は技術能力さえあれば良しとされ、その後、対人関係(接客)能力が必要とされて今日に至りました。しかし今後は人間的視点に立った組織もしくはチームの管理運営能力が要求されることでしょう。
この業界が長年抱えてきた問題点の一部を挙げてみましょう。
労働条件・待遇
- 勤務時間……今や週40時間勤務の時代ですよ。いかに同好の士と言えども、趣味の団体ではなくプロの集団。特殊な業界だからだの、時間で仕事をしているんじゃないだの、それらは大勢から見ればただの言い訳。練習やミーティングなどで1日の在社時間が12時間を超えるサロンも少なくありません。「自分の時間がない」と訴える若者に「甘い」とか「十年早い」とか、まだ言いますか?
- 有給休暇……あってなきがごとし。せいぜい病欠の穴埋め。土日の結婚式には出られないし、旅行もできない。つまり、自由に使えない。繰り越しても使い切れない。
- 給料、賞与、退職金……給料はともかく、賞与と退職金の支給レベルはあまりにも低い。それらを加味した利益計画が立てられていない。今や年収から生涯賃金を考慮すべき時代なのに。
- 保険制度……社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)・傷害保険・所得保障保険などに対する意識も低いと言わざるを得ません。スタッフの福利厚生について真摯に取り組む必要があります。
機能的・組織的運営
- 権限と責任……いくら階層をつくっても、権限と責任の範囲の明確化とその委譲がなされないなら組織になりません。役職は名ばかりになり、リーダーシップは育たずチーム力も向上しません。
- オーケストラ的機能集団……違った得意技をもった異質な人が集まり、相互に補完・援助をするのが機能的集団。技術は一通り何でもできるという同質の技術者の集団では単調な味しか出すことはできませんし、プロとしての個性は発揮しにくいでしょう。
間接部門(人事・労務管理、決算・財務管理、仕入・在庫管理、営業・企画開発・教育などの非生産部門)の設定立ち遅れ、もしくは不備も機能的・組織的運営の大きなネックになっています。
営業・教育意識
仕事の性質上、個人の技術習得に教育が偏重し、全社的思考が育ちません。これはある意味、徒弟制度の名残りともいえます。ほとんどのサロンが、「教育=技術」という認識なので、営業教育や管理者教育、自己啓発学習などには目が向いていません。根本的には、それらはオーナーの経営哲学の脆弱さに由来するものと思われます。
社会的使命
前世紀に企業が犯した大きな罪の1つに「社会的使命」を忘れたことが挙げられるでしょう。
企業は獲得した利益に応じた納税により社会的使命の最低限は果たすことができますが、これは憲法で定められた義務の遂行です。今私たちが論ずべきことは、社会とのかかわりの中で仕事を通して義務ではないが貢献がいかにできるかということです。
企業単体で成し得ないならば、他企業または他産業との協働によって新たな価値創造、新たな文化創造を推進すべきでしょう。
優れていて独特なもの
ところで、何をもって一流と言うのでしょうか。
ここで一流とは「他の追従を許さないほど優れたものであると同時に、他と比較することのできない独特のもの」をいいます。
一流になる可能性は誰にでもあります。だが、願望があっても、自分が本当に一流になれると信じている人は少ない。
たとえば、自分の来月の売上げ目標を200万円に設定したとしても、心の奥底では「でも無理だな」と思ってしまったのならば、その時点ですでに目標を実現不可能なものとして諦めてしまっているのであって、目標は目標でなくなり、絵に描いた餅でしかなくなっています。
『心底願うことは実現の可能性があるが、願わないことはけっして実現はしない』これは単純明快な原理なのです。
できると思ったことはできますが、できないと思ったことはできません。
私たちはもっともっと自分自身を、そして自分の可能性を信じなければならない、と私は強く思うのです。
「自分はできるんだ」と自分が意識しないで、誰があなたをできる人間だと思ってくれるでしょうか。
何かをやろうとするとき、その行動に移る前に、自分には無理だとか、自分にはできないと意気阻喪して自分を諦めてしまったり、捨ててしまったりしてはいないでしょうか。
それを自信がないからだとか、過去がダメだったからだとかいうならば、これからどうやって自信をもち、それを深めていくのですか?
何歳になろうが、過去をどのように過ごしてこようが、体裁にとらわれず「よし、今からがスタートだ!」と思い切る勇気さえあれば、きっとあなたは自分の思い描く夢を実現させていくことができるのです。
私たちは命ある限り、わが身に備わっている「優れていて独特なもの」を自らの手で発揮しなければなりません。必ずそれはありますから。
自らの発掘作業を止めてしまったとき、あなたは自分を見出すことも、自分を磨くことも放棄してしまうのであり、そういう人に私は遠慮なく「ナマケモノ!」と言ってあげたいと思うのです。
さて、プロとして、当初から二流を目指す人はいないことでしょう。誰だってなれるものなら万人から認められる正真正銘の一流になりたいと思いますよね。
一流の条件
しかし、一流にまで行き着く人(集団)は極々少ないのです。また、たとえ一流になってもその多くは没落してしまい、永くはその位置に留まることができません。
なぜかといえば、一流になった者が社会に対してなすべき使命を忘れ、そこで自己満足に浸りきってしまったり、あるいは自己の利得のためだけに働いてしまうからです。
大きな錯覚は、自分1人の力でここまでやってきたと思ってしまうこと。自分の能力が今の地位や名誉や金を呼び寄せたのだと思ってしまうこと。だから、一流の栄誉を自分1人だけのものにしたいという欲に駆られ、その栄誉に有頂天になり慢心してしまうのです。
一流を目指し、あるいは一流を維持しようとする人にもっとも大切な心の姿勢は「謙虚」であること。
常に自分のあり方に厳しく目を向け、自分をここまで引き立ててくれた多くの陰の応援者に心からの感謝の念を持ち続けることが、一流の条件の1つであると言えましょう。
一流はバランスではなくハーモニーだ
あなたはバランスのとれた人間になりたいと思っておられますか。それは社会人として必要なのかもしれません。だが、私は思うのです。だから個性的な人間が育たないのだと。元来人間はバランスがとれないもの。行動的な人と思考的な人を足して2で割るわけにはいかないのに、それを修正し平均化しようとするのがバランス思考。
欠けているものを補おうとする考えが優先する限り、好きなことや得意なことを伸ばそうとする発想は普及しません。同質の人間の集団は安全かもしれませんが、同質ゆえに反発し、優劣を競い、したがってチームワークはとりにくいのです。
これに対して、ハーモニー(調和)とは、相反する性質や機能をもった異質のものが不離一体となって、相互に補完し合い、反応し合って、新しいものをつくりだして、秩序とバランスを保つ状態をいいます。
「優れていて独特なもの」はここで生かされ、互いを不可欠な存在として遇するゆえに、自然な形でチームワークがとれるのです。
つまり、自己の内で完結を目指すバランス思考から視点を変えて、独自な者同士が援助・補完をし合うハーモニー思考への転換を、私はあなたにお勧めしたいのです。
たとえば、メロディーと伴奏を1人で完結してしまうピアノ的人間を10人集めて育成してきたのが今までの理美容業界だとすれば、今後は金管・木管・打楽器のように異質のものを10人集めて1つの音づくりに挑戦していく考え方が「一流」を目指すために必要になると思うからです。
一流は文化だ
一流といわれるものに接すると、そこには美しさがあり、香りがあり、快い波動があります。一流は感動を呼び起こすものだからです。
一流には芸術性があり、創造性があり、そしてそこに人間性が備わって、顧客の求める満足をはるかに超えるものを与えるのです。
一流は顧客の要望に応えるために何かをするのではなく、常に自己の独自性を追求し、ベストを尽くすことに集中し、その結果として顧客の満足が生じるのだということができるでしょう。
この「文化」については次号でも詳しく言及したいと思います。
一流には高い志操がある
イギリスのケンブリッジ大学入学試験を扱ったTVドキュメントがありました。
地方の高校で最優秀の成績を修めた生徒が、同大学を受験し、まずは筆記試験に合格し、いよいよ最終の教授による面接試験に臨んだのです。面接はスムーズに進行し、その大詰めを迎えたとき、教授の1人が問いかけました。
「君の筆記試験はすべての科目で高得点をあげていてまったく申し分ない。大学は君を歓迎したいと考えているのだが、ひとつ聞いておきたいことがある。君は大学で数学を専攻したいということだが、数学を学んで卒業した後、君は社会に出てそれをどう役立てようと考えているのだろうか。」
彼はその質問に当惑し、満足に答えることができませんでした。
面接終了後、直ちに教授たちは彼の合否について論じ合いました。彼の高い知能と可能性を生かしたいという意見が出て、そこに異論をとなる教授はいませんでした。しかし、合否の決め手になったのは次のような意見でした。
「ケンブリッジ大学では、社会に役立つ人材を送り出すことを使命としている。いかに学力が優れていても、社会への役立ちを意識していない者には当大学に在籍してもらうわけにはいかない。」
結果を待ちわびる彼に届いたのは、不合格の通知でした。
そのシーンを見ていた私は、一流の一流たる所以を思い知らされ、その志操の高さに感動を覚えたのでした。
一流は哲学だ
理容師のA氏は33歳。小さな町でスタッフのN君と2人で予約制の店をやっている。毎日の開店は午前9時半だが、閉店時間は特に決めていない。予約客が終了したときが閉店なのだ。予約が切れればお昼ごろに閉店することもあるし、予約が混めば夜中の2時3時までやることも珍しくはない。A氏は人間としてのかかわりを大切にする。
A氏の生き方は単純明快で、ストレートにものを言うから、彼の元には子育てに行き詰った親が相談に来る。職場での人間関係に悩む若者が助言を求めて来る。会社の経営者や重役が苦境打開の相談にやって来る。小学生の鍵っ子が毎日下校途中に寄っていく。などなど、とにかく人生の相談所のような理容室なのである。
夜中に予約を入れてくる顧客は、A氏にゆっくり相談をもちかけたい経営者や若者が多い。
A氏は相談を受けたくてやっているのではない。人間が生きにくいこの社会で、心を見失い苦悩する人があまりにも多いことに愕然としているのだ。世間体や見栄や欲が人の心を蝕んでいる現実を知り、また孤独と不安に打ちのめされている人に多く接して、彼はいたたまれず訴える。もっと軽やかに、もっと楽しく生きていきましょう、と。
だから彼はときを忘れて語り合う。夜が明けてしまうこともある。
A氏の独特な生き方は誰にも真似ができない。私はそんな彼を見ていて一流の人間だと心から思う。
一流の根源にはその人の哲学があります。
自分が本当にやりたいことを、ひたすらやっていく。
自分を見つめ、自分にしかできないことを見出してやっていく。
それを持続したときに、やってきたことは洗練され、格調の高いものになっていくはずです。
らしさの追及と発揮
要は、「自分らしさとは何か」をとことん追求し自覚することが、一流への必須条件だということです。
自分らしさとは、自分にしかない魅力です。それを1つでも見出したなら、周りからバカと言われようが、何と言われようが、それを自分の生きていく核として思う存分発揮してみようではありませんか。
人間性回復の経営学(全12回)
| 回 | テーマ | サブテーマ |
|---|---|---|
| 1 | 第1回講義 心の枷(かせ)をはずしてみよう | 常識との対決...思い通りの人生を歩むために |
| 2 | 第2回講義 自分は一体何者なんだ | 自分の臭さに気づいていますか |
| 3 | 第3回講義 人間関係の極意教えます | (極意につき極秘) |
| 4 | 第4回講義 人間尊重こそ繁栄の原点 | 手間暇惜しまず "one to one" |
| 5 | 第5回講義 感動と絶望について | 説得では何も変わらない |
| 6 | 第6回講義 不安と孤独について | お触りサロンのお勧め |
| 7 | 第7回講義 犯人は誰だ! | 犯人は◯◯だ! |
| 8 | 第8回講義 停泊中の船舶に告ぐ…直ちに出航せよ | 経営とリーダーシップについて |
| 9 | 第9回講義 決別の決断 | 1本の命綱を誰に投げるのか |
| 10 | 第10回講義 一流の条件 | "らしさ" の追求と発揮 |
| 11 | 第11回講義 文化の発信基地として | これこそサロンの使命だ |
| 12 | 第12回講義 もっと儲けよう、そしてもっと使おう | 愛と奉仕の実践 |