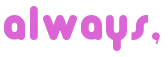事実をどう認識するか
日本のある製靴会社が2名の市場調査員をアフリカのある地域に派遣した。間もなくA調査員からの報告があった。「ここでは誰も靴を履いていません。だから販売の見込みは全くありません」。次いでB調査員からの報告。「ここでは誰も靴を履いていません。だから販売の見込みは無限大にあります」。
裸足で歩く人たちを見て、Aさんはお先真っ暗を感じて落胆し、Bさんは青天井の可能性を感じて喜んだのでした。
長期構造不況といわれる今日、その「不況」というものをどう認識するかで先は大きく変わっていくものと思われます。
不況を否定的にみる人は、過去の好況時の業績を基準にするため、現在を苦境と感じ、我慢して耐えるか、あるいは何とか現状を打開しようと策を練ります。
一方、不況を肯定的にみる人は、過去は過去として現在との比較基準にせず、現状を謙虚に受け止め、策に走らず、経営に対する意識の転換を計ろうとするのです。
前者は経営のコンセプトは変えずに方法による改善を目指すことになり、後者はコンセプトそのものを見直すことになります。
ただ、言えることは、不況による業績低下を悲観的に見ている限りは、何をしようと結果も悲観的にならざるをえないということです。
私がここでみなさんに申し上げたいのは、こと理美容業界において、多くのサロンは不況打開の策をいかに打ち出そうが、これといった決め手を見出せないできたのではないか、ということです。
もちろん、策を練ることを否定しているのでもないし、策の効果がないと言っているのではありません。しかもしれらが顧客の要望に応えて生まれた策であればなおさらのことです。
見える世界から見えない世界へ
だが、現実はなかなか期待通りにはいきません。なぜなら、それらの策は顧客の「顕在化した要望」に応えてはいるものの、顧客の心の奥深くにある「潜在的な要望」には応えていないからだと、私は思うのです。
歴史を顧みるに、この業界はまず「伸びた髪を結ったり切ったりする」職人の技で顧客に応え、次いで「ファッションとしての髪を創造する」デザイナーの出現によって基本的に顧客の要望を満たしてきました。しかし、先年のカリスマブームを頂点として以後は顧客にアピールする決め手を欠いたまま今日を迎えているというのが実情ではないでしょうか。
私たちは今、顧客の潜在化した要望を掘り起こし、新たな視点に立って経営のコンセプトを見直すべき時期を迎えているように思います。
顧客の真の要望を探るために、見える世界から見えない世界へ目を向けてみようではありませんか。
時間について
サービス業に位置する理美容業の根本的特徴は「顧客を長時間拘束する」ことです。
顧客はサロンでの滞在時間を自分で決めることができません。
それゆえ「自分の貴重な時間を預けるに足りる理美容室(もしくは技術者)かどうか」が顧客の心理を動かす大きな要因になっていることを改めて認識していただきたいのです。
いかに優れた技術を持ってしても、顧客にとってカットやパーマ、カラーの施術時間は身動きできない苦痛の時間であることには変わりありません。この苦痛の時間を緩和できるのは技術者の人間性であり、それ以外の何者でもないことに異論はないことと思います。
優秀な技術を持ちながらも顧客の支持を得られず、やむなくこの業から身を引いた技術者を何人も見てきた私は、もちろん本人の人間性や対人関係能力の不足や欠如はあるにせよ、それを知りながらも人間性向上の教育には目も向けず、ただ技術習得一辺倒の教育で善しとする経営者の姿勢に疑問の目を向けざるを得ないこともしばしばありました。
人間性について
技術第一主義も結構、業績第一主義も結構。だが、技術をするのも人間、業績を上げるのも人間、顧客もまた人間なのです。
この業が人間関係業だと言われているにもかかわらず、どうしてこうまで人間第一主義をとる経営者が少ないのでしょうか。
こと理美容業においては、プロとして最も大切な資質は、今や技術能力ではなくて「人間性」なのだ、ということを私は断言したい。
たとえば医の世界をみれば、医師も看護師もそれぞれの能力をもって患者を看ているのですが、患者である私たちは治療を通して彼らの能力よりも実は人間性を見ているのだということ。入院という長期滞在を経験した方ならそこはよくおわかりのことでしょう。
医も仁術ならば、理美容もまさに仁術であるといえます。
滞在時間が長くなればなるほど、受け容れ側の私たちは顧客からシッカリと人間性を見られているのであり、サロン盛衰の鍵はまさにそこにあるのだ、と言っても過言ではないでしょう。
プロ志向について
さて、私たちプロは顧客に対してどのような姿勢をもって対応しているのか、改めて考えてみたいと思います。
①対応型
- 顧客の好みやセンスを把握して、その要望に応えることを第一とする。
- 顧客の要求レベルが低いときや、要求レベルを超えた技術力・応対力を持ったときに、技術者は夢や目標を失い、マンネリに陥って独創性と新鮮さを失う。
- 熟練工的「職人」の域を脱しえない。
②調和型
- 自分の芸術性・創造性・人間性を磨いて、顧客の要望に応えようとする生き方。技術は顧客と自分の架け橋となる。
- 自分の芸術性・創造性・人間性が顧客のそれを超えたとき、顧客にとってカリスマ的存在となる。
- サロンに文化が発生する。
- 高い志向が顧客の要望を無視して独善的になる危険もある。
あなたは、上記①対応型②調和型のいずれでしょうか。
過去、多くのサロンが目指してきた①顧客ニーズ対応型サロンは、受信型サロンであり、顧客の要望がますます個別化し多様化していくであろう今後を想定したとき、その対応力に限界が生じて徐々にサロンの力は衰退していくものと思われます。
一方、②プロの文化発信サロンは、自分の生き方や自分の持ち味がにじみ出ることにより、顧客の共感や感動を呼び起こし、サロンは発展の道をたどっていくことでありましょう。
意識と無意識について
人間は考える葦であると言われるように、きっとあなたも多くを考え、多くを意識しながら日々を過ごしておられるにちがいありません。
しかし、私たち人間が意識して行動しているのは実はほんの数%であって、そのほとんどは無意識の行動なのだそうです。
つまり、自分が知っている自分はやはりほんのわずかであって、他人は私たちが自分で気づいていない自分の多くを見ているのだと言うことができます。
自分の持つ雰囲気、自分の香り、自分の色、自分の味など、自分ではわかりません。だからそれらが他人に対してどのような影響をおよぼしているかはさらにわからないのです。
では、その自分の香りや色や味はどこから出てくるのでしょうか。
それは、私たちが文化(カルチャー)に出会い、文化に触れること。
文化に触れて、衝撃や感動を味わうごとに、私たちの内側の何かが変わっていきます。その変化を自身で感じることはなくとも、気づかぬうちに自分は変わっていくのです。
そして、自分の香りや色や味が洗練され、心地よい風を送りだすようになっていく。つまり、品位、品格が高まっていくのです。
孤独社会に訴える
ひきこもり、不登校など、青少年が自ら社会とのかかわりを絶って孤独な世界に入りこんでいく。青少年に限らず、今や年齢を問わず人間関係に不安と怯えを強く感じながら生きている人が顕著に多くなってきたように感じるのは私だけなのでしょうか。
それは甘えだ、逃げだと評論するのは簡単です。評論で事態が改善されるなら何の世話もいりませんが、評論によってさらに傷つく人が増えることを私たちは肝に銘じておくべきでしょう。
理論や理屈をいくら言ったところで、傷ついた心はけっして癒されはしないのです。
今、私たちはこの孤独社会において何かできることがあるならば、対岸の火事を見物しているような姿勢を捨てて、職業生活の中であろうが、私生活の中であろうが、何かを行動に移してみるべきではないでしょうか。
もう言葉はいらない! 言葉だけではあまりに冷たすぎる!
公認の触り屋
『触ってもらうことに飢えているアメリカ人は、公認の触り屋の世話になる。理髪師、ヘアドレッサー、マニキュア師、マッサージ師は、人々が望む身体接触を提供することで、その人々がアメリカ社会でのストレスを克服してゆく手助けをしているのである。また病院では毎晩のように入院患者の「背中さすり」を行うが、これに床ずれ予防以上の治療効果があることが認められてすでに久しい。指圧師や足専門の治療師がもたらす慰安も、もし機械がやるのだったら、それほど大きくはならないだろう』
(マジョリー・ヴァーガス著「非言語コミュニケーション」新潮選書より)
この本は15年前の1987年に刊行されました。
理美容業が、表舞台では髪を中心とした美の演出を行いながら、同時に顧客の心を癒す重要な役割を果たしていることが明記されています。それも身体接触によって。
乳児、幼児の時期にはだっこやおんぶなどの身体接触によるコミュニケーションは誰にでも許されるのですが、大人になるとそれは社会的に容認されなくなってしまいます。
では、大人にはそれが不要なのかといえば、そうでないことをみなさん自身がよくおわかりのはずです。
ストレスがますます強くはびこるこの人間社会にあって、私たちが顧客に対してできる大切な行為の1つがこの「身体接触」であることに異論ある方はおられないことと思います。
身体接触の不足から
一昔前のことですが、アメリカでは凶悪・残酷な事件が多発し、青少年の情緒が非常に不安定であるのに比べ、日本ではそのような事件は少なく、また青少年の情緒安定度が高いのはなぜかということを研究したアメリカの心理学者がいました。
そして原因は、乳幼児期の親子関係であることが判明したのです。日本では母親が母乳を飲ませ、おんぶ、だっこ、添い寝をしているのに比べ、アメリカではベビーシッターが哺乳瓶で授乳し、乳幼児はベッドで単独で育てられる。要は、乳幼児期に親との身体接触に恵まれなかった子どもは、言語障害、学習障害、アレルギーなどになることが多く、また抑うつ、自閉、凶暴性、攻撃性などを含む数多くの情緒障害になるということが判明したのです。
昨今の日本では、ご存知の通り、過去起こり得なかったような凶悪・残虐な事件が多発しています。
幼児虐待などその顕著な例で、どうしてここまで親が親らしくなくなってしまったのかを考えざるを得ません。
言うまでもなく、子を持った親自身が幼児期に身体接触に恵まれなかったことも大きな要因であることは間違いないことでしょう。
ひきこもりや不登校の子を持つ親自身も同様の原因を持っていると考えられます。
ふれあいの文化を
いずれの職業も、それだけやっていれば良い時代ではなくなりました。
世の中がこれだけ大きく狂い、人間が人間らしく生きることが至難の技になってしまった今日、仕事は自分のためだけにするのではなく、人間社会を回復するために何らかの協力をする必要がでてきたのです。
これから社会を担っていく子どもたちが、生き生きと生きていける社会づくりに、そして高齢化するこの社会で老人たちが生き生きと希望を持って生きていける社会づくりに、少しでも貢献できる私たちになっていこうではありませんか。
見えないところに真実がある
見える世界だけを見ていると、大切なものを見失ってしまいます。
いつの世も、本当のものは見えない世界にあるのです。
見えないところに真実があり、幸せの鍵があるのだと、私は思っているのです。
そして、そのことを教えてくれた詩が金子みすゞさんの「星とたんぽぽ」です。皆様はこの詩を読んで何を思いますか。
星とたんぽぽ
金子みすゞ青いお空のそこふかく、
海の小石のそのように、
夜がくるまでしずんでる、
昼のお星はめにみえぬ、
見えぬけれどもあるんだよ、
見えぬものでもあるんだよ。ちってすがれたたんぽぽの、
かわらのすきに、だァまって、
春のくるまでかくれてる、
つよいその根はめにみえぬ
見えぬけれどもあるんだよ、
見えぬものでもあるんだよ。
人間性回復の経営学(全12回)
| 回 | テーマ | サブテーマ |
|---|---|---|
| 1 | 第1回講義 心の枷(かせ)をはずしてみよう | 常識との対決...思い通りの人生を歩むために |
| 2 | 第2回講義 自分は一体何者なんだ | 自分の臭さに気づいていますか |
| 3 | 第3回講義 人間関係の極意教えます | (極意につき極秘) |
| 4 | 第4回講義 人間尊重こそ繁栄の原点 | 手間暇惜しまず "one to one" |
| 5 | 第5回講義 感動と絶望について | 説得では何も変わらない |
| 6 | 第6回講義 不安と孤独について | お触りサロンのお勧め |
| 7 | 第7回講義 犯人は誰だ! | 犯人は◯◯だ! |
| 8 | 第8回講義 停泊中の船舶に告ぐ…直ちに出航せよ | 経営とリーダーシップについて |
| 9 | 第9回講義 決別の決断 | 1本の命綱を誰に投げるのか |
| 10 | 第10回講義 一流の条件 | "らしさ" の追求と発揮 |
| 11 | 第11回講義 文化の発信基地として | これこそサロンの使命だ |
| 12 | 第12回講義 もっと儲けよう、そしてもっと使おう | 愛と奉仕の実践 |