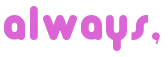何のため、誰のため
これからは、個人はもとより、特に企業は「この世の中をよくしていこう」という意識をもって活動を行い、社会に積極的に貢献していかなければ、自らの存立基盤を失ってしまうことになるでしょう。若者たちの中に大企業を見限り、あるいは既存の企業に期待することをやめる風潮が生まれています。
若者たちは求めているのです。真にやりがいのある仕事を。
夢をなくし意気消沈したまま、社会の枠やしきたりに束縛されていた若者が、無用な常識だの慣習だのといった呪縛を解き放ち、今立ち上がろうとしています。そして、世に向けて彼らの煮えたぎるマグマを噴出させようとしているのです。
彼らは叫びます。「一体何のため、誰のための学校なんだ。そして、一体何のため、誰のために企業は存在しているのか!?」と。
にもかかわらず、巷では相も変わらずこんな問題ばかり。
オトナ…「高校くらい出ておかなければ」
コドモ…「なぜ?」
オトナ…「良いところ(会社)に行けないから」
コドモ…「良いところに行くために高校に行くの?」
オトナ…「この社会、中卒なんかだと馬鹿にされて惨めになるから」
このオトナがもうすでに社会的風潮に毒され、自ら中卒を馬鹿にしている……。中学も高校も予備校化して久しくなりました。
学校は勉学の意義を生徒に伝えることができず、進学を目指さない子は宙に浮き、また進学を目指す子もその多くは終着駅(?)の大学や専門学校で腑抜けのようになってしまっている。
誰がやるのか
この現実を誰が打ち破っていくのでしょうか。社会が悪いとか、教育体制が悪いとか、いくら批判しようが事態が改善されないことは、みなさんが一番よくご存知のはず。
そうです。私たち1人ひとりがやっていくしかないのです。教育の専門家が体制にはまり込んで、為すべきことを為さないのであれば、たとえ稚拙であろうと私たちが伝えていくしかないではありませんか。自分1人では何もできないなんて諦めてはいけません。私たちは今まであまりにも体制に依存しすぎていたのではないか。そして、1人間として為すべきことを、怠けて放り投げていたのではないか。
人間をやっていくのにプロもアマもありません。
そして、真の教育はあくまでも1人の人間から1人の人間へ伝えること、つまり「人格から人格への伝承」であることを、私たちは改めて見直さなければならないときを迎えている、と私は思うのです。
……『コラ!テツヤ、何ばあんたしようとかいな。早う大学ば行ってこんね、あんた。大学へ行ってあんた、学問ばしてこんね、あんた。毎日テレーとしてから。……』(中略)
『行ってこい、どこでも行ってきなさい。母ちゃん、お前のごたぁ息子がおらんごとなっても、何もさびしうなか。が、いうとくがなあ、なまじ腰ばおろして休もうなんて思うたらつまらんど。死ぬ気で働いてみろ、テツヤ。人間働いて、働いて、働き抜いて、もう遊びたいとか、休みたいとか思うたら、一度でも思うたら、はよ死ね。それが人間ぞ。それが男ぞ。おまえも故郷を捨てて都へ出てゆく限りは、帰ってくるときは輝く日本の星となって帰ってこい。行ってこい。行ってこい。』(後略)
母に捧げるバラード(詞 武田 鉄矢)より
親子関係のゆがみ
最近、私は不登校や引きこもりの子たちに接する機会が多くなりました。また、表面はにこやかに明るく振る舞ってはいても、内面に極度に鬱積し不安定で、自失状態になると自損行為に走る子にも会いました。人を信じることができないという子にもたくさん会いました。それから、対人恐怖症とか自閉症とかうつ病とか強迫神経症といった病名をつけられた人たちにも多く会いました。
社会を正常だとみなせば彼らは異常であり、彼らが正常だとすれば社会は狂っている。いずれにせよ、彼らが現実の社会に対応できていないことは事実です。
彼らとの対話、そして親との対話から、私は彼らが社会に対応できなくなった原因の多くは「親の子に対する姿勢」であることを実感せざるをえませんでした。
その親たちは例外なく、いかに我が子を愛しているかを訴えてきましたが、私に言わせれば、これまた例外なく子を人格ある1人の人間としてみることができない親ばかりだったのです。
子を子としかみることができず、だから、親の思い通りに育てようとして子を支配したり、干渉したり、あるいは保護しすぎたり、甘やかしたり、挙げ句の果てには子にへつらい機嫌までとってしまう。
そして思い通りにならなくなると、子に対してまったく無関心になってしまったり、否定し拒絶してしまう。
結局のところ、親が自分の孤独を癒すために子を慰み物にしてしまっているのですが、もちろんその自覚症状は親にはありません。
このような親の態度で、彼らは人間として生きようとする「主体性」を根本から踏みにじられてしまっていたのです。
一生懸命やらないこと、頑張らないこと
主体性を踏みにじられた彼らは、自分の人間としての存在を認めることができず、したがって自分に自信をもつことができません。
彼らは常に孤独と不安の中を生きているのです。
彼らが根本的に辛いのは、「愛されている」という体験をもっていないこと。
つまり「人間として生きている」という感覚をもっていないでいるのです。
だが、それを対岸の火事として見物していてはいけない。あなたの足元にだって火種があって、自分が気づかないうちに、もうすでにくすぶり出しているかもしれないのですから。
あなたが、仕事や生きることに対して、一生懸命やらなければ、頑張ってやらなければという意識の強い人なら、特にそれらを生活信条にしている人なら、私は申し上げたい。
「一生懸命やることも、頑張ることもおやめなさい」と。
もちろん、このことは仕事や生きることをいいかげんにしてよいと言っているのではなく、一生懸命とか頑張るという意識自体を捨てなさい、と言いたいのです。
心に傷を負い社会対応のできない子たちの親は、一生懸命頑張ってきた人たちばかりでした。その典型を2つに分ければ、一方は体を張り汗を流し、逆境を撥ね退け、歯を食いしばって生きて社会的地位を築いてきた親、もう一方はエリートコースを走り頭脳を駆使して社会的地位の高い仕事についた親。いずれの親も自分の体験を「生きるための信条」として、人はこうあるべき、仕事はこうあるべきといった「あるべき論」を強くもっていることを、私は感じずにはいられなかったのです。
一生懸命努力して社会的評価を得た親は、それができない我が子に強い不満をもって、つい口うるさく説教をしたり指示命令をしてしまい、子の人格を無視するようになって、子が自ら生きようとする力を奪ってしまいがちです。
一方、子は体験豊富な親の生きる姿勢や信念に対抗できず、何をやっても親にかなうわけもなく、ただ親への強い劣等感と内向する反発心を抱えたまま、徐々に自己否定への道をたどるしかなくなってしまうのです。子に一生懸命頑張ることを教えてもいい。だが、それは子が一生懸命になれるもの、頑張れるものをもっている場合にのみ有効なのであって、そうでない場合は子をつぶしてしまう圧力になるということをまず親自身が知っておかねばなりません。
資本主義から人間主義へ
家庭での親子関係と経営におけるトップとスタッフとの関係は何ら変わるところはない、と私は考えております。
育てようとして、親は子をつぶし、トップはスタッフをつぶしてしまう。だが、親もトップも自分がつぶしているとは思っていない。本音のところでは自分が正しいと思っているから、公の場では「自分の責任」だと言いながら、子に謝る親も、スタッフに謝るトップもいないのです。なぜこんなに歪んだ世界になってしまったのでしょうか。それはまだあのバウル好況期を夢見ているから、と言ったらあまりにも飛躍しすぎているでしょうか。
あの享楽の時代、環境は破壊され、人間は心を失い、物と金と権力が幅をきかせていました。そして、過去経験したことのない長期の不況がやってきました。倒産やリストラの不安、財産目減りの不安の中で、多くの人は金や地位にしがみつき、ますます人としての心を失ってしまったといえるでしょう。そして先が見えない不安や焦りで苛立った親やトップがそれを弱者にぶつけて自らを癒そうとする、何とも悲しい事態が頻発しているように思えてなりません。
私たちは今、人間としての正念場に立っています。もう自分の利得だけを考えるのではなく、自然界の一員としての人間であることを深く認識し、環境を回復し、助け合いの精神を深め、贈られた命を慈しむ私たちに戻らなければならないのです。
そして、砂漠のように乾いてしまった人間の心に潤いをもたらす文化を生み出し、人間性を回復していかなければならないのです。
言ってみればそれは、資本主義から人間主義に変えていくことなのではないかと、私は強く思っているのです。
人間としての仕事
この不況は、人間が人間を忘れたことへの天罰とも言えるし、また人間が自然界の一員として復帰するための天恵だと言うこともできるでしょう。
経済的にも社会的にも混迷の続く現在、ようやくではありますが、政府の教育指針に「知・徳・体」の教育の必要性が謳われ、人間性を高め、「公」に寄与する人間を育てようとする動きもでてきました。
もう「自分さえ良ければ……」という考えは通用しないのです。自分の周りの人たち、そしてこの社会に生きる人たちが幸せになるために、自分は一体どのような役に立てるのかを真剣に考え、行動を起こしていかなければならなくなったのです。
言いかえれば、私たちには「プロとしての仕事」に加え、もうひとつ「人間としての仕事」をやっていく時代が来たということです。
プロとしての仕事は「役割としての自分」がやっていくのであり、もちろんこれで社会に貢献することができるのですが、これは代理可能な仕事であって、自分以外の人でもやっていけます。
しかし、もう1つの人間としての仕事は、この世で唯一無二の「存在としての自分」が自分にしかできないことをやっていくのです。これは代理のきかない独自な自分の仕事だということができるでしょう。
根本は能力ではなく人間性だ
6年ほど前の話ですが、東京から北約300kmにあるN市に3店を構えるサロンAを訪れたことがあります。スタッフ30数名、年商3億円。特に成人式には1千万円超(客単価7〜8万円)という常識を超えた売上げをあげているということを聞いての訪問でした。
まず、市の目抜き通りにある本店を訪ねました。そして、ドアを開けてから1分もしないうちに私は大きなショックに見舞われていたのです。ショックは少し時間をおいて打ち寄せる波のような感動に変わっていきました。
何がそんなに大きな感動を生み出したのかと言えば、それは店内にいる人たちの1人ひとりのあたたかな笑顔と挨拶だったのです。私が止めを刺されたのは、スタッフの方のみならず、何とお客様からも同じように歓迎の笑顔と会釈や挨拶をいただいたことでした。
待合いに座る人たちからも、セット椅子に座る人たちからも……。
そして、私はふと思い出しました。以前にも同じような感動を味わったことがあったことを。そう、それはC市にあるM美容室でした。そこでも私はお客様から暖かく迎えられたのでした。
1人のお客様が私に向かって言いました。「このお店は初めてですか? よいところに来られましたね。ここは天国ですよ」。もう1人が言いました。「私はこのお店の人たちに会いたくてしょうがなくなって来るんです」……。
ちなみに先のサロンAがあの驚異的な成人式売上げを実現したことも、その5年後、売上げを5億円に伸ばしたと聞いたときも、根本は人間対人間の深いかかわりがなしたことだと、私は1人で何度もうなずいていたのでした。
いかに「面倒なこと」に取り組むか
プロが苦労したぶんだけ客が喜び、プロが楽したぶんだけ客が悲しむ、と言われます。
サロン繁栄の秘訣は、相手がスタッフにせよ、顧客にせよ、とにかく自分が1人の人間としてどこまで徹底してかかわっていけるかということに尽きる、と私は思っています。
1人の人間としてトコトンかかわるというのは、並大抵のことではできません。手間暇がかかります。個人の悩みや苦しみにも触れることになります。人間対人間の難しい問題にも触れることになります。
でも、それが人間。人間としてのかかわりとは、そのようなもの。マニュアル的に接したり、自分に都合のよい接し方で済ませたりしている限りは、スタッフや顧客のみならず、友人、家族、そして最愛の人までも失ってしまうことになるでしょう。
忙しくてスタッフと接する暇がないとか、職場は仕事をする場所だからとスタッフ間の人間関係には目を向けないでいるトップのサロンでは、ギスギスして潤いがなく、信頼関係もつくれず、勤労意欲も失せて、職場を去るスタッフが多くなり、当然ですが売上もダウンしてしまうのです。
トップがそれを自分の怠けによるものと自覚しない限りは、どんな方法を用いても結果が好転することはないでしょう。
癒しは愛
行きたくて仕方がなくなる店がある。会いたくて仕方がない人がいる店がある。
なぜ行きたくなるのか。なぜ会いたくなるのか。
それは、この「いのち」を暖めてくれるから。
どんなに表面は快活に振る舞っていても、心の中に苦しみや悲しみを抱えていない人はいない。
言わなければ、誰にもわかってもらえないこの思いを、そっと受けとめてもらったとき、人は癒される。
人はそのとき愛されていることを感じるのだ。愛には愛が返ってくる。
愛そう、そして心をこめて尽くそう。
誰もがいつ消えるかわからない人生を生きているのだから。
そして、もう二度と会えないかもしれないのだから。
あなたが顧客を1人の人間として愛したときに、それは繁盛という結果となって返ってくるのだ。(了)
最終回を迎えました。1年の間、拙文とお付き合いいただき、ありがとうございました。また、通信添削を通じて、皆様と暖かな交流を持てましたことを心より感謝いたしております。
皆様からの回答は何度も何度も読ませていただきました。脳裏に浮かび上がってきたお1人お1人の姿に向かって、感じるままに失礼を顧みず私の思いをぶつけてしまいましたこと、どうかお許しください。
書いてお伝えすることのもどかしさに、何度お会いして語り合いたいと思ったことでしょうか。
まだ見ぬあなたですが、誌上でのこの出会いをこれからも大切にしていきたいとこころより願っています。
最後に、この講座を支え、励ましてくださったBBcom鈴木社長はじめスタッフの皆様全員と、この連載のきっかけをつくってくださった菅野孝社長(ブレーンブール)、上村修社長(OK倶楽部)、そして田中晃一社長(ビューティフルライフ)に心より御礼申し上げて、ここに閉講させていただきたく思います。
ありがとうございました。 林 英憲
人間性回復の経営学(全12回)
| 回 | テーマ | サブテーマ |
|---|---|---|
| 1 | 第1回講義 心の枷(かせ)をはずしてみよう | 常識との対決...思い通りの人生を歩むために |
| 2 | 第2回講義 自分は一体何者なんだ | 自分の臭さに気づいていますか |
| 3 | 第3回講義 人間関係の極意教えます | (極意につき極秘) |
| 4 | 第4回講義 人間尊重こそ繁栄の原点 | 手間暇惜しまず "one to one" |
| 5 | 第5回講義 感動と絶望について | 説得では何も変わらない |
| 6 | 第6回講義 不安と孤独について | お触りサロンのお勧め |
| 7 | 第7回講義 犯人は誰だ! | 犯人は◯◯だ! |
| 8 | 第8回講義 停泊中の船舶に告ぐ…直ちに出航せよ | 経営とリーダーシップについて |
| 9 | 第9回講義 決別の決断 | 1本の命綱を誰に投げるのか |
| 10 | 第10回講義 一流の条件 | "らしさ" の追求と発揮 |
| 11 | 第11回講義 文化の発信基地として | これこそサロンの使命だ |
| 12 | 第12回講義 もっと儲けよう、そしてもっと使おう | 愛と奉仕の実践 |