巷ではプログラミングだのAIだの騒がれているが、バズワードで盛り上がっては冷めていく、マーケティングと偽称した身勝手であからさまな市場操作バイアスは今に始まった事ではない。
これからの時代、ITエンジニアという専門職は狭く深くなっていく。必要とされる人材の数は減っていく。
使う側、作る側
使う側はより簡易に高度な機能が使えるようになっていく。
Goal: ドラえもん、アラレちゃん
Newtypeは、高度に専門家した未来のエンジニアに与えられる称号ではない。Newtypeは、シンギュラリティ後の、人間の制御を離れたautonomous growthをもつシステムを使いこなす者のことを示す。当然、部分的なシンギュラリティも含む。
使う側の教育は、暫定的なものだ。現在のITシステムは総じて理解し難く、使いこなすまでのコストがかかる。一輪車と自動運転車の難易度を比較してみればいい。したがって、あるラインよりも高齢な人に対して提供する使い方レクチャーは現在需要がある。だがそれも使うリテラシーがあるラインまで到達するまでの話だ。識字率と同じだ。
未来を生きる若者に教えるべきは、使う側のリテラシーではなく、作る側の知識だが、求められるものがより深く広くなっている。さらに、求められる人材は減る。なので限られた適性のある者だけが携わればよい。
プログラマーの大量生産は、非効率的で非生産的で競争力のない企業が生き延びるための浮き輪にしかならない。沈みかけた船は浮き輪では止められない。
DX、クラウド、スマホ、XaaS、ASP、ダウンサイジング、……。
経済の力でハラスメントをするのはもう終わりだ。ここまで来たら、もう戻せない。
GIGAスクール構想、プログラミング授業導入。
ITの本質をまるっきりわかってないとしか僕には思えない。
かくしてITの世界では数多くの仮想化・カプセル化・ライブラリ化が積み重なり、さらにオープンソースが広がりを見せ、経済がどうあれこの世界はやはりエンジニアたちの自由思想に対して金で操れるものは存在しないことが証明されつつある。
情報技術(IT)は物事を理論的に整理し、効率化や体系化を推し進める。それによってロボティクスなどの工業における応用が進歩する。工業そのものも新たなる数学的発見や物理学的進歩にあわせて高度化している。
みなさんこれがどういうことを意味しているのか、お分かりか。
人間がやるべき仕事は減る一方で、人間が必要とするアートは増える一方なのだ。
半端な職人はどんどん不要となり、必要とされる技術レベルは常にコンピュータなどの進化より上にある必要がある。
プログラマーばかり育てて、今更どうしようというのだ。
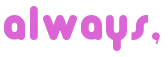
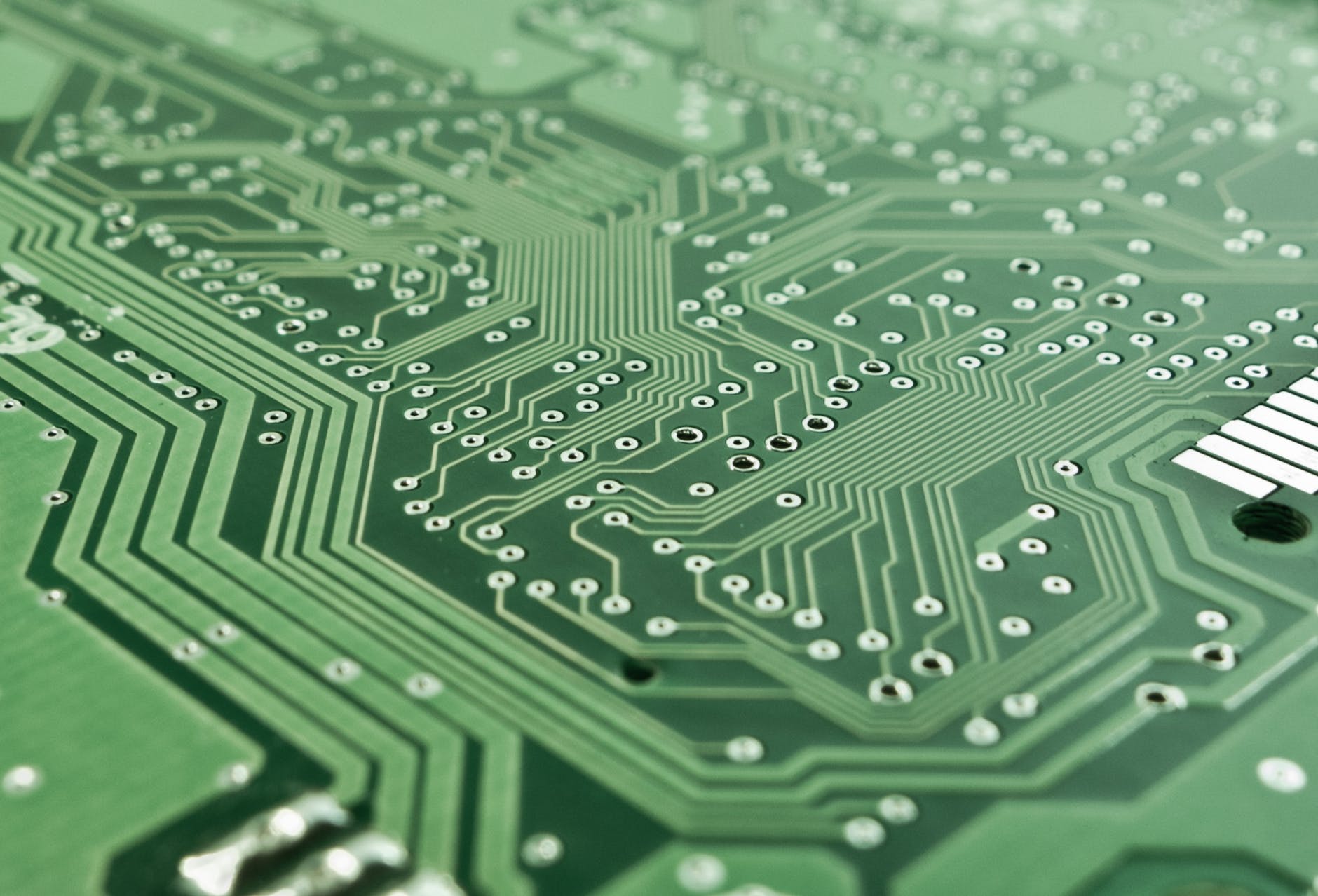


コメント