息子たちが終業式を迎え、通知表が渡された。
2002年度以降の通知表は昔と違って絶対評価であり、5が何%のような相対評価はない。
ところで、各教科の成績がどうだったかについては、ほとんど興味がない。僕が注視しているのは次のようなことだ。
- 好奇心・新しいことへの興味がどの程度発現しているのか
- 自分が好きと思えることに対してとことんやり抜いている兆候はあるか
- やりたくないことにどう対処しているか
好奇心のままに何かを貫くとき、必ず突き当たるのが取捨選択の壁だ。人間には等しく1日24時間という時間が与えられている。それをどううまくマネジメントしていくかという課題は人生の始めから終わりまで尽きることがない。そうすると、自分が本当にやりたいことのために割く時間を確保するためには、捨てなければならないものがあるということを認識する。
取捨選択のためには、優先順位付けが必要だ。また、複数の興味カテゴリをどうしたら同時に満たすことができるか? といったような疑問を持ち、その答えを探すことを諦めない心も必要かもしれない。
優先順位付けをしたのに行動に反映されない場合は、それはほぼ間違いなくその優先順位が自分の心から願っているものではなく、頭で考えた優先順位であるのだが、心で決めていようが頭で決めていようが、僕はあまり関係がないと思っている。
何か新しいことをやるとき、何か古いものを捨てる必要がある。
古いものを捨てることができないとき、人は行動できずにその場に留まってしまう。
小さなことからスタートしてもいいから、新しいことにチャレンジすることの楽しさを知ってほしい。そして失敗とはそんなに恐れる対象ではないということも知ってほしい。
「秀才」と評されてきた人ほど、失敗を恐れる傾向がある。「努力の成果」「成功率」に対する執着が強い人が多い。なんとなくでも、多くの人にその機序はわかると思う。
多くの子供たちと接してみて、やはり子供は好奇心や興味を爆発させるように生まれてきているんだなと思う。それが物心つくかつかないかの頃から、様々な「常識」や「ルール」について学ばせることなく無条件に押し付けてくる大人たちの環境に少しずつ毒されていく。
「天才」とは、そうしたバイアスに屈することなく子供らしさを貫いて行動した結果、他者にそれを認められることに他ならない。ここでいう結果とは、大人基準での成果のことではない。
子供心を忘れてしまった大人が大多数のこの世界を裏返したい。長い間そう願って生きてきた。
キラリと光る人、好奇心や興味のままに行動することを捨てなかった人。そんな人に出会うとワクワクする。
ところで、猫って好奇心のままに生きてる。
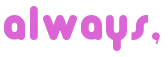



コメント