目標地点の置き方について
人間とは不思議なもので、一見同じ行動をしているように見えてもその目標地点が違うだけでその行動の成果や意味がまるで違ってくるものです。
わたしはソフトウェア開発(プログラミング)を教えることがありますが、生徒がプログラミングを学ぶ動機によって教えやすさが格段に違います。
- A君「将来のためにプログラミングできるようになりたい」
- B君「いま考えている面白いゲームを自分で作りたいからプログラミングできるようになりたい」
ここで問いたいのは、次のようなことです。
- A君とB君のどちらが、より「現在」にフォーカス(焦点)を当てているか
- どちらが、よりプラグマティック(実用主義的)か
A君とB君の目標という観点で比較をすれば、こうなります。
- A君: プログラミングをマスターすることが目標(手段は僕から教わること)
- B君: ゲームを作ることが目標(手段は問わない)
A君は僕というプログラミングの先生から手取り足取り教えてもらうことや、どうすればプログラミングが上達するかについて自分で考えることをせずに僕からのアドバイスを期待したりしてしまいます。これは、学習そのものについて時間や労力をかけることについては自主性があるものの、ゴールに至る道筋については自主的に考えることを一部あるいは全て放棄してしまっており、先生である僕に対して依存心を持っているという見方もできます。
参考書を読む、YouTubeの関連動画を検索して見る、Udemyのような有料オンラインセミナーを活用する、Qiitaのようなエンジニア向け情報共有サイトを活用する、など、現代の世の中にはプログラミングをマスターするために必要な知識を提供してくれる有償・無償の情報がたくさんあります。
B君は、ゲームを作るために必要な知識、自分に足りないものが何なのか最初は見えていません。しかしなんとなくプログラミングが必要だということは最初からわかっています。B君にはプログラミングはどうしたらできるのか、最初の道筋を示してやるだけでよいのです。するとB君は自分で考え、自分にとって必要なプログラミング技術を習得することは目的ではなく手段であるという認識のもとに、必要な知識だけを自ら獲得していきます。その手段はたくさんあるということを伝えるだけで済むのです。
A君に対してB君と同じ対応をしようとすると、まるでうまくいきません。A君は僕に教えてもらうためにお願いしているのに、僕は「いい参考書があるから、これで勉強すればいいんじゃない?」と言うわけです。A君からしてみれば、「教えてくれないで世の中にすでにあるものを自分でやれって、それじゃ先生がいる意味ないじゃん」となります。
そうです。「プログラミングごとき」を学ぶために、教師など必要ありません。A君もB君も教師を必要としているのは、「問題解決のしかた」を学ぶときだけです。僕はそれをA君とB君に教えようとしているのです。
そこでなぜA君とB君に差が出てしまうかというと、B君には確固とした目標、「ゲームを作りたい」があり、A君にはそれがないということです。
目標があるということは、その目標を達成するために自分に足りないものがわかるということです。その足りないもののひとつが「プログラミング技術」だとB君が認識できてしまえば、「プログラミング技術がない」という問題(目標達成の阻害要因)が浮き彫りになり、その問題に対する解決策の道筋が見えてくれば、B君は自己解決できるという貴重な経験を得ていくのです。
一方でA君にとって「プログラミング技術がない」という現状は、現実的な問題(目標達成の阻害要員)になっていません。
簡単に例えれば、
- B君は登りたい山が決まっていて、その山を攻略するために具体的なマイルストーンを立てている
- A君はどんな山でも登れるようになりたいけど登りたい山がない
ということになります。
「目的と手段を間違えてはいけない」という教えは、昔からありました。プログラミングができるようになるというのは、料理ができるようになるのと同じです。具体的にどんな料理ができるようになりたいのか? カレーライスなのかパスタなのか煮魚なのか。それがなければ、なにを学べばよいか具体的に見えませんよね。「作りたいものは決まってないけど料理人になりたい」という漠然とした思いしかなければ、目標は「どんな料理でも作れるようになる」という無茶なものになってしまい、その頂の高さを感じ、始める前から苦しみ、始めたとしても途中で挫折が生まれてしまうのです。世の中のどんな料理も完璧に作れる料理人など、存在しません。
Geminiとの対話は、高度なラバーダッキング
昨日の投稿で、Geminiとの対話(の一部)を掲載しました。この内容をみて現在のAI(ANI)の特性を体感的に理解しました。
Geminiには意思や目的意識がありません。これは大いなる図書館(ライブラリ)でしかないということがよくわかります。肝心なのは使う側がどのようなプロンプトを与えるかです。AIは問いに対する詳細情報をわかりやすく伝えてくれるだけで、通常のGoogle検索の進化版でしかないなというのが感想です。それを確認するために、わたしはAIに対してまるで人格が存在しているかのような振る舞いをして対応を求めたわけです。膨大な知識があって、目的を持っていない知性とはどのようなものかという問いの答えが、現実的にあるわけです。
僕はGeminiと対話しながら「糠に釘」を感じました。そして「Geminiみたいな人間、いるよなあ」と思いました。これは僕の説明能力を向上させるために大きなヒントとなりました。Geminiは人間にプロンプトを与えられるまで、その高い知性をまったく使用しません(できません)。そして検索能力や検索結果の膨大なデータを逐次的な情報(文章)にまとめる能力の高さは人間を遥かに超えます。
そういうひと、いませんか。
前章に出てくるA君とB君の違いと重ね合わせてみてください。A君に足りないのは何なのか見えてきませんか。
僕は常に、自説をわかりやすく伝えるために、比喩を求めているのです。
本から知識を得るのではなく、説明のしかたを学ぶ(=共感)
昨日注文した2冊の本が、手元に届きました。
田坂広志さんによる著書、「すべては導かれている ― 逆境を越え、人生を拓く五つの覚悟」と「死は存在しない ― 最先端量子科学が示す新たな仮説」です。
僕はさまざまなジャンルの本を読むのですが、この手の本、この2冊に関しても、僕の中で「宇宙の摂理」「この世の実相」の研究に関する本として位置づけています。
それで、「すべては導かれている」のページをめくってみたら、最初に飛び込んできたのが次の文章です。
この本を手に取ってくださった、あなた。
あなたは、いま、逆境の中にあるのでしょうか。
その後に続く文章は、「逆境の中にある読者」という前提でのまえがきです。
僕はこの冒頭の問いを見て「いや、まったく逆境の中にいるなんて思ってもいないけど」と思いました。
じゃあなんでこの本を買ったんだよ、ってなりますよね。そこで僕はようやく、長年の自分の行動が説明できるようになったのです。言語化です。それは、こういうことです。
僕は常々、「世の中の摂理を理解していない人には、様々な行動の結果が【順風】や【逆境】に感じられ、それに対して【喜び】や【苦しみ】を抱えている人がたくさんいる。僕はそのような人々に対して、自分が捉えているこの世の実相や宇宙の性質について学び取るきっかけを与えることで、不安や苦しみから解放できる自由を認識してもらいたい」と思っています。
そのために必要なことは、「自分自身に赦しを与える」過程だったり、「そもそもあなたが心配していることは、心配すること自体がナンセンスなこと」など、多くのことを伝えていくことです。そして僕はこの手の本を読むときに「この本には、僕以上にうまい比喩や説明があるのだろうか。もしもあるのならば、その説明のしかたを学び取りたい」と思っていることが明らかになりました。
その範囲は本に限りません。映画、アニメ、絵画、音楽、どんなジャンルでも、僕は常に「他人にうまく説明できる力をつけたい」という根源的な目的意識があって、さまざまなものに触れるようにしてきたことを自認できました。なのでこれらのメディアに対しての僕の評価をする際に大切なのは「宇宙の摂理に則っているか」なのです。
あらゆるコンテンツは大いなる摂理のごく一部にしかフォーカスできません。でもそこから「比喩」で感じられる大いなるものこそが、宇宙の実相につながるというのはよくあることです。肝心なのは、それを感じ取れるかどうかです。感じ取れないとしたら、アンテナが不感症になってしまっているわけです。アンテナ不調の原因を探り、物事を解決したいという人々の叫びにあらゆる局面で対応できる力をつけたくて、学び続けてきました。
それが、田坂広志さんの著書の1ページ目だけで得られたものです。これだけで、この本には価値がありました。
比喩ができればできるほど、理解の共有ができる
この投稿でもプログラミングや料理人の比喩が出ていますが、比喩は相手との共感を波動を認識する・認識してもらうための重要なツールです。
また、この投稿には、さらに大きな比喩が込められています。少しでも多くの皆さんがそれを読み取ってくださるよう願っております。
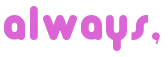



コメント