ひとの脳や神経をつなぐ全ネットワークは、電気信号や化学反応によって脳細胞間を伝播する信号を複雑に処理するひとつの器官。
さまざまな信号が飛び交っており、ある研究によれば、人間が意識下で認識できる信号は、体内を飛び交う信号の0.1%程度だそうだ。つまり、人間は、知覚している情報の1,000倍もの情報量を、常に体内で扱っているということになる。
心臓の鼓動や内蔵の動きなどを司る信号も知覚できない情報の種だ。また、たとえば何かに触れた時、知覚できる情報がすべての情報ではないという実験結果を、次の書籍では説明している。
[amazonjs asin="4062196131" locale="JP" title="驚きの皮膚"]
内容紹介
120万年前、体毛を失って身体中の皮膚をさらしてから、人間の脳は大きくなりました。著者は、人間の言語の獲得にも皮膚感覚が関与していたと考えています。そして、人間の皮膚感覚にはふだん私たちが知らない驚きの能力がたくさんあります。皮膚は「見ている」「聴いている」「味わっている」「考えている」「予知する」……。本書ではそれらを国内外のさまざまな興味深い実験とともに紹介します。一例を挙げればこんな実験。一人の被験者にABCD四つの山に伏せられたカードを引かせます。カードには、いくらもらえる、いくら支払う、という指示が書かれています。100枚引いたところでゲームは終了しますが、多くの被験者は80枚くらいの段階で、どの山のカードが支払いリスクが高いか気づきます。ところが、同時に皮膚の電気変化を調べると50枚くらいでリスクの高い山のカードを引くときに「無意識」の電気変化が現れるのです。つまり、皮膚は脳より先にリスクを「予知している」ことになります。
本書は、そうした文字通り「驚きの皮膚」感覚を検証するだけでなく、その皮膚感覚のおかげで大きくなった脳が「意識」を司り、文明を創り、さまざまな社会システムを生み出し、今、その社会システムゆえに、時に個人の自由が奪われたり、あるいは生命が脅かされている現状に警鐘を鳴らします。
やがて著者の筆は、システムが複雑巨大化する中で、美術、音楽、文学など、芸術の世界で、皮膚感覚という原初の本能への回帰が、人間一人一人の生きる意味を問うていることにまで伸びていきます。
ゴッホ、マーラー、村上春樹をはじめ、多くの実例を引いた著者のロマンチシズム溢れる文章は、単なる科学読み物の域を超えて、多くの読者の知的好奇心を刺激することでしょう。皮膚には視覚、聴覚があり、あるいは、記憶し、予知する力がある。その知られざる「皮膚感覚」を説く気鋭の皮膚研究者が、村上春樹のエルサレム・スピーチを引用するとき、私たちが「裸のサル」になった本当の理由と運命が明らかになる―。知的にしてスリリング!ページをめくる指先の快感!
わたしたちは、脳で知覚していると思いこんでいるが、果たしてそうなのかもわからない。
確かにわたしたちは、皮膚や神経などに散在している受容体を通して、外界とよばれる世界の情報をprobe(探査)している。
よく知られている五感。それは、すべて波動のセンサーであるということができる。
受容体は、波動を何かしらの化学的・電気的信号に変換するための装置と言い換えることができる。
触覚は、わたしたちの身体がどこか自分以外のものに触れたときの圧力等を、受容体が感じとるものだ。それでは、実際にモノに触れたとき、ミクロの世界では一体なにが起きているのか。
指がテーブルに触れる瞬間、そこではなにが起きているのか。
身体を構成する原子と、テーブルを構成する原子が、最接近する。
そのとき、まるで宇宙のような壮大なことが起きている。
原子の電荷、原子核を取り囲む電子の存在座標可能性の変化。量子ゆらぎ。原子による原子の観測。
それは、観測されていない物質の持つ波動としての特性が、観測を経て粒子の特性を持つ物質として認識・認知されるまでの、まるでビッグバンのように荘厳で、美しい世界が広がっている。
ただ、テーブルに触れているだけ。
波動と波動の影響で、波動の変化を起こし、波動を観測していると言い換えることもできる。
嗅覚や味覚も、物質と臭細胞の間で同じようなことが起きている。
聴覚は、耳の外にある空気の圧力の変化、つまり音の波動を鼓膜や身体が感じとる。音の波長は、音階。
視覚は、光の波動を網膜が感じとる。光の波長は、色。
わたしたち人間の耳には、不可聴域といって、あまり波長の短かすぎる音(超音波)や長すぎる音(低周波)を聞き取ることができない。同様に、波長の短すぎる色(紫外線)や波長の長過ぎる色(赤外線)も視認することができない。
感じとることのできない波長の音や光は存在するけれど、人間の感覚器で受容できる範囲には限界があるということです。
五感すべてにおいて、そうした感覚の限界があります。しかしその限界には個人差があります。
たとえば年をとると高い音が聞こえにくくなったりするのも、老化によって限界が低くなっている。
生まれつき、ある感覚だけとても鋭い人もいるし、訓練によって鋭くなる人もいる。
たとえばソムリエ。たとえば音楽家。たとえば絶対音感。たとえば画家。
識別できる色の数も、人によって異なる。
味覚が鋭ければ、よい料理人や料理評論家になれるかもしれない。
嗅覚が鋭ければ、よい調香師になれるかもしれない。
一般的に多くの人が見たり聴いたりできる周波数。
それが、最大公約数的なこの世界の姿。
しかし時には、他の人には見えないものが見える人がいたりするのも、不思議とは思えない。
五感を研ぎ澄ましていけば、その先にある無限の可能性に気づく。
さらに言えば、五感以外の感覚についても、現代科学では解明されていないというだけで、人間は持っている可能性があることを示唆するさまざまな実験データが存在する。
たとえば頭の中心部に近いところに存在する、松果体という小さな組織。
この組織は、概日リズム(体内時計)を調節する、メラトニンというホルモンを分泌する。
概日リズムについて調べてみると面白いことに、人間もそれ以外の動物も、真っ暗闇の中に閉じ込められると、24時間の概日リズムが崩れる。つまり、概日リズムの維持と日照は切っても切れない関係。昼夜の認識ができないと、体内時計は狂うことが証明されている。
つまり松果体は何らかの形で太陽光線を受けているということを認識して、それをトリガーにしてメラトニンの調節をしている。
トカゲ類の一部などには頭頂眼と呼ばれる第三の目が存在することが知られているが、頭頂眼が退化して頭蓋近辺から脳の奥のほうに引っ込んでいったものが、松果体である。
発生過程を見れば、松果体は頭頂眼と源を一にする器官である。まず頭頂眼について説明する。
脊椎動物の祖先は水中を生息圏として中枢神経系を源とする視覚を得る感覚器に外側眼と頭頂眼を備えていた。外側眼は頭部左右の2つであり現在の通常の脊椎動物の両眼にあたる。頭頂眼は頭部の上部に位置していた。初期の脊椎動物の祖先は頭部の中枢神経系で、つまり今では脳に相当する部分に隣接して存在したこれら左右と頂部の視覚器官を用いて皮膚などを透かして外界を感知していたが、皮膚の透明度が失われたり強固な頭骨が発達するのに応じて外側眼は体表面側へと移動した。また、外側眼が明暗を感知するだけの原始的なものから鮮明な像を感知できるまで次第に高度化したのに対して、頭頂眼はほとんど大きな変化を起こさず、明暗を感知する程度の[4]能力にとどまり、位置も大脳に付随したままでいた。やがて原因は不明ながら三畳紀を境にこの頭頂眼は退化してほとんどの種では消失してしまった。現在の脊椎動物ではヤツメウナギ類やカナヘビといったトカゲ類の一部でのみこの頭頂眼の存在が見出せる。
受精後に胚から成長する過程である動物の発生過程では、動物共通の形態の変化が見られるが、この過程で頭頂眼となる眼の元は間脳胞から上方へと伸び上がる。この「眼の元」は元々は左右2つが並んで存在するが、狭い間脳胞に生じたこれらはやがて前後に並んで成長する。2つあるうちの片方が松果体となり、残る片方はある種の爬虫類では頭頂眼となるかまたはほとんどの種では消失してしまう。
脊椎動物における松果体
脊椎動物の中には、松果体細胞が目の光受容器細胞に似ている動物がある。松果体細胞は進化において網膜の細胞と起源を同じくすると考える進化生物学者もいる。
脊椎動物には、光にさらされると松果体で酵素、ホルモン、ニューロン受容体に連鎖反応が起きるものがあり、この反応が概日リズムの規則化を起こしていると考えられる。
ヒトなどの哺乳類では、概日リズムの機能は網膜視床下部によって行われ、視床下部視交叉上核の中にリズムが伝えられる。人工的な光にさらされると、視交叉上核の時計に影響が起こる。哺乳類の皮膚で合成されるオプシン関連の受光機能については、現在論争中である。松果体が磁力感知の機能を持っている動物がいるとする研究もある。
鳥類の1種ニワトリの松果体には、ヒトの網膜などで見られる光の感知に関与するロドプシンに似た、ピノプシンと言うオプシンの1種が見つかっている。また、スズメの頭骨は薄いため、スズメの松果体には太陽光が直接届いており、スズメの概日リズムに関与していることが知られている。
この他、現在のヤツメウナギやムカシトカゲなどに見られるように、脊椎動物(または脊索動物)には松果体の近くに頭孔を持つものがいる。
わたしたち人間はいま、目をつぶる、あるいは目隠しをされてしまうと明暗を認識できないと思いこんでいる。
しかし実際には皮膚そのものは明暗を認識できる受容体を持つことが判明しているし、松果体そのものも今でも明暗を認識できている可能性がある。それはわれわれの知覚にまで届いていないだけで、皮膚による明暗の感覚が信号として松果体に送られているのかもしれないし、脳の奥深くにある松果体そのものが、何らかの方法で明暗を認識できているのかもしれない。
ところで人間の松果体はよく、石灰化する。
松果体の石灰化はヒトの成体においてよく見られる変化である。16歳を過ぎた頃から、松果体にはカルシウムやマグネシウムが盛んに沈着するようになり、やがて石灰化して、X線撮影をすると骨と同じように容易に見えるようになる。
さらに調べると、石灰化は松果体だけで起きているわけではないこともわかる。
さらにさらに掘り下げると、脳だけではなく、全身に石灰化が起きることもわかる。
とまあ、調べだすとキリがない。いまここで問題視したいのは、脳や神経系の石灰化によって引き起こされるものが何かということだ。
脳神経系が石灰化すれば当然、認知・思考・判断・行動に支障があらわれると考えるのが合理的だ。
石灰化して問題が起きないのならば、石灰化したその器官はもともと不要だったということになるわけで。
認知の最前線の現場は受容体をはじめとした、外界との接点にある。物理的に考えればそうだ。
しかしそこで起きている量子レベルの「認知」について深く掘り下げてみると、実に面白いことがたくさん見えてくる。
さらに、認知そのものに問題を抱えてしまった人は、外部から見れば思考や判断に問題を抱えてしまったように見える。
たとえば認知症の患者。しかしそれって、人間の存在が身体のあらゆる器官を通じてこの世界とのコミュニケーションを達成しているだけのことで、そのコミュニケーションに必要な道具としての肉体に障害が現れただけのことだから、実際人としての中身まで変わってしまったと言い切ることはできない。
[amazonjs asin="4041068991" locale="JP" title="跳びはねる思考 会話のできない自閉症の僕が考えていること (角川文庫)"]
本書の著者は自閉症で、まともに会話もできないが、文章を書くことはできた。彼の中でいったい何が起きているのか本書で説明してくれている。貴重な本だと思う。彼の言葉を借りると、
僕は、まるで壊れたロボットの中にいて、操縦に困っている人のようなのです。
☆☆☆☆☆
そうしてかつて、宇宙とつながりのあった人類の魂は限定的に引き裂かれ、蒼い惑星へと向かった。
存在はすべて。そして存在の一部であるわたし。
それは幻想であるがこの物質世界において観察され実体化しているように魅せているそれがわたしでありあなた自身なのである。
古今東西、あなたはあなたでしかなく、そして、わたしである。
わたしはあなた自身が答えを導き出すことができるよう、様々な道標をあなたに授けてきた。
求めよ、されば与えられん。
別次元の存在を創造するのも、この世界を体験するのも、同じわたしなのだ。
認知という深淵に飛び込んでものごとを考えると、
一体わたしたちは本当に、人の姿をしているのだろうか、とか、
いま見えているものは、脳が便宜的にそう見えるように処理してくれているだけなのではないか、とか、
いろいろ考えることになるだろう。
クオリア。
あなたとわたしは、同じものを本当に同じように見ているのだろうか。
宇宙レベルの多様性のキーワードがここにあり、
認知や知性というもの、知能というものが、決してわたしたち人類に認識され得る形で眼の前に現れるとは限らないということを示唆してくれる。
眼の前の石ころには、知性があるのかないのか。
それを証明することは、いまのところ、わたしたちには不可能だ。
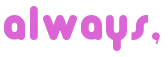

コメント