ときに人生は荒野。ただひたすら広く、乾き切った冷たい風が砂埃を頬にぶつける。地平線の彼方に聳える山脈を目印に、砂が目に入らぬよう瞼を細めて、黄土色の大地に転がる石を踏みつけながら、一歩ずつ進む。時折、何もかも投げ捨てて引き返したい衝動に襲われる。しかし後ろを振り返っても、荒野。山岳。ジャングル。雪道。今まで歩んできた道のりに思いを馳せて、もう戻ることはできないと知り、また前を向き、歩く。
陽炎の向こうに動く影。ポンチョを纏った人がいる。彼か彼女か判断できないが、おそらく自分と同じ旅人だ。
何日もかけて、動く影が少しずつ近づいてくる。このままいけば3日後くらいには、互いの道が交叉する。
2日過ぎた日暮れ時、挨拶を交わす距離まで近づいた。やはり旅人だった。ここにキャンプを張り、一晩を共に過ごすことにした。
火を囲みながら、互いの旅路で目にしてきたことを語り合う。わたしは干し肉を勧め、旅人はわたしが今まで見たこともない不思議なパンをくれた。それはとても固いパンだったが、噛めば噛むほどに味が染み出してきた。
わたしは残り半分を切ったテキーラを、羊の胃袋のボトルから注いだ。もちろん旅人の分も。
旅人は見知らぬ透き通った容器から、白く濁った酒をわたしの器に注いだ。これも初めて口にするものだったが、甘くて素晴らしく美味だった。旅人によれば、この酒は東の彼方、山をいくつも越え、計り知れない大きさの川を渡った先にある村で手に入れたという。
焚火の炎が鎮まり、わたしたちはそれぞれのテントで眠りについた。
その晩わたしは、いままで経験したこともない深い森の先にある、不思議な家に住み、不思議な服を着て、不思議な食べ物を食する人々を訪れる夢を見た。この荒野と違って、その村には水が豊富にあった。
目が覚めると、風はなく、空気が澄んでいた。東の山脈の上に広がる空が深紫に染まり、橙色に変わっていく。
振り返ると、旅人が同じ空を眺めていた。
わたしたちは言葉を交わすこともなく、それぞれの旅支度を始めた。
去り際に、互いの旅路の無事を祈りあう。
そしてまた、いつも通りの旅が始まる。
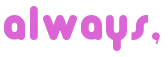

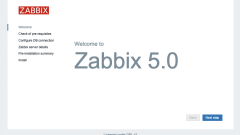

コメント