富の創りかた
この文章では、まず第一章で現在あるいは少し前の時代において王道ともいえる富に対する捉え方とその創り方について記述する。それはかつて多くの書籍や成功者によって何度も語られてきたものでもあり、会社という枠組みを成功に導くのが目的なのだとしたら参考になる話だ。
第二章では、これからの世界に適合した富の概念の説明および価値観のアップデート、そしてそれを前提にした富の創り方について記述する。この章では、第一章で主張していることの多くがまったく逆の主張になる。
これはまだ今の日本では理解できていない人が多いし、さらに世界の最先端のその先に飛び出す話になる。チャレンジャーが少なく、比較によって成否の確率を判断する方にはなかなか受け入れがたい内容かもしれない。
第三章では、実際にTOWNSHIP LABOが向かっている方向、やってきたことの理由、そしてこれから何をしていくのかについて述べる。
第一章:既存経済社会への適合
裕福になりたいと思ったらどうすればいい? 一番分の良い方法はおそらく、ベンチャー企業(スタートアップ)を起こすか、それに参加するかだ。これはここ数百年にわたって、裕福になる信頼性の高い方法である。「スタートアップ」という言葉が使われるようになったのは1960年代からだが、その中身は、中世に資本家がスポンサーとなっていた貿易航海で行われていたこととほとんど同じだ。
ベンチャー企業は通常、新しい技術と関連がある。だから「ハイテクベンチャー」というのは冗長な言い回しとも言える。ベンチャー企業とは、困難な技術的問題に挑戦する小さな企業だ。
専門以外のことは何も知らないでも裕福になった人々はたくさんいる。良い投手になるのに物理学を知る必要はない。でも、基礎となる原理を理解しておいたほうが、有利な立場に立てるんじゃないかとわたしは思う。なぜベンチャー企業は小さくなくてはならないんだろう。そして、なぜそういう新興企業は新しい技術の開発に取り組むんだろう。ベンチャー企業のほとんどが、サラダ油や洗剤ではなく、新薬やコンピュータソフトウェアを売っているのはなぜなんだろう。
命題
経済的には、ベンチャー企業は一生分の労働期間を数年間に圧縮したものだと考えられる。ゆったりと40年働く代わりに、可能な限りハードに4年間働くんだ。技術の分野では速い仕事により価値があるので、この手法はとりわけ有利だ。
この経済的な命題を簡単に述べてみよう。あなたが20代半ばの優秀なハッカーだとすると、おそらく年俸800万円くらいの仕事を見つけられるだろう。ということは、そのハッカーが平均して会社に800万円の利益をもたらせば、会社としてはトントンということになる。さて、やろうと思えばおそらくあなたは、従業員として働く時間の2倍の時間を仕事に充てることができる。そして集中すれば、おそらく1時間当たりの生産性は3倍くらいに上げられれうだろう。
ベンチャー企業のみで得られる貴重なことのひとつは、中断されないことだ。職種によって、時間の単位は異なる。文章の校正係は、15分ごとに作業を中断しても、生産性にさして影響を与えないだろう。だが、ハッキングの時間単位はとても長い。問題のすべてを頭に収めるだけで1時間を要するかもしれない。そんな時に、あなたが書類を埋めるのを忘れたことを指摘する電話が来たりすると、その影響は計り知れない。
ハッカーが質問をされて、スクリーンから目を離す時におそらく不機嫌な目つきをしているのはこのためだ。ハッカーの頭のなかでは、巨大なトランプの家が崩れているんだ。
中断されるかもしれないと感じるだけで、ハッカーは難しいプロジェクトを始めるのを遅らせる。ハッカーが夜遅くに仕事をしたがるのはそのせいだ。素晴らしいソフトウェアをブースで書くことが、深夜ででもなければほとんど不可能なのもまたそうだ。
ベンチャー企業の大きな利点は、邪魔するような人がまだいないということだ。事務部はないから、書類の催促の電話もかかってこない。
また、大企業にいる、髪のとんがった中間管理職の上司に足を引っ張られなければ、少なく見積もってさらに2倍の仕事ができる。さらにもうひとつ係数がある。求人票に出ていた仕事内容に比べて、あなたはどれくらい優秀だろうか。この係数を3倍と見積もろう。すべてを合わせると、適当な会社に入って仕事をするのに比べて、あなたは36倍の仕事をする能力があるということになる。
ベンチャー企業では大企業より人々が20倍も30倍も働くという事実に直面して、大企業の役員は、自分のところの社員に同じくらい働いてもらうにはどうしたらよいかと頭をひねるはずだ。答えは簡単だ。その分、給料を払えばいい。
ほとんどの企業では、内部は共産主義国家のように運営されている。自由市場をそれほどに信奉しているなら、会社もそのように運営したらどうなんだろう。
仮説:企業は、従業員それぞれが自分の創り出す富に比例する給料をもらえるときに、最も多くの利益を出すようになる。
もし、かなり優秀なハッカーが大企業で800万円の年俸に値するとしたら、その人物が、足手まといになる企業内のごたごたに縛られずに仕事をすれば年間3億円の仕事ができることになる。
もちろん実際には、これ以外にも色々な要素が絡んでくるはずなので、この数値そのものの正当性を主張するつもりはない。でも計算式自体は間違っていないと思う。係数が36ぴったりであるなんて言うつもりはないが、たぶんそれは10より大きいだろうし、かといって100まではいかないだろう。
年間3億円というのが大きすぎる数字に思えるかもしれないが、これはあくまで限界まで働いた場合、つまり自分のための余暇の時間は全くなく、そして健康を損ねかねないほどハードに働いた場合の数字、ってことだ。
ベンチャー企業は魔法じゃない。富の生成の法則を変えることはできない。曲線の一番端の店を表現しているにすぎないんだ。ここにも保存則が適用される。1億円儲けたければ、1億円分の苦労をしなくちゃならない。例えば郵便局に一生勤めて、給料の最後の1セントまでをこつこつ貯金すれば、1億円貯めることはできるだろう。そうやって50年間、郵便局に勤めるストレスを想像してほしい。ベンチャー企業では、同じ量のストレスが3〜4年間に圧縮されてやってくるんだ。まとめ買いによる割引がきく場合もあるが、根本的な保存則を変えることはできない。ベンチャー企業を立ち上げることが簡単なら、みんなやってるはずだろう?
億万長者ではなく、百万長者
年俸3億円は、人によってはとても多く思えるだろうが、そうでもないと思う人もいるだろう。たった3億だって? それより、どうやったらビル・ゲイツみたいに、何千億もの財産を作ることができるんだ?
とりあえずビル・ゲイツは置いておこう。有名で裕福な人物を例として使うのは良くない。というのも、メディアはなかでも一番裕福な人々についてしか書かないし、そういう人々は例外点であることが多いからだ。確かに、ビル・ゲイツは明晰な頭脳と強固な意思を持ち、ハードに働く人間だが、それだけで彼ほどの財を築けるわけではない。恐ろしいほどの幸運というものも必要なんだ。
どんな会社の成功にも、大きなランダム要素が絡んでくる。だからメディアで報道されるような成功者は、明晰な頭脳と強固な意思、それに宝くじに当たるような幸運を併せ持った人なんだ。マイクロソフトが大きな利益を上げることができたのは、ビル・ゲイツが明晰な頭脳と強固な意思を持ち、取引相手がビジネス史上稀に見る大失策を犯したからだ。DOSのライセンス契約だ。もちろんビル・ゲイツは総力をあげてIBMがその失策をするように仕向けただろうし、それを利用するに当たっても素晴らしい仕事をしたが、もしIBM側に一人でも頭脳を持った人間がいたなら、マイクロソフトの将来は全く違ったものになっていただろう。マイクロソフトはあの時点ではIBMに対してさしたる影響力を持っていなかった。実質的に、部品の供給業者にすぎなかったんだ。もしIBMがそうすべきだったように独占契約を要求していたとしても、マイクロソフトはそれを飲んでいただろう。そうだったとしても当時の彼らにとっては大金だったし、IBMはその気になれば他からオペレーティング・システムを探してくることだってできたのだから。
だがIBMは結局、市場に持てる力をすべて使って、マイクロソフトにPCにの標準を握らせてしまった。マイクロソフトは、そこからはただ実行するだけでよかった。企業を賭けた難しい決断を迫られることはなかった。ライセンス先の企業から取れるだけ取り、最新の技術を十分に速くコピーしてさえいればよかった。
IBMがこの過ちを犯していなくても、マイクロソフトはまあまあ成功した企業になっていただろうが、こんなに速く大きくはなっていなかっただろう。ビル・ゲイツは裕福になっていただろうけれど、たぶんForbes 400の下の方に、同年代の起業家と一緒に並んでいたんじゃないかと思う。
裕福になるには実に色々な方法があるが、このエッセイで扱うのはそのうちひとつだけだ。このエッセイでは、富を創り、その対価を得ることで金を儲けることについて扱う。金を手に入れる方法はほかにいくらでもある。偶然、投機、結婚、相続、窃盗、強奪、詐欺、独占、汚職、癒着、贋札、探鉱、などなど。最大の財産のいくつかは、おそらくこれらのうちの数種類がかかわっているんじゃないかと思う。
このうちで、富を生むことで裕福になる方法は、単により合法的というだけじゃない(他の方法の多くは現代では非合法だ)。より直接的だ。人が望むことをするだけでいいのだ。
お金は富ではない
富を築き上げようと思ったら、まずそれが何かを理解することが役に立つ。富はお金と同義ではない。
最近まで、政府でさえ貨幣と富の違いを把握していないことがあった。アダム・スミスは『国富論』で、「富」を保存するために金銀の輸出を禁じた国家について述べている。変換媒体をたくさん持つだけでは、国は豊かにならないのに。同じ量の富に対してより多くの貨幣があれば、単に価格が上がるだけだ。
富は、人類の歴史と同じくらい古くからある、いや、それより古くからあると言ってもよいだろう。蟻だって富を持っている。お金(貨幣)は比較的最近発明されたものだ。
富はもっと根本的なものだ。富とは、わたしたちが欲しがるもの、食物、衣服、住居、車、道具、観光地への旅行、そういったものだ。お金を持っていなくても富を持つことはできる。例えば、車を作れだとか夕食を料理してくれだとか洗濯をしてくれだとか、何でも命令すればやってくれる魔法の機械があったとしたら、もうお金はいらないだろう。一方、南極大陸のど真ん中、何も買い物ができない場所にいるとしたら、いくらお金を持っていても無意味だ。
富こそが欲しいものであって、お金ではない。でも富がそんなに重要なら、どうしてみんな金を儲けることについて話しているんだろう。それは一種の省略記法なんだ。お金は富を移動する方法のひとつで、現実では普通、富と交換可能だ。しかし両者は違うものだ。「お金を作る」ことについて話すのは、ニセ札作りでもしようというのでなければ、むしろ実際に裕福になる方法を理解する妨げになる。
お金は専門化の副作用だ。専門家された社会では、人が必要とする多くのものを自分で創り出すことはできない。じゃがいもや、鉛筆や、住む所が欲しければ、普通はそれを誰かからもらわなければならない。
じゃがいもを作っている人から、いくらか分けてもらうにはどうすればいいだろう。その人が欲しがるものを代わりにあげればいい。でも互いに欲しがるものを直接交換しているだけでは、まだ不便なことこの上ない。例えばあなたがバイオリンを作っていて、近所の農家の人は誰もそれは欲しがらなかったとしたら、どうやって食べていける?
社会がより専門化してゆく過程で発明された魔法は、交換を2段階にするというものだった。バイオリンを直接じゃがいもと交換する代わりに、それを例えば銀と交換する。そしてその銀を必要な他のものとまた交換する。この中間に使われるもの、交換媒体は、希少で持ち運びができるものなら何でもよい。歴史的には金属が広く使われてきたが、近年、わたしたちは実際に物理的に存在しない「お金(円、ドル、etc.)」という交換媒体を使うようになった。それは物理的に存在しないが交換媒体として利用できる。政府がその希少性を保証しているからだ。
交換媒体の利点は、それにより交易が可能になるというものだ。しかし交易の本当の意味が分かりにくくなるという欠点もある。人々はビジネスというものはお金を儲けることだと思い始めた。だが、お金は欲しいものを手に入れるための単なる中間段階、省略記法にすぎない。ほとんどのビジネスがやっていることは富を生み出すことだ。人々が欲しがることをやるんだ。
「富」という言葉にはさまざまな意味があり、物質的なものだけを意味するわけではない。わたしはここで、何が本当の富なのかについての深い哲学的な考察をするつもりはない。むしろ、「富」という単語を、特定の技術的な意味で使っている。人々が貨幣と交換したがるもの、という意味だ。この種の富は研究してみる価値がある。餓死しなくても済むからだ。そして、人々があなたに貨幣をくれるのは、あなたにではなく、富に対してなのだ。ビジネスを始めるとき、あなたのやっていることを顧客が欲しているという考えに堕ちてしまうのはたやすい。インターネット・バブルの頃に、単に自分がアウトドアが好きだというだけで「アウトドアポータル」を始めようとしていた女性と話したことがある。アウトドアが好きなら、どういうビジネスを始めたらいいか。クラッシュしたハードディスクからデータを復旧するサービスだ。
どういう関連があるのかって? 何もない。それが言いたいことだ。富を(餓死しないため、という狭い技術的な意味で)創り出したいのなら、自分が好きなことを中心にした計画に対しては特に疑ってかからねばならない。その分野では、何が価値があるかというあなたの判断は、他の人々と大きくずれていることが多いからだ。
パイの誤り
驚くほど多くの人々が、子供の頃持った、世界には限られた富しかないという考えを持ち続けている。普通の家庭のある時点では、確かに限られたお金しかない。でもそれは同じことじゃない。
そういう文脈で富が語られるとき、それはよくパイに例えられる。政治家はよく、「パイを大きくすることはできない」と言う。ある家族の銀行口座にあるお金とか、政府の年間の税収とかについての話ならば、それは真実だ。誰かが余計に取ればその分誰かが損をすることになる。
わたしも子供のころ、もし少数の裕福な人々が全部のお金を取っちゃったら、他の皆には少ししか残されないじゃないかと思ったのを覚えている。どうも大人になってもこのことを信じている人が多いようだ。人口のx%がy%の富を所有している、といった議論の背景には、たいていこの誤りがある。もしあなたがベンチャー企業を立ち上げようとしているなら、自覚の有無にかかわらず、このパイの誤りを証明しようとしていることになる。
人々が間違える理由は、お金による抽象化だ。お金は富ではない。富を移動する手段にすぎないんだ。だから、ある時点(例えば今月の家計)に決まった量のお金しかほかのものと交換するのに使えないからといって、世界中に決まった量の富しか無いということにはならない。富は創り出すことができる。人類の歴史のどの時点でも、富は生み出されたり、消滅したりして(だが、トータルとしては創り出されて)きた。
例えばあなたがポンコツの古い車を持っているとしよう。次の夏休みにぼさっとしている代わりに、その車を修理して元の状態に戻したとしよう。そうすることであなたは富を創り出している。世界は、そしてとりわけあなたは、ひとつのクラシックカーの分だけ裕福になったわけだ。これは比喩的な意味ではない。あなたがその車を売ることを考えれば、より多くの金を受け取ることができるだろう。
古い車を修理することであなたは自分を裕福にできた。でも他の人に損をさせてはいない。だから、決まった大きさのパイなんか明らかに存在しないんだ。実際、一度こういうふうに考えてみれば、いったいどうして他の人が決まったパイなんて考えるのか、不思議にならないだろうか。
普通の車を修理することで、他の皆は微視的には貧しくなるかもしれない。環境への少々のダメージがあるからだ。環境のコストは計算に入れなければならないが、そうしたところで富を創ることがゼロサムゲームになるわけじゃない。例えば、ねじが緩んでいただけの機械を直したとしたら、環境への影響無しで富を創り出したことになる。
子供は、自覚こそしていないが、自分が富を創り出せることを知っている。誰かにプレゼントをあげたくて、でもお金がないとき、自分で何かを作るだろう。ただ子供は何かを作るのがあまり上手ではないから、自家製のプレゼントは店で売っているものとは違う、何か劣ったもののように思ってしまうんだ。そこに込められた気持ちが大事なんだとか何とかね。確かに、両親のために作った不格好なマグカップは、店で売ったって大した金にならないだろう。
職人
富が創り出されるものだということに気付きやすいのは、ものを作るのが上手な人々、職人だ。職人の手作りの作品は、店で売られるものになる。だが、工業化が進むにつれ、ものを作る職人はどんどん少なくなってきた。現存するなかで最も大きいグループのひとつが、コンピュータプログラマだ。
プログラマはコンピュータの前に座って富を創り出すことができる。良いソフトウェアはそれだけで価値のあるものだ。問題を複雑にする製造工程なんてものはない。プログラマが打ち込む一文字一文字が完全な製品を構成するんだ。例えばどこかのプログラマが軽快なWebブラウザを書いたとしたら、世界はその分だけ裕福になる。
会社の中では、全員が協力して人々が欲しがるものを作るという意味で、富を創り出している。しかし従業員の多くは(例えば郵便物の仕分けとか人事部などは)実際にものを作る場所からは1ステップ離れている。プログラマはそうではない。プログラマは文字通り、製品を頭のなかから一行一行紡ぎ出す。したがってプログラマにとっては、富は仮想的なお父さんが切り分けてくれるパイなんかではなく、創り出されるものだということはより明白だ。
また、プログラマにとっては、富が作られるペースには非常に大きな差があるということも明白だろう。某社には生産性の鬼のようなプログラマがいた。ある長い一日に彼がした仕事を見ていて、彼は会社の市場価値を数十万ドル増やしたと感じた。凄腕のプログラマは半月で1億円相当の仕事をすることだってできるだろう。平凡なプログラマは同じ期間で、ゼロどころかマイナスの富を創ることだってある(バグを入れるからね)。
これが、良いプログラマの多くがリバタリアンであることの理由だろう。
リバタリアン(liberterian)とは、個人の自由を最大限尊重し、政府が個人の自由に介入することを最小限にとどめるべきとするリバタリアニズムを支持する人々のこと。
プログラマの世界は泳ぐか沈むかで、言い訳は通用しない。富が創り出される現場からはるかに離れた所にいる人々、例えば学生や記者、政治家たちは、最も富める5%の人々が全世界の富の半分を所有していると聞いて「不当だ!」と考える。経験豊かなプログラマはむしろ「それだけ?」と思うだろう。たぶん最も優秀な5%のプログラマが、世の中の良いソフトウェアの99%を書いているんじゃないだろうか。
創られた富は、必ずしも売られる必要はない。少なくとも近年まで、科学者は創り出した富を実質的に寄付してきた。ペニシリンを知ることで私たちは豊かになった。感染から死ぬ危険が減ったからだ。富は人々が欲しがるもので、死なないことは確かにわたしたちが欲することだ。ハッカーはしばしば、オープンソースソフトウェアとして誰もが無料で使えるようにすることで、自分の仕事を寄付している。わたしはFreeBSDを使うことでとても豊かになった。
仕事とは何か
産業化の進んだ国では、人々は20歳代になるまで何かの組織に所属して過ごす。それだけの年月を過ごせば、人は、何かのグループに所属して、一緒に朝から同じ建物に行き、普通は面白くもないことをやらねばならないものだ、という考えに慣れてしまう。組織に所属することが自分のアイデンティティにさえなる。氏名、年齢、役職と所属、というわけだ。自己紹介するときや、誰かに紹介されるときには、こんなふうになる。ジョン・スミス、10歳、どこそこ小学校の生徒です。あるいは、ジョン・スミス、20歳、どこそこ大学の学生です、とね。
このジョン・スミス氏が学校を卒業した。彼は就職することになる。すると、就職するということが、まるでもうひとつの組織に所属することのように思えてしまう。表面的にはそれは大学と似ている。自分が働きたい企業を選んでそこに応募する。気に入られればその新しいグループのメンバーになる。皆と一緒に朝から同じ建物に行って、普通は面白くもないことをやらされる。違いも少しはある。暮らしは学生の時ほど楽しくなくなるけど、授業料を払う代わりに給料を貰えるんだ。でも違いよりも類似点のほうがどうやら多いようだ。ジョン・スミス氏はいまや、ジョン・スミス、22歳、どこそこ会社のプログラマです、となったわけだ。
実はジョン・スミス氏の人生には、彼が気付いている以上に大きな変化が起きたんだ。社会的に、会社は大学と同じように見えるかもしれないが、より深い現実へと入ってゆけば違いのほうが目についてくる。
会社がやっていること、そして存続してゆくためにやらねばならないことは、金を稼ぐことだ。そしてほとんどの会社が金を稼ぐ方法は、富を創り出すことによってだ。会社はそれぞれ非常に専門化しているので、この共通項は見え難くなっているけれど、製造業だけが富を創り出しているんじゃない。例えば富の大きな要素は場所だ。前に挙げた、車や夕食を作ってくれる魔法の機械の例を覚えているだろうか。あの機械が作った夕食を中央アジアのランダムな場所に届けるようになっていたら、あまり使い道がないだろう。富が人々の欲しがるものなら、ものを移動する会社だって富を創り出している。物理的なものを造っていない他の様々な会社だって同様だ。ほとんどすべての会社は、人々が欲することをやるために存在している。
そしてあなたが会社で働いていれば、それはあなたがやることでもある。でも会社では、別の層が下にある現実を隠してしまいがちだ。会社では、あなたがやる仕事は他の多くの人がやることと平均化されてしまうんだ。他人が欲することをやっているんだ、ということに自分では気づかないかもしれない。あなたの貢献は間接的かもしれない。でも会社全体としては、誰かが欲するものを提供していない限り、利益を上げることはできない。会社があなたに年俸をx万円払っているとすれば、あなたは少なくとも平均して年にx万円以上の貢献をしているはずだ。でなければ会社は稼ぐよりも多くのお金を使うことになり、潰れてしまうからね。
大学を卒業しようとしている学生は、就職しなくちゃならないと周りから言われるし、自分でもそう考える。まるで組織のメンバーになることが重要であるかのように。でももっと直接的に言えば、人々が欲することを始めることが必要なんだ。そのために会社に所属する必要はない。会社とは、人々が集まって他の人々が欲することをやる集団にすぎない。人々が欲することをすることが重要なのであって、集団に属することは問題じゃない。
20代初めに、混乱して落ち込んでる人は多い。大学はあんなに面白かったのに。もちろんそうだったろうさ。表面的な類似性に騙されちゃいけない。ゲストから召使いになったわけだからね。この新しい世界で楽しむことだってできる。そのうちのひとつは、「関係者以外立入禁止」のドアの中に入れることだ。でも、この変化は最初は衝撃的だろう。特にその変化を意識しないでいるうちは。
たいていの人々にとっては、既にある会社に就職して働くことが最良のプランだろう。それでも、そうすることで本当は何をしているのかを理解しておくことは重要だ。仕事とは、会社の他の人々と一緒に平均化されつつ、人々が欲することをなすことだ。
もっと頑張って働く
問題なのはこの平均化の部分だ。大企業における唯一にして最大の問題は、各人の仕事の価値を測ることの困難さだと思う。たいていの場合、彼らは賭けに出る。大企業では、従業員にそこそこ予測可能な給料を支払い、そこそこ頑張って働くことを期待するんだ。従業員は、明白に仕事ができなかったり怠けたりするのは困るが、全人生を仕事に賭けることも期待されていない。
しかし生活のどれだけの部分を仕事に捧げられるかに関しては、規模の経済が成り立つ。ビジネスの種類によっては、本当に仕事に打ち込めば、平均的な社員の10倍どころか100倍もの富を生み出すことさえできる。例えばプログラマは、既存のソフトウェアを保守したり改良したりして時間を潰す代わりに、全く新しいソフトウェアを書いて新しい利益の源を創り出すことだってできる。
会社はそういうことをしたい人のためにはできていない。上司のところに行って、明日から10倍働くので給料を10倍にしてくださいとは言えない。そもそも表向きはあなたは既に可能な限り頑張って働いていることになっている。
だがより重大な問題は、会社はあなたの仕事の価値を測る手段を持っていないということなんだ。
セールスマンは例外だ。彼らがどれだけの利益を産んでいるかは簡単に測れるし、従ってそれに比例した給料を受け取るようになっていることが多い。セールスマンがもっとたくさん働きたいと思えば、ただそうすればいいし、それに従った給料を自動的に貰えるだろう。
営業部門以外にもうひとつ、大企業が一級の人々を雇える職種がある。最高管理職だ。そしてそれもまた同じ理由による。彼らの成績は測ることができるからだ。最高管理職は会社全体の利益に責任を負う。普通の従業員は仕事の成果を測られないから、「ちゃんと仕事する」以上のことは求められない。しかし最高責任者はセールスマンと同様、数字を出さなければならない。傾いた会社のCEOは「ちゃんと頑張ったんです」と言ったって駄目だ。会社の利益が上がらなければ、彼は仕事をうまくやれなかったということだ。
会社がすべての従業員に仕事量通りの給料を支払えれば、その会社はおそろしく成功するだろう。仕事した分だけ給料が貰えるというなれば、多くの従業員は頑張って働くはずだ。さらに重要なのは、そういう会社が特に頑張って働きたい人を惹き付けることだ。競争相手は打ち負かされるだろう。
残念ながら、会社は全員にセールスマンのように支払うことはできない。セールスマン一人で行動するが、多くの従業員は一緒になって仕事をする。例えば一般向けの便利な小型機器を造っている会社を考えてみよう。エンジニアは、頑丈でいろいろ新しい機能がついた機器を製造する。工業デザイナーが、素敵な外観をデザインする。そしてマーケティング部門が、消費者に、これは必須のアイテムだと信じさせる。この製品の売上のうち、各グループの努力がどのくらいを占めるのかというのをどう測ればいいだろう。さらに、その会社のそれまでの製品によって培われた評判も考え合わせると、過去の製品の作成者の貢献だってある。これらの要素を解きほぐす方法なんてない。たとえ消費者の思考が読めたとしたって、いろいろな要素は曖昧に交じり合って判然としないだろう。
速く仕事をしたいと思ったら、多人数と一緒に何かやるのは問題になる。大きな集団では個人の成果は分離して測ることはできない。そして、速く行こうとする人の足を他のメンバーが引っ張るのだ。
測定と挺子
裕福になるためには、2つの環境を整えなければならない。測定と梃子だ。まず、自分の生産性が測れる地位に就かなければならない。でないと頑張っただけ支払ってもらえないからだ。また、梃子が必要だ。すなわち、あなたの決定が大きな効果を持つようにすることだ。
測定だけでは十分ではない。測定があって梃子がない職種とは、例えば向上での歩合制の単純作業だ。仕事ぶりは測定されて、それに見合った給料が支払われるが、決断することはほとんど何もない。唯一決められることはどれだけの仕事を自分でするかだが、それだけでは頑張ってもせいぜい収入を2倍か3倍にするだけだろう。
測定と梃子が両方ある仕事の例は、映画俳優だ。仕事ぶりは映画の興行収入で測られる。そして、自分の演技で映画の成功を左右できるという意味で、梃子を手にしている。
CEOもまた、測定と梃子を持っている。会社の成績が自分の成績になるという意味でも測られるし、自分の決断によって会社すべての方向が決まるという意味で梃子を持っている。
自分の努力によって裕福になった人々は誰もが、測定と梃子のある環境にいたのだと思う。わたしが思いつく全ての人はそうだ。CEO、映画スター、お笑い芸人、ヘッジファンドのマネージャー、プロスポーツ選手。梃子の存在を知る良いヒントは、リスクの可能性だ。良いことは悪いこととバランスしていなければならない。大きな利益を得られる可能性がある場所には、常に恐ろしいリスクの危険も潜んでいる。CEO、スター、ファンドマネージャ、スポーツ選手は常に、自分の頭上に剣が吊るされているような人生を送っている。一度でも失敗すればそれで終わりだ。安心できるような仕事に就いている限り、裕福になれる可能性はないだろう。リスクのない場所には、まず梃子が存在しないからだ。
でも、測定と梃子を手に入れるために、CEOや映画スターになる必要はない。難しい問題に取り組む小さな集団に参加すればいいんだ。
小ささ=測定
従業員一人一人の仕事の価値は測れないとしても、近いことはできる。小さなグループによる仕事の価値は測れるのだ。
会社全体のレベルでは、従業員たちの生み出した利益を正確に測れる。したがって、会社が小さければ、各人の貢献を測ることに近いところまで行ける。元気なベンチャー企業は10人くらいしか従業員がいないかもしれないが、それは各人の努力が、10倍くらいの係数の範囲で測れるということを意味する。
ベンチャー企業を興したり参加したりすることは、多くの人々にとっては、ちょうど上司に10倍働くので10倍給料をくれということに一番近い方法だろう。ただ、2つの違いがある。まず、それを言う相手は上司ではなく直接の顧客であるということ(結局、上司というのは顧客の代理でしかない)。それに、自分ひとりでそう言うのではなく、少数の野心的な仲間と一緒にやるってことだ。
通常、それはグループになるだろう。俳優とか小説家のような例外的な仕事を除いては、会社を一人で運営しちゅくことはできない。そして、一緒に何かをしようという人は優秀でなければならない。だって自分の仕事は彼らの仕事と平均を取られるわけだから。
大企業は1,000人の漕ぎ手がいる巨大なガレー船のようなものだ。この船が遅くなる理由が2つある。まず、個々の漕ぎ手が自分の努力の結果を見ることができないこと。そして、1,000人も人がいれば、平均的な漕ぎ手というのは文字通り平均的である可能性が高いことだ。
その船からランダムに10人の漕ぎ手を選んで別の船に乗せれば、たぶんその船より速く進むだろう。目の前のニンジンがぶら下がっているからだ。力が余っている漕ぎ手は、自分の努力次第で船のスピードを上げられると知ればやる気を出すだろう。そして誰かが怠けていたら他の人は気付いて文句を言うだろう。
だがこの10人の船が本当に力を発揮するのは、巨大なガレー船の漕ぎ手のうち最も優秀な10人を選んで乗せたときだ。もちろん彼らは小さなグループにいることによってさらにやる気を出すだろうが、より重要なのは、小さなグループを選ぶことにより優秀な人物を選べるということだ。トップ1%に入る漕ぎ手で構成できるんだ。全員で平均を取るより少数精鋭で平均をとったほうがいいに決まっている。
これが、ベンチャー企業の本当の意味だ。理想的には、大企業でやるよりずっとたくさん働いて、ずっとたくさん給料をもらいたいという集団を集めることができる。しかも多くの場合、ベンチャー企業の創立者たちは、お互い既に知っている(か、少なくとも評判を聞いている)、野心的で自分から何かをしようとする集団になるから、ただの小集団よりもずっと測定は正確になる。ベンチャー企業とはただ10人集まっただけじゃない。10人はあなたのような人物が集まった集団なんだ。
スティーブ・ジョブズは、ベンチャー企業の成功と失敗は最初の10人の従業員で決まると言ったことがある。わたしもそれに同意する。もし言い換えられるなら、最初の5人と言ってもいいだろう。ベンチャー企業をすごい場所にするのは、ただ小さくあるだけじゃなくて、選り抜かれた小さい集団であることだ。村のような意味で小さい集団でなく、オールスターチームのような集団が必要なんだ。
集団が大きくなればなるほどその平均は人口全体の平均に近づいてゆく。したがって、他の条件がすべて同じなら、大企業にいる非常に能力の高い人は損をしていることになる。その人の成果は他のより低い成果に足を引きずられてしまうからだ。もちろん他の条件はいつも同じではない。お金を儲けることに関心がない人だっているし、大企業の安定性を重視する人だっている。だが、お金に関心があり、かつ能力のある人は、同じような仲間との小さな集団で働くほうがよいだろう。
技術=梃子
ベンチャー企業は測定と梃子のある環境を提供してくれる。小さいことで測定が可能になり、新しい技術を発明してお金を儲けることが梃子になる。
技術とはなんだろうか。それは手法だ。何かを行う際の手法だ。新しい方法で何かをやれることを見つけたとすれば、他の皆が同じ方法を使うことで、その価値は人数分増えることになる。よく言われるように、それは魚ではなく釣り竿だ。ベンチャー企業がレストランや美容室と違うのはそこだ。そういう店では、一個ずつ卵を炒めたり、一人ずつお客の髪の毛を切る。しかし、多くの人々が関心を持つ技術上の問題を解けば、その解法を使うすべての人を助けられる。これが梃子だ。
歴史を見てみれば、富を創ることで裕福になった人々の多くは、新しい技術を創ることでそうしたと分かるだろう。卵を素早く炒めたり髪を素早く切るだけでは不十分なんだ。1200年のフィレンツェを裕福にしたのは、当時のハイテク製品である毛織物を生産する新しい手法だった。1600年のオランダを裕福にしたのは新しい造船技術と航海術で、それにより彼らは極東までの航路を一手に収めた。
幸いなことに、小さな集団は困難な問題を解くことに適している。技術の最先端は非常に速く動いている。今日価値のある技術でも、2年後には価値がなくなっているかもしれない。小さな会社はこのような世界を心地よく感じる。動きを止める、層になった官僚的なシステムを持たないからだ。また、技術の進歩はしばしば突拍子もない挑戦から生まれるが、小さな会社はそこでも伝統に縛られないという利点がある。
大企業も技術を開発することはできる。ただそれを素早く行うことはできない。その大きさのために、進行は遅くなり、並々ならぬ努力を求められた従業員に報いることが難しくなる。結局、大企業が技術を開発するのは、多大な投資が必要なためにベンチャー企業が参入しにくい分野に限られる。マイクロプロセッサ、発電所、あるいは旅客機といったものだ。しかもこれらの分野でさえ、個々の要素技術やアイディアはベンチャー企業に負うことが多い。
バイオテクノロジーやソフトウェアで困難な技術的問題を解くベンチャー企業が出てくるのは当然だが、この原理は技術とは一見関係ないビジネスでも正しいと思う。例えばマクドナルドは、フランチャイズというシステムを設計し、それを世界中にコピーすることで大きくなった。マクドナルドのフランチャイズは非常に綿密な規則により制御されていて、まるでソフトウェアみたいだ。「一度書けばどこでも走る」(Write once, run everywhere)というやつだ。ウォルマートも同じだ。サム・ウォルトンは小売店をやることで裕福になったんじゃない。新しい種類の店を設計することでそうなったんだ。
困難な問題を選ぶというのは、最初に会社の目標を選ぶときに役立つだけじゃない。業務の中で決断を下さなければならないときの指針にもなる。某社での第一の規則は「階段を駆け上がれ」だった。あなたが小さく非力で、巨大で太ったいじめっ子に追いかけられているとしたら、上へ逃げる? それとも下へ逃げる? わたしは上を選ぶ。いじめっ子はたぶんあなたと同じくらい速く階段を駆け下りられるだろう。でも駆け上がるとき、いじめっ子の体重は負荷になる。もちろんあなただって駆け上がるのは苦しい。でも相手の方がもっと苦しいんだ。
現実の場面でこのたとえが意味するのは、わたしたちは意識して難しい問題を探したということだ。もしわたしたちがソフトウェアに追加すべき機能を2つのうちから選ばなくてはならなくて、どちらもその困難度に比例した価値があったとしたら、常に難しいほうを選んだ。そちらのほうが価値が高いというだけでなく、そちらのほうが難しいという理由身体。それによって、より大きく動きの遅い競争相手が、より困難な土俵でわたしたちを追いかけるのに苦労しているのを見て喜んだものだ。ベンチャー企業は、ゲリラのように、中央政府軍が追ってこられないような険しい山岳地帯を好む。わたしは、おそろしく困難な技術上の課題にまる一日がかりで皆で取り組み、精も根も尽き果ててしまったときのことを覚えている。それでもわたしは嬉しかった。わたしたちがこれだけ苦労するような問題なら、きっと競争相手は誰も解決できないだろうと思ったからだ。
これは、ベンチャー企業を経営していくのに良い方法というだけじゃない。そもそもこういうことをするのがベンチャー企業だ。ベンチャーキャピタリストはもちろんこのことを知っていて、それに対する用語まである。「参入障壁」だ。あなたが新しいアイディアを思いついてベンチャーキャピタルに投資をもちかけたとしたら、最初に尋ねられるのはそれを他の誰かが作るのはどれだけ難しいか、ということだ。言い換えれば、あなたと他の追跡者との間にどれだけ困難な領域が確保してあるか、だ。
ベンチャーキャピタルに、別のベンチャー企業がわたしたちのソフトウェアと同等のものを作るのにどれくらいかかるかを尋ねられたときには、きっと他の人は作れないでしょうと答えていたものだ。ずいぶんものを知らないか、嘘つきだと思われていたに違いない。
そして、あなたはその技術を他で作るのがどれだけ困難かという、説得力のある説明を用意しておかなければならない。でなければ、大会社はそのアイディアを見た途端に自分で同じものを作り、大会社のブランド名、資本、販売チャネルを使って、あなたの市場を一夜にして奪ってしまうだろう。まさに、正規軍に平原の真ん中で捕まるゲリラみたいなものだ。
参入障壁を作るひとつの方法は特許によるものだ。しかし、特許は大した障壁にはならないかもしれない。競争相手はうまく特許を回避する方法を見つけるからだ。たとえそれができなくても、わざと特許を侵害して裁判に持ち込む戦術を取るかもしれない。大会社は訴えられることを恐れない。日常的なことだからだ。彼らは確実に裁判を長期化させ、こちらは莫大な費用を払わされることになる。フィロー・ファーンズワースの話は聞いたことがあるだろうか。彼はテレビを発明した。彼の会社の名前など普通の人は知らないだろうが、それは彼の会社がテレビでお金を儲けることがなかったからだ。
一人の発明者がはっきりしている技術はほとんどない。だから、何か(電話でも、流れ作業でも、飛行機でも、電球でも、トランジスタでも)の「発明者」をあなたが知っているとすれば、それは彼らの会社がそれで金を儲けて、その広告部門が話を広めたからにほかならない。何か(自動車、テレビ、コンピュータ、ジェットエンジン、レーザー)の発明者をあなたが知らないとすれば、それは他の会社がそれで儲けたからだ。
テレビで金を儲けたのはRCAであり、ファーンズワースが得た見返りといえば、十年にもわたる特許裁判の苦労だけだった。
ここでも、攻撃こそが最大の防御になる。競争相手が真似するのが難しすぎるような技術を作りさえすれば、他の防御に頼る必要はない。難しい問題を選ぶことから始め、決断が必要な場面では常に難しいほうを選べばよい。
これは人生においても、一般的に良い方法だ。2つの選択肢がある場合、難しいほうを選べ。ジョギングに行くか、座ってテレビを見るか迷ったら、ジョギングに行け。このルールがとてもうまくいくのは、おそらく、選択肢があって一方が難しいという場合、たぶんあなたの怠惰さがもう一方の選択肢を持ち出したに違いないからだ。心の底では、何をすべきかを知っているんだ。このルールに従えば、それを自分で認めることになる。
落とし穴
普通の会社員をやっているより頑張って働けばそれに比した給料がもらえるというだけなら、ベンチャーを立ち上げるのは何の損もないことだ。それだけなら、ベンチャーのほうが面白いだろうし。多くの人は、大企業のゆっくりとしたペース、いつ終わるとも知れない会議、休憩室でのおしゃべり、物分りの悪い中間管理職とかいったものにうんざりしてているんじゃないかと思う。
残念ながらここには落とし穴も2つばかりある。ひとつは、曲線上のどの点に留まるかを自分が選ぶことができないということだ。例えば、どれくらい働きたいのかを自分で決めることはできない。だいたい2倍から3倍働いてその分給料を貰いたいな、というわけにはいかない。ベンチャーを立ち上げたら、競争相手があなたがどれだけ働かなくちゃならないかを決めることになるんだ。そしてどの会社も同じような結論へと向かう。つまり、可能な限り頑張るってことだ。もうひとつの落とし穴は、自分の生産性に比例した見返りというのは平均値にすぎないということだ。先に述べたように、どんな会社の成功にも大きくランダムな係数がかかってくる。したがって現実は、30倍働いたから30倍貰えるということにはならない。あなたが30倍働いたとしたら、貰える額はおそらくゼロから1000倍のどこかになるだろう。そして、平均値が30倍だとしても中央値はたぶんゼロだ。多くのベンチャー企業は生き残れない。インターネットバブルのころによく目にしたドッグフードのポータルのようなものだけじゃない。本当に良い製品を作っているのに、少し長くかかりすぎただけで、資本を使い果たし潰れてしまうベンチャー企業は珍しくはない。
ベンチャー企業は蚊みたいなものだ。熊なら叩かれてもけろっとしているだろうし、蟹なら叩かれても固い甲羅で身を守れるが、蚊はただひとつのことのために作られている。刺すことだ。防御に対しては一切エネルギーが使われていない。種としては、蚊はたくさんいることが防御となっているが、それは一匹一匹の蚊にとってはあまり慰めにはならないだろう。
ベンチャー企業は、蚊と同じように、オール・オア・ナッシングの立場に立つことが多い。そして最後の瞬間までどちらに転ぶかは分からないものだ。過去の経験でも何度も危ない場面があった。わたしたちの軌跡はまるでサイン曲線のようなものだった。幸いにして曲線の頂点で買収されることができた企業も、本当にギリギリであるということが珍しくない。
この、のるかそるかという状態は、決して嬉しいものじゃない。少なくないハッカーたちはリスクを回避したがる。ものすごく働いてそれに見合うものをもらうだけでいい方法、くじの要素が入ってこない方法があるなら、狂喜することだろう。20%のチャンスで10億円を得るよりも、100%のチャンスで1億円を得ることができれば、理論的には前者のほうが2倍期待値が高いとしても、後者を選ぶかもしれない。残念ながら、現在のビジネスの世界のどこを探しても後者のような方法は存在しない。
できることと言えば、ベンチャー企業をなるべく早い段階で売ってしまい、得られたかもしれない巨大な利益(とリスク)の代わりに、保証された小さな見返りを得ることだろう。
買収を擦るような企業は、安い買い物を探しているわけではない。ベンチャーを買収できる規模の企業というのは、通常は保守的にならざるを得ないくらい大規模で、しかも買収の責任者となるような人は中でも最も保守的な、ビジネススクールを出て後からその会社に就職したような人であることが多い。安全な選択ができるなら払いすぎてもよいとさえ考える人々だ。だから、初期のベンチャー企業よりは、たとえ金額が大きくても、既に確立したベンチャー企業を売る方が易しいのだ。
ユーザを獲得すること
可能なら、買収されることは悪いことではないと思う。企業を継続して経営してゆくことは、育てることとは違う。巡航高度に達したら大企業に後を任せるのがよいだろう。またそれは財政的にも有利だ。売ることでリスクを分散できる。ファイナンシャルアドバイザーが、顧客の資産を不安定な株1銘柄にすべて突っ込んだらどう思う?
どうやったら買収してもらえるだろう。やることは、買収を目標にしない場合とたいして変わりはしない。例えば利益を出すとか。でも、買収されることにはそれ特有の技術というものがあり、マスターするのに長い時間がかかる。
買い取ってくれそうな会社は、可能ならいつだって決断を遅らせようとする。買い取られるに当たって難しいのは、彼らの腰を上げさせることだ。多くの人々にとって一番強い動機付けは、利益への期待ではない、損失への恐れだ。買取会社候補にとっての一番の動機付けは、彼らの競争相手が買ってしまうかもしれないという恐れだ。これがあるからCEOは深夜のフライトに飛び乗って来る。二番目の心配は、もし今のうちに買っておかなければもっと急速にあなたの会社が大きくなって、後で買うにはもっとずっと金がかかるか、下手をすると競争相手にさえなるかもしれないと思わせることだ。
どちらの場合でも一番大事なところは、結局ユーザに行き着く。ベンチャー企業を買収しようなんて会社は、たくさんの調査をしてターゲットの技術がどれくらい価値があるかを決めようとする、と思うかもしれない。全然そんなことはない。彼らが聞くのは、あなたが持っているユーザ数だ。
実質的に、買収しようとしている企業は、顧客こそが一番の技術を知っていると仮定していることになる。これはそれほどおかしな考えではない。ユーザはあなたが富を創り出したことの唯一の現実的な証明だからだ。富は人々が欲しがるものであり、人々があなたのソフトウェアを使っていないのなら、それはマーケティングが下手なだけじゃないかもしれない。それは、あなたが作ったものは人々が欲しがるものではなかったということなのかもしれないのだ。
ベンチャーキャピタルは、注意すべき危険信号のリストを持っている。トップ近くにあるのは、ユーザを幸せにすることより面白い技術的問題を解くことのみに夢中な、技術馬鹿によって会社が経営されている場合だ。ベンチャー企業は単に問題を解くだけじゃいけない。ユーザが解いてほしいと思っている問題を解くべきだ。
したがって、買収しようとしている企業と同じように、あなたもユーザを指標とするべきだと思う。ベンチャー企業を最適化の問題と考えてみよう。その性能がユーザ数で測られるものとするのだ。ソフトウェアを最適化した経験のある人なら誰もが知っているように、鍵は測定にある。ソフトウェアのどの部分が遅くて、どこをどうしたら速くなるかを推測に頼っているときは、その推測はまず確実に間違っている。
ユーザ数は完全なテストではないにしても、かなり近いものにはなるだろう。買収しようとする企業はそれを気にしている。収益もユーザ数に依存している。ユーザ数が多ければライバルは心配する。記者は感心し、新しいユーザ候補も関心を持つだろう。確かにこれは、どの問題を解くのが重要なのかを頭から決めてかかるよりも良い指標だ。たとえあなたが技術的にどんなに優れていようとも。
ほかにも、ベンチャー企業を最適化問題と考えれば、ベンチャーキャピタルが恐れる別の危険を避けやすくなる。製品開発に長く時間をかけ過ぎるという危険だ。この危険は、ハッカーには既に知られている、別の避けるべき問題と同じだ。早過ぎる最適化というやつだ。バージョン1.0を可能な限り速く出そう。ユーザを獲得しない限り、手探りでの最適化からは逃れられない。
常に注目しておかねばならないことは、富とは人々が欲するものであるという基本原理だ。富を作り出すことで裕福になろうとしているなら、人々が欲するものは何かを知っていなければならない。顧客を幸せにすることに本当に注意を払っているビジネスはほとんど存在しない。内心びくびくしながら、店に入ったり、会社に電話をかけたりすることは多いだろう。電話で「あなたの電話はわたしたちにとって重要です。どうかしばらくお待ちください」という録音されたアナウンスを聞いて、うん、いいぞ、これで大丈夫だ、なんて思うかい?
ファミリーレストランは、たまには焦げた料理を出しても何とかやっていける。でも技術の分野では、ひとつの料理を皆が食べる。人々が欲するものとあなたが作るものとのギャップは、何倍にも拡大される。顧客全員を喜ばせるか、煩わせるかだ。顧客が欲しがるものに近づけば近づくほど、生み出せる富は大きくなる。
富と力
富を創ることは裕福になる唯一の方法ではない。人類の歴史の大部分では、むしろ他の方法がずっと多かった。数世紀前までは、富の腫瘍な源は鉱山や奴隷や農奴、土地、あるいは家畜であり、それらを一気に得るには、相続するか、結婚するか、征服するか、没収するしかなかった。富に悪い評判が立つのも自然なことだ。
2つの変化があった。まず、法律による規制だ。世界の歴史の大部分の期間では、誰かが財を成すと、支配者やその取り巻きたちはそれを掠め取る方法を見出した。しかし、中世のヨーロッパで新しいことが起きた。新しい階級である商人や工場主が都市に集まりだした。
中産階級が最初にイタリアと低地諸国に現れたのは偶然ではないだろう。そこには、強い中央政府がなかった。これら2つの地域は当時最も裕福な地域で、ルネッサンスの拡がりの2つの中心となった。これらの地域がいまでは中心でないのだとしたら、それは彼らがもともと発見した原理を、米国など他の地域のほうが忠実に実行しているからだろう。
彼らは一緒になって、地域の領主に立ち向かった。そして歴史上初めて、いじめっ子がいじめられっ子の弁当代を盗むのを止めさせることができたのだ。これはもちろん、第二の変化である工業化への大きな動機付けになった。いや、むしろ主要な理由であったかもしれない。
産業革命の理由については既に様々な論説が書かれている。だが、自分の作った財産を平和に持っておけるということは、十分条件ではないにせよ、必要条件ではあったはずだ。
これは、十分条件でもあり得る。だがそうだとして、なぜ産業革命はもっと早くに起こらなかったのだろう。2つの(相互に矛盾しない)答えが考えられる。(a) それは実際に起きていた。いわゆる産業革命は、連続して起きていた変化のひとつにすぎない。(b) 中世の都市では、独占とギルドの縛りが新しい生産手段の発展を妨げていた。
証拠のひとつは、ソビエト連邦や、英国の1960年代から1970年代の労働党政権のように、古いモデルに戻ろうとした国に何が起きたかだ。富への動機付けを取ってしまえば、技術革新はほとんど停止してしまう。
経済的に、ベンチャー企業が何を意味していたかを思い出してほしい。それは「私はもっと働きたい」と主張する手段だった。50年間、普通の給料をゆっくり貯める代わりに、できる限り早くお金を得たい、と。もし政府が富を貯めることを禁じるなら、それは実質的に、ゆっくり働けと命じているに等しい。50年の間に3億円稼ぐことは推奨するけれど、ものすごく働くことで2年間でそれをやるのはダメ、というわけだ。ちょうど、10倍働くから10倍給料をくれと行っても通じない、大会社の上司みたいなものだ。違いは、国の場合はそこから抜けて新しい会社を始めるわけにはいかないことだ。
ゆっくり働くことの問題は、技術革新が遅くなるだけではない。革新が全く起こらなくなることだ。革新を起こすようなプロジェクトをやりたいと思うのは、スピードを味方にして敢えて難しい問題に挑戦しようとするときに限られる。新しい技術を開発するのはものすごく大変なことだ。エジソンが言ったように、1%のひらめきと、99%の努力なのだ。富への動機付けがなければ、誰もそんなことをやろうとはしないだろう。エンジニアは確かに、月ロケットとか戦闘機みたいな華々しいプロジェクトなら普通の給料でも仕事をするだろうけれど、もっと地味な技術、電球や半導体のようなものは、起業家によって開発されなければならない。
ベンチャー企業は、ここ20年の間にシリコンバレーに出てきたものではない。富を創り出すことで裕福になることが可能になってからというもの、それをした全ての人が、同じレシピを使ってきた。測定と梃子だ。小さな集団で働くことで測定を得て、新しい技術を開発することで梃子を得る。このレシピは、1200年のフィレンツェでも、今日のサンタクララでも、何の違いもない。
このことを理解することで、ヨーロッパはなぜあんなに成長したのか、という重要な問いの答えが見つかる。ヨーロッパの塵が重要だったのだろうか。それともヨーロッパ人が人種的に優れていたのだろうか。それとも宗教のせいか。答えは(少なくとも近似的には)、財を成した人にそれを持っていてもよいとする、という強力で新しいアイディアの波に乗ったからだ。
それが許されて初めて、剤を成したい人は、盗む代わりに富を生み出すようになった。この技術の進歩の結果は、富だけでなく、軍隊の力にも変化していった。ステルス航空機の原理となる理論はソ連の数学者により作られた。しかしソ連はコンピュータ産業を持っていなかったため、それは理論に留まった。実際の航空機を設計するのに十分なだけ速く計算ができるハードウェアを持たなかったからだ。
この点では、冷戦は第二次世界大戦と同じ教訓を教えてくれるし、それを言えば近世以降のほとんどの戦争はそうだ。軍人や政治家の支配者階級に、起業家を潰させるな。個人を裕福にするのと同じレシピが、国をも裕福にする。いじめられっ子の弁当代を取り上げないでおけば、世界を征服できるんだ。
第二章:富の再定義と常識の書き換え
オセロをやったことがあるだろうか。
この世は、縦にも横にも無限に盤面が拡がるオセロのような性質がある。
いままで真っ白だった列が、両端を黒に挟まれるだけで真っ黒な世界になる。
情報というものは、入力があって、処理して、出力される。
プログラムでもし入力されたデータに間違いがあったら、出力も当然ながら正しくないものになる。
我々は一体、正しいデータを処理しているのか?という命題と、我々の処理体系を支える論理構造は矛盾が無いのか?という命題が常にある。
そしてそれは常に変動していくものなのだ。ある時代の常識は、別の時代の非常識になる。
その変化が目まぐるしくなっているのはなぜかというと、情報の交換が世界レベルで加速しているからだ。
目まぐるしく書き換えられるものは、大事なものを支える柱にはなりえない。
こうした時に必要なのは、情報のメタ化と、情報の詳細化というふたつの全くベクトルの異なるアプローチの併用だ。
マクロに迫るメタ化と、ミクロに迫る詳細化。
演繹と帰納。このいずれかが欠けてしまうと、論理展開できない。
また、縦軸でものを考える捉え方と、横軸で考える捉え方のふたつも重要となる。
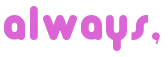



コメント