Source One: Suzume
2023/05/06 TOHO Cinemas日比谷「すずめの戸締まり」(監督:新海誠)

公式サイト:https://suzume-tojimari-movie.jp/
Source Two: Synchronicity
シンクロニシティ 科学と非科学の間に
著:ポール・ハルパーン(Paul Halpern)、翻訳:権田敦司(生物学者)、解説:福岡伸一
ダイジン(白猫)、サダイジン(黒猫)
ダイジン
概要
九州の田舎町の廃墟にあった災いの扉「後ろ戸」を閉じた岩戸鈴芽と宗像草太の前に突然現れた、人間の言葉を話す謎の白い猫。草太を小さな子供椅子の姿に変えた張本人であるほか、鈴芽と草太の旅のきっかけとなった存在でもある。日本各地に開く後ろ戸とともに出没し、戸締まりの旅をする鈴芽たちを翻弄することになる。また、ダイジンという名前は彼自身が名乗ったわけではなく、日本中を放浪していくなかでSNS上で話題に上がるうちに自然と「ダイジン」という名前がつけられたことによるものである。
容姿
左目だけ黒く縁取られた黄色い丸い目をした、白い毛並みの小さな子猫。上向きにカールした白いひげが昔の大臣を思わせることから「ダイジン」という名前で呼ばれている。
鈴芽の前に初めて現れたときは、骨ばった身体でげっそりと痩せこけていたものの、彼女からご飯をもてなされて以降は、大福のようにふっくらと肉づいて元気を取り戻し、ちょこまかと走り回るようになる。
性格
意図のさっぱりつかめない、気まぐれで自由奔放な性格の持ち主。極めて透明感のある幼子のような声色で無邪気に語りかけ、持ち前の神出鬼没さで遊び相手を翻弄している。
また、たまたま目についた人間をにたりと笑いながら呪って椅子の姿に変えたり、数百年に一度の大災害が起こるさまを前にして「いまからたくさん ひとがしぬ」と嬉しそうに昂るなど、人道的な情緒や他者をおもんばかる共感性が欠落しているような発言も見受けられる。
能力
人間の言葉を話して対話できるのみならず、目をつけた人間を無機物の姿に変えてしまう呪いをかけることもできる。
また、神戸のスナックに姿を現した際には、スナックの店員や客に暗示をかけて自身の姿を羽振りのいいダンディに見せかけ、「よっ、お大尽!」「大尽太っ腹!」などと場を盛り上げている。
経歴
ダイジンの正体は神を宿した要石(かなめいし)が猫の姿になった、いわゆる「かりそめの顕現」であり、もともとは長きにわたって九州の地で人知れず災いを鎮める存在であった。
あるとき、地元の廃墟の温泉街を訪れた鈴芽が、後ろ戸のそばに埋まっていた要石を引き抜いたことで、封印が解けたダイジンは猫の姿になってその場を逃げ出している。そののち、自身を引き抜いた鈴芽のもとに現れたダイジンは、彼女からご飯を与えられて可愛がられたことで彼女を気に入り、そばにいた草太を邪魔者扱いして椅子の姿に変えてしまう。怒った草太と困惑する鈴芽から追いかけられたダイジンは、港を出たフェリーの甲板に追い詰められてしまうものの、偶然にそばを通りかかる警備艇を見つけ、「またねっ」と言葉を残して彼らのもとから逃げ延びている。
その後のダイジンは、道行く人々の前で子猫としての愛くるしい振る舞いを見せ、数々の写真やテレビ中継に収められている。とりわけSNSでは、ダイジンのキュートな見た目や仕草が大きな人気を博し、「#ダイジンといっしょ」という専用のハッシュタグまで作られて話題を集めるまでになっている。
ダイジンはそうして人々の噂の種になることで鈴芽と草太を後ろ戸の開く場所へと誘い出すとともに、戸締まりを終えた彼らの前に姿を現して「うしろどは またひらくよ」と言葉を残して消え去るなど、彼らを翻弄することを楽しむような様子を見せている。
サダイジン

概要
岩戸鈴芽が「戸締まりの旅」の途中で出会う、人間の言葉を話す謎の黒い猫。
その正体は、かりそめの顕現として黒猫の姿を借りた「東の要石」であり、もともとは東京都のどこかに存在する巨大な後ろ戸のもとで人知れず災いを鎮める存在であった。
災いを封じながら悠久の時を過ごしていたサダイジンは、あるとき「西の要石」であるダイジンが要石の役目を放棄して逃げ出してしまったことをきっかけとして、たった一本だけで暴れ狂う災いを押さえつけなければならないという危機に直面してしまう。4日間にわたる苦闘の末、要石としてのサダイジンは耐えきれずに抜けてしまい、これまで封じていた災いのすべてを現世(うつしよ)に逃してしまうものの、間一髪のところで新たな要石が災いを食い止めてくれたことによって最悪の事態は回避された。しかしながら、それも一時的なものに過ぎないと判断したサダイジンは、常世(とこよ)に入ることを望む鈴芽の前に現れるとともに、彼女に要石としての自身の責務を果たす助けをしてほしいと頼み込むことになる。
容姿
ぎらぎらと光る緑色の瞳を持つ、大型犬ほどの大きさの黒い猫。目を縁取る毛の模様はダイジンと対照的になっており、ダイジンが左目を黒い毛で縁取っているのに対して、サダイジンは右目を白い毛で縁取っている。
また、身体の大きさについても、初めて鈴芽の前に現れた際には乗用車と同程度の巨体であったものの、そののち車の後部座席にすっぽり収まるサイズまで縮んだりするなど、身に秘める能力によって自在に変えられる様子をうかがわせている。
性格
幼子(おさなご)のような声色とは裏腹に、くっきりとした知性と明確な意志を宿しており、その口ぶりには要石として過ごした時の長さがにじみ出ている。
あわせて、自身が押さえきれずに解放してしまった災いをふたたび鎮めるために鈴芽に協力を求めたりするような、人間に味方をして平和を守ろうとする想いも見て取ることができる。
能力
ダイジンと同様に、人間の言葉を話すことによって人と意思疎通を図ることができる。
また、人間に取り憑いてその人の秘める想いを暴くといった、いわゆる「狐憑き」のような力も併せ持っており、作中では鈴芽の前に現れる際に彼女の叔母である岩戸環にこっそりと取り憑き、彼女が頑なに伏せていた鈴芽への負の感情を引きずり出している。
経歴
九州に祀られていたダイジンと対をなす「東の要石」であるサダイジンは、東京都千代田区の皇居の地下深くにある古びた後ろ戸のもとで人知れず祀られており、後ろ戸を通って現世に現れ出ようとする災いを永きにわたって鎮めていた。しかし、九州の地で災いの一端を押さえていたダイジンが抜けてしまったことにより、勢力を強めた災いは現世に出ようと暴れ回るようになり、残された東の要石であるサダイジンはたった一本だけで災いをつなぎ止めていた。しかし、サダイジンは暴れ回る災いの力に耐え切ることはできず、ダイジンが抜けた4日後にとうとう災いの力の前に屈して抜けてしまい、数百年に一度の巨大な災いを東京の上空に逃してしまうことになる。
その巨大な災いは、新たな要石になった宗像草太がその身を犠牲にして封じ込めたものの、サダイジンは要石1本だけでは災いを押さえきれなくなるのも時間の問題であると認識し、旧知の「閉じ師」である宗像羊朗のもとを訪れる。そこで常世に入ることを望む少女・鈴芽の存在を知ったサダイジンは、彼女が羊朗の病室を去ったのちに黒猫の姿で羊朗の前に現れ、久々の対面を果たした彼から鈴芽への力添えを頼まれている。
サダイジンは自身の故郷に向かって旅をする鈴芽を追いかけ、道中の道の駅で彼女の前に現れる。その際に鈴芽の叔母である環に取り憑いて彼女の本心をあらわにしたために、鈴芽を悲しませたことを怒ったダイジンから飛びかかられてしまうものの、それを軽くいなしながら平然とした体で彼女たちの旅に加わっている。そして、その旅のなかで鈴芽の乗る車を運転する芹澤朋也が「その黒猫には鈴芽に何かしてほしいことがあるのではないか」という素朴な疑問を口にしたことから、サダイジンは「そのとおり」と口を開き、要石である自身をふたたび災いに刺して鎮めてほしいという頼みを明かしている。
真の姿
鈴芽との旅の末に、彼女とともに常世に降り立ったサダイジンは、現世に出ようと暴れ回る災いを力づくで食い止めるために、これまで隠していた「猛き大大神(おおおおかみ)」としての真の姿をあらわにしている。
雄叫びとともに一瞬で巨大化したサダイジンは、家ほどの大きさがある巨体と、長い髭と尾をたなびかせた白い毛並みの獣へと変貌を遂げている。猛き大大神の名にふさわしい威厳と勇猛にあふれた姿になったサダイジンは、一陣の風のような速さと鋭い爪牙(そうが)をもって、荒れ狂う災いに真正面から挑みかかっている。
要石(かなめいし)
要石(かなめいし)は、茨城県鹿嶋市の鹿島神宮、千葉県香取市の香取神宮、三重県伊賀市の大村神社、宮城県加美町の鹿島神社に存在し、地震を鎮めているとされる、大部分が地中に埋まった霊石。
鹿島神宮
鹿島神宮の要石は、鹿島神宮奥宮(武甕槌神の荒魂)の背後約50メートル、本宮より東南東約300メートル離れた、境内の森の中に位置する。 花崗岩で、地上露出部分はほんの十数センチメートルであり、凹んでいる。
鹿島神宮の要石は、「山の宮」、「御座石(みましいし)、石御座(いしのみまし)」と呼ばれる。日本神話の葦原中国平定において、天津甕星(天香香背男)は平定の大きな妨げになった(日本書紀、巻第二神代下、第九段一書の二)。天香香背男討伐にあたり、経津主神と武甕槌神は建葉槌命を遣わす(日本書紀、巻第二神代下、第九段本文)。鹿島神宮社伝によれば、武甕槌神は見目浦(みるめのうら)の磐座に降り、天香香背男討伐のため建葉槌命を派遣した[12]。神が降りた磐座が現在の要石、住居が鹿島神宮の原型であると伝えられる。
『鹿島宮社例伝記』によれば、鹿島社要石は仏教的宇宙観でいう、大地の最も深い部分である金輪際から生えている柱と言われ、この柱で日本は繋ぎ止められているという。同じような謂れを持つ場所に琵琶湖の竹生島がある。また、日本書紀では「鹿島動石(ゆるぐいし)」「伊勢大神宮」など、漂う日本を大地に繋ぎ止める「国中の柱」とされる場所が全国に点在しているとされていた。『詞林采葉抄』などの文献資料から、神仏習合を経て14世紀中頃に要石のイメージは固まったと見られる。
古墳の発掘なども指揮した徳川光圀は、鹿島神宮と香取神宮の両宮を崇敬していた。1664年、要石(どちらの要石かは資料により一定しない)の周りを掘らせたが、日が沈んで中断すると、朝までの間に埋まってしまった。そのようなことが2日続いた後、次は昼夜兼行で7日7晩掘り続けたが、底には達しなかった。香取神宮史によれば、同年3月に同宮を参拝し、楼門前に桜を植えた。その際に香取の要石を掘らしたが根元を見ることが出来なかったという。
1255年(建長8年)に鹿島神宮を参拝した藤原光俊は、「尋ねかね 今日見つるかな 千劒破 深山の奥の 石の御座を」と詠んでいる。
江戸時代には「ゆるげどもよもや抜けじの要石 鹿島の神のあらん限りは」で締めくくる呪い歌を紙に書いて3回唱えて門に張れば、地震の被害を避けられるという風習があった。1596年の京都の公家日記『言経卿記』に、近畿地方で起こった地震の際に、余震避けとして3首の呪い歌が街中に貼られたという記録がある。
1855年10月の安政大地震後、鹿島神宮の鯰絵を使ったお札が流行し、江戸市民の間で要石が知られるようになった。地震が起こったのは武甕槌大神が神無月(10月)で出雲へ出かけたからだという説も現れた。
地中深くまで埋まる要石が、地震を起こす鯰の頭を抑えていると古くから伝えられています。水戸の徳川光圀公がどこまで深く埋まっているか確かめようと7日7晩にわたって掘らせたものの、いつまで経っても辿り着くことができなかったばかりか、怪我人が続出したために掘ることを諦めた、という話が黄門仁徳録に記されています。
香取神宮
香取神宮の要石の地上部分は丸い。香取神宮の要石は総門の手前にある。
古くより、この地方は大変地震が多く、人々はとても恐がっていました─これは、地中に大きなナマズが住み着いて荒れ騒いでいるのだと。香取・鹿島両神宮の大神様等は、地中に深く石棒を差し込み、大ナマズの頭尾を刺し通されたといいます。当神宮は凸形、鹿島は凹形で、地上に一部を現し、深さ幾十尺と伝えられています。貞享元年(一六八四)水戸光圀公が当神宮参拝の折、これを掘らせましたが根元を見ることが出来なかったといわれています。
大村神社
三重県伊賀市(旧・青山町)の阿保に所在する大村神社は、土地の守り神である大村神を祀る地震との関わりが深い神社であり、拝殿の西側に大鯰を抑える形で奉鎮されている。
また、近隣の名張市の下比奈知には、地震の神であるなゐの神を祀っていたとされている名居神社が存在する。
拝殿の西に「要石」が奉斎されています。創始は、 神護景雲元年(767年)、御本殿相殿祭祀の武甕槌命・経津主命は、常陸・下総の国より奈良の 三笠山遷幸の途次、大村神社に御休息、「要石」を奉鎮せられました。この霊石は、地下深く広がり、大地を揺るがす大なまずをしっかりと押さえていると伝えられています。又大村の森全体が大きな岩盤におおわれ、この地域をしっかりと護っていると伝えられています。毎年、9月1日の防災の日に地震除災祈願大祭が斎行され、又秋祭り には大なまずが街中に引き出されます。
鹿島神社
宮城県加美町の鹿島神社にも要石があり、風土記によれば鹿島神宮のものを模したものだという。1973年にはまた別の要石が奉納され埋められた。
この鹿島神社は鹿島神宮と祭神は同じだが、他の多くの「鹿島神社」と違い、鹿島神宮ではなく塩竈神社からの勧請である。
要石に鹿島の大神が降臨して守護っているから日本の国土はぐらぐらしないと云う意味です。
要石は鹿島神社以外の神社には祀られていません。
俗に要石を拝むと云う事は家庭的にも社会的にも精神的には、どんな地震が起きるともびくともしない不動の精神を養うと云う信仰の精神は、すなわち人間の 「へそ」であり其の「へそ」が要石とも云えます。現在鹿島神社境内に祀られている要石は昭和四十八年故事来歴により奉納された「約十トン」の要石で往古の要石と共に祀られています。
鹿島神社の境内にある要石は
武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)※1の象徴として国家の鎮護の石剣として
祀られている事は有名です。この要石は国を鎮める意想で日本国をとりまく「リュウ」を鎮める石剣とされています。
「リュウ」龍は古代では海水を意味し、日本をとりまく「リュウ」が転化してナマズ(鯰)になりました。 地震は地下にもぐった鯰の寝がえりだとされてこの要石は地震ナマズを永遠におさえていると云う 信仰をうんだのです。(日本民族学全集より)
加美町鎮守鹿島神社社殿の西御山下の老杉の根元に要石というのがあります。安永書上の風土記にも高さ一尺二寸余、廻り四尺八寸余(住古より要石と申伝候事)とあり、頭の方一尺余り出ているが地下の大鯰の背中に達していると云われて来たもの、これは常陸の鹿島神宮の要石に模したものと伝えられます(風土記参照)
常陸(茨城県)鹿島神宮の要石の伝説によれば昔その地方にしばしば地震があり、それは地下に大鯰がいてあばれるからだと云うので、鹿島の神々達が相談の上大きな石の棒(石剣)で鯰の頭を釘刺してしとめました。
それが即ち要石で地震の際にはこの要石は殊の外大いに揺れるが どうしても抜くことが出来ないと云われて来ました。我が地方においても大地震はくるけれども鹿島神社には要石が祀られているから昔から大きな災害がないと語り伝えられています。
※1 古事記では建御雷之男神(たけみかづちのおのかみ)
現世(うつしよ)
現世(げんせ、げんせい、うつしよ)とは、現在の世のこと。古くは「げんぜ」とも読む。
概要
我々人間が現在暮らしていると思っている(認識している)世界、または、その認識。日本語では「顕世(けんせ)」とも読み書きし、「この世」とも言い換えられる。
仏教用語としての「現世」は「げんぜ」と(も)読む。自身が輪廻転生していくなかで今生きて属している(生を受けた)この世界のことを指す。彼岸に対する此岸。
現世に対置される世界としては、仏教では、前世、来世(それに加えて地獄が語られることも)。神道では常世・常夜(とこよ)、幽世・隠世(かくりよ)などがある。キリスト教では、天国、地獄(陰府)などがある。
江戸川乱歩は「現世は夢、夜の夢こそまこと」としばしば好んで色紙に書いたことで知られる。
神道
神道では「現世」と書いて古語としては「うつしよ」と読み、この世や人の生きる現実世界を意味する。それに対峙して、常世(とこよ)いわゆる天国や桃源郷や理想郷としての神の国があり、常夜(とこよ)と言われるいわゆる地獄としての死者の国や黄泉の国と捉えている世界観がある。
ただし、常世と現世として二律背反や二律双生の世界観が基本であり、常世・神の国には2つの様相があり、このことは常世(常夜と常世は夜と昼とも表される)が神の国としての二面性を持つことと、荒ぶる神と和ぎる神という日本の神の2つのあり方にも通じるものである[要出典]。
古神道の始まりといわれる神籬(ひもろぎ)・磐座(いわくら)信仰の森林や山・岩などの巨木や巨石は、神の依り代と同時に、籬は垣(かき)の意味で磐座は磐境(いわさかい)ともいい、常世と現世の端境を表す神域でもある。神社神道においても鎮守の森や植栽された広葉常緑樹は、神域を表すと同時に結界でもあり、常世(神域)と現世の各々の事象が簡単に行き来できないようにするための物であり、禁足地になっている場所も多い。
また、集落につながる道の辻に置かれる石造の祠や道祖神や地蔵なども、厄除けや祈願祈念の信仰の対象だけでなく、現世と常世の端境にある結界を意味するといわれる。現世における昼と夜の端境である夕刻も常夜との端境であるとも考えられ、この時分を「逢魔時(おうまがとき)」といって、現世に存在しないものと出遭う時刻であると考えられている。
仏教
仏教における「三世」の一つであり[2]、前世、今世、来世 のうちの今世に該当する。また、時間的な前後は別として、浄土教では「厭離穢土、欣求浄土」の概念がある。「穢土」とは「穢(けが)れた世」という意味で、現世にあたる。
『金剛般若経』では「一切の有為の法は、夢幻泡影の如し」とあり、現世を夢幻、泡のように儚いものとして把握していたことが窺える。このように仏教では現世を否定的に捉えていた。
プロテスタンティズム
近代プロテスタンティズムでは被造物を重視することが徹底して否定され、それによって現世の否定がなされ、来世指向のみになったが、やがて現代化するにつれて来世指向は失われ現世指向に傾斜した、と池田昭は解説した。
現世利益
神仏の恵みが現世で与えられるとする信仰。 日本では、一般的に、多種多様な神仏は、それぞれの特色に応じた恵みを、生活の様々な局面のなかで授けてくれるという世界観が根付いている。 一般的に、宗教における現世利益の位置づけは軽視されがちであるが、日本においては、神仏と切っては切れないものとして認識されている。
神道
古来より、地域共同体の守護神である氏神や鎮守神へ、村落などの氏子の共同体成因の集団的意志として、雨乞い、日乞い、虫送り、疫病送りなどの現世利益を得ることを目的とした祈願行為が行われていた。現代でも、「祭」のなかに、その伝統文化が根付いている。 現在では、個人の心願に応えるために、神前にて、神職や巫女により祝詞奏上や神楽舞奉奏がされ、祈願者の玉串拝礼により得られるとする。 個人としての心願の種類としては、病気直し(自分とその家人)、家内安全、商売繁盛、生活苦からの離脱に分類され、そのうち、病気なおしを祈願する場合がもっとも多いという。
仏教
教典を読経したり、真言・題目を唱えたり、祈祷を行う、寺や塔、仏像などを建立することにより得られるとする。
日本では、仏教伝来以降、奈良大仏のように国策として仏像の建設をするなど、現世利益を得る政策がとられた。そして、災厄が訪れ、生活が挫折した際、回復するためにご利益を願うという民衆の心意に対応し、古代末期から中世にかけてさかんとなった真言・天台密教による加持祈祷により、民衆に広まった。現在でも、僧侶による護摩修行などが盛んに行われている。
鎌倉仏教の時代になると、法然のように「いのるによりて病もやみ、いのちも延ぶることあれば、たれかは一人として病み死ぬるひとあらん」(祈ることで病気が治り寿命が延びるなら、どこに死ぬ人がいるだろうか)として現世利益に否定的な者も現れた。
インド
インドではガネーシャが現世利益をもたらす神とされ、民間では非常に人気がある。特に「富の神様」として商人からの信仰を集めている。
常世(とこよ)
常世(とこよ)、かくりよ(隠世、幽世)とは、永久に変わらない神域。死後の世界でもあり、黄泉もそこにあるとされる。「永久」を意味し、古くは「常夜」とも表記した。日本神話や古神道や神道の重要な二律する世界観の一方であり、対義語として「現世(うつしよ)」がある。
概要
「常夜」と記した場合は、常に夜の世界であり、常夜という表記の意味から、死者の国や黄泉の国とも同一視される場合もある。ただし、折口信夫の論文『妣が国へ・常世へ』(1920年に発表)以降、特に「常世」と言った場合、海の彼方・または海中にあるとされる理想郷であり、マレビトの来訪によって富や知識、命や長寿や不老不死がもたらされる『異郷』であると定義されている。
古神道などでは、神籬(ひもろぎ)・磐座(いわくら)などの「場の様相」の変わる山海や森林や河川や大木・巨岩の先にある現実世界と異なる世界や神域をいう。
日本神話
『古事記』や『日本書紀』1書第6によると、大国主神とともに国造りを行なった少名毘古那神は国造りを終えた後に海の彼方にある常世の国に行ったという記述がある。
『万葉集』では、浦島太郎が行った竜宮城も常世と記され、現実の世界とは時間の流れが著しく違う。このことから不老不死の楽園を表すとされる。
『日本書紀』の天照大神から倭姫命への神託では、伊勢を常世の浪の重浪の帰する国(「常世之浪重浪歸國」)とある。
古神道・結界と禁足地
古神道の依り代とされる巨石・霊石や神木や鎮守の森などは、神の依り代であると同時に、神籬の「籬」は「垣」であり磐座は「磐境」ともいい、それぞれ「端境」を示している。
その境界の先は神域と考えられ、常世のことであり、沖ノ島などは社(やしろ)や鎮守の森だけでなく、島全体が神域となっていて禁足地である。鎮守の森や神社の広葉常緑樹の垣は、その常世との端境であると同時に結界でもあり、現世と常世の様々なものが簡単に行き来し、禍や厄災を招かないようにしていて、禁足地になっている場所も多い。
集落に繋がる道の辻に、石造の道祖神や祠や地蔵があるのは、道すがらや旅の安全の祈願祈念だけでなく、常世との端境にある結界の意味を持つ。
常夜という意味から、夕刻などの夜と昼の端境も常世と繋がると考えられ、「逢う魔時」といわれ、深夜なども深い静寂な夜は、常世と重なることから、現実には存在しない怪異のものが現れる時刻を、「丑三つ時」と呼び恐れた。
琉球神話
琉球神話には、これと類似する異界概念としてニライカナイがある。
和歌
紫式部 著『源氏物語』
第12帖「須磨」
- 心から常世を捨てて鳴く雁を雲のよそにも思ひけるかな
- 常世出でて旅の空なるかりがねも列に遅れぬほどぞなぐさむ
- あかりなくにかりの常世を立ち別れ花の都に道やまどはむ
第41帖「幻」
- なくなくも帰りにしかな仮の世はいづこもつひの常世ならぬに
常世国(とこよのくに)
常世の国(とこよのくに)は、古代日本で信仰された、海の彼方にあるとされる異世界である。一種の理想郷として観想され、永久不変や不老不死、若返りなどと結び付けられた、日本神話の他界観をあらわす代表的な概念で、古事記、日本書紀、万葉集、風土記などの記述にその顕れがある。
こうした「海のはるか彼方の理想郷」は、沖縄における海の彼方の他界「ニライカナイ」にも通じる。
常世の国の来訪者
日本神話においては、少彦名神、御毛沼命、田道間守が常世の国に渡ったという記事が存在する。浦島子(浦島太郎)の伝承にも、常世の国が登場する。
少彦名神
大国主国造りのくだりでは、少彦名神が大国主とともに国土を成した後に帰った地とされる。『古事記』上巻の記述では、この国を作り固めた後、少彦名神は常世の国に渡ったとあり、日本書紀神代巻の該当箇所では、本文ではなく第八段の一書第六の大国主の記事中に、大国主神が少彦名命と力を合せて国作りの業を終えた後、少彦名命は熊野の岬に行き、そこから“常世郷”に渡った、またその直後に異伝として「淡嶋(鳥取県米子市)に行き、登った粟の茎に弾かれて常世郷に渡ったとある。この茎に弾かれた話は「伯耆国風土記」逸文にも出てきており、伯耆国の「粟嶋」という地名の由来譚となっている。
御毛沼命
御毛沼命(三毛入野命)は鵜葺草葺不合命の息子で、神武天皇の兄にあたる。『古事記』の中ではまったく何の事跡もなく、上巻末尾の鵜葺草葺不合命の子を並べたところに、御毛沼命は波の穂を跳みて常世の国に渡ったとのみある。『日本書紀』では三毛入野命が神武天皇の東征に従軍して軍船を進め熊野に至った折、暴風に遭い、「自分の母と姨はともに海の神であるのに、なぜ波を起こして我々を溺れさせるのか」と嘆き、波の秀を踏んで常世郷に往ったという。
田道間守
『古事記』では垂仁天皇が多遅摩毛理に時じくの香の木の実(ときじくのかくのこのみ)を、『日本書紀』の垂仁紀では、垂仁天皇が田道間守を常世国に遣わして、「非時香菓」を求めさせたが、その間に天皇は崩御したという記述がある。「非時」は、時を定めずということから「いつでも香りを放つ木の実」を指すと解され、「今の橘なり」と言われる。橘は葉が常緑であることから、すぐに散る桜とは対照的に「永遠性・永続性」の象徴と考えられており、「非時香菓」もまた不老不死の霊薬(黄金の林檎)と考えられる。
浦嶋子
『万葉集』巻九・1740の高橋虫麻呂作の浦嶋子を詠んだ歌では、浦島子が漁に出て、七日帰らず海を漕いで常世に至り、海若(わたつみ)の神の宮に神の乙女とともに住んだという。神の宮では老いも死にもせず、永世にわたって生きることができたにもかかわらず、浦嶋子は帰郷し、自分の家が既に無くなっていることを知って開けてはならぬ玉笥を開けてしまう。この歌における常世の国は、海の神の支配する不老不死の世界であること、また外界とは時間の流れの異なる世界であるという観念が読み取れる。『日本書紀』の雄略天皇二十二年や、『丹後国風土記』逸文にも同様の話があるが、いずれも海中の「蓬萊山」に至ったという。
常世の国は死後の世界か理想郷か
先に引いたように、常世の国へ至るためには海の波を越えて行かなければならず、海神ワタツミの神の宮も常世の国にあるとされていることから、古代の観念として、常世の国と海原は分かちがたく結びついていることは明らかである。『万葉集』の歌には、常世の浪の重浪寄する国(「常世之浪重浪歸國」)という常套句があり、海岸に寄せる波は常世の国へと直結している地続き(海続き)の世界ということでもある。
しかしながら、常世の国には、ただ単に「海の彼方の世界」というだけでなく、例えば「死後の世界」、「神仙境」、永遠の生命をもたらす「不老不死の世界」、あるいは「穀霊の故郷」など様々な信仰が「重層的」に見て取れる。
常世の国=死の国という観想は、神武東征における御毛沼命の常世の国渡りの話から読み取れる。これは、ヤマトタケルの東伐の中で弟橘媛が嵐を鎮めるために海に身を投げたというエピソードと状況が非常に類似しており、仮にこの対比が妥当だとすれば、御毛沼命は海に身を投げてわが身を生贄としたのであり、直接に「常世の国=死後の世界」を暗示させる。
また、常世の国は神々の住まう神仙境としても信仰されている。『万葉集』の浦嶋子の歌におけるワタツミの神の宮(「常代尓至 海若 神之宮」)はまさに神の居所であり、『日本書紀』の垂仁紀では、天皇崩御の翌年に実を持ち帰った田道間守がついに間に合わなかったことを慨嘆して、「遠く浪を踏んで遙かに弱水(河川)を渡って至った常世の国は、神仙のかくれたる国、俗のところではない。このため往来に十年かかってしまった。帰還を果たせないと思ったが、帝の神霊によってかろうじて帰ることができた」と述べている。
田道間守が持ち帰った「非時香果」はまさに永遠性の象徴であり、常世の国に渡った浦嶋子が老いることも死ぬこともない世界に至ったという『万葉集』の歌からは、常世すなわち永久不変の国という観想が見られる。
それ以外にも、常世の国に渡った神話的存在がいずれも多少は穀物神・豊穣神の属性を持っていることから、常世の国は豊穣・穀物をもたらす「穀霊の故郷」としての信仰も考察されている。すなわち、少彦名が国造りに協力した創造的な神であること、御毛沼命の名義は「御食」に通じ穀物神の要素を持つと考えられること、そして田道間守が「非時香果」を持ち帰ったという事績があることより、「豊穣・穀物をもたらす存在」と「常世の国」が結び付けられうる、とする考察である。
常世の神
前述のように、「橘」は常世の国に生える「非時香果」のこととされた。『日本書紀』の皇極紀によると、橘に発生する「虫」を、常世神として祀る新興宗教が富士川の近辺で起こり、都にまで広がった旨が記されている。この神を祀れば、富と長寿が授かると説かれた。
しかし、民を惑わすとして秦河勝に討たれ、常世神信仰は終息した。
その他
雁は常世の鳥とされ、『源氏物語』「須磨」に歌が数首詠まれている(今泉忠義 『新装版 源氏物語(二)』 講談社学術文庫 p.173)。
Mimizu
- 2011/03/11(金), 日比谷
- 2023/05/06(土), 日比谷, 満月
Noto Peninsula
- 地震多発中
- The next place to visit
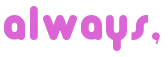



コメント