Facebookに投稿した内容
昨日15時35分に、川根の自宅で助産師さん3人を含む7人に見守られながら妻が無事に男の子を出産しました。
ご心配くださった皆様にこの場をお借りしてご報告させていただきます。
母子ともに何の問題もなく、安産でした。
午前3時から陣痛が始まり、5時に起こされて、6時に助産師さんが家に到着。
それからあれやこれやと、あっという間に時間が過ぎ、12時間後に赤ちゃんが出てきたときには、助産師さんと出産した本人以外は全員、感動の涙と鼻水でぐちゃぐちゃになってました。
思えば昨年の今頃には、赤ちゃんどころか妻と結婚することも、この子の兄2人(昊太・拓海)を家族として迎えることも、川根に移住することも、想像のはるか彼方でした。
去年の4月といえばまだ妻とは敬語混じりで話をするくらいの関係でした。
人生というものは不思議ですね。その時々で理解できないこと、説明のつかないことでも、直観・内なる声のままに行動することの大切さを強く感じます。
ここから先は僕の駄文が続きますので、お時間のある方はどうぞ。
---
「事実は小説よりも奇なり」
1897年、マーク・トウェインは『赤道に沿って(Following the Equator)』で次のように書いています。
「真実は小説よりも奇妙だが、それは小説が可能性に固執する義務があるからである。真実はそうではない」
(Truth is stranger than fiction, but it is because Fiction is obliged to stick to possibilities; Truth isn’t.)
【可能性】について語るとき、人は過去の経験や知識の範囲内でしか想像することができません。しかし「真実」や「現実」とは個々の考えの及ぶ範囲などまったくお構いなしです。可能性や不可能性といった枠にとらわれることのない無制限性をもっています。
直観を研ぎ澄まし、瞬間瞬間の生きる選択をすること。
「できる・できない」という論理は捨ててしまってよいと思います。何事もやってみなければわからないのです。
統計的有意性とか、タイパとかコスパとか、まったくの無意味とすら思っています。「1%の可能性」って一体どれだけの意味があるのでしょう。この宇宙の広さと深遠さからしたら、人の経験できることなんてごくごく限りがあるのに、僕の小さな脳味噌だけで考えたパーセンテージに有意性なんてあるとは思えません。
目の前に現れる課題は自分とってどんな「意味」をもつのか。
どう対応することが自分らしいだろうか。後悔しないだろうか。
そう考えるとき、僕が基準にしていることは、
「お天道様に恥ずかしくない行動」です。
自分の行動基準を他人に説明することなんて究極的に不可能。
でも僕は、お天道様、あの世にいるおじいちゃん、おばあちゃん、ご先祖様を裏切りたくない。
あの世が存在するか・しないかは問題ではない。
僕がそうしたいかどうかが大事。
その結果、2024年初めからずっと激動の日々でした。
人間って1日も無駄にしなかったら、想像を超える成果を出せるのだと改めて思います。
この1年間で、説明しきれないくらい多くのことがありました。
思えばその前の年も、そのまた前の年もそうだったかもしれません。たまたまこの1年間は、他人様の目にも見える変化が多かっただけのようにも感じます。
でもいま後悔なんて全くないのです。
自分にできるベストを尽くした結果だという自信があります。
人を裏切りたくないという思いも通しました。
ここに我が子がひとり増えたことを心から嬉しく思います。
名前は「正樹(まさき)」です。
正樹が皆さんのお世話になる日があるかもしれません。
よろしくお願い申し上げます。

Be Prepared(そなえよつねに)
The Scout Motto of the Scout movement is, in English, "Be Prepared", with most international branches of the group using a close translation of that phrase. These mottoes have been used by millions of Scouts around the world since 1907. Most of the member organizations of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) share the same mottoes.
スカウト運動におけるスカウトのモットーは英語で「Be Prepared(備えよ)」であり、ほとんどの国際支部ではこのフレーズに近い翻訳を使用しています。これらのモットーは1907年以来、世界中の何百万人ものスカウトによって使用されてきました。世界ガールガイド・ガールスカウト連盟(WAGGGS)の加盟団体のほとんども同じモットーを共有しています。
In the first part of Scouting for Boys, Robert Baden-Powell explains the meaning of the phrase:
『スカウティング・フォー・ボーイズ』の最初の部分で、ロバート・ベーデン・パウエルはこのフレーズの意味を次のように説明しています。
The scouts' motto is founded on my initials, it is:
BE PREPARED,
which means, you are always in a state of readiness in mind and body to do your DUTY;
Be Prepared in Mind by having disciplined yourself to be obedient to every order, and also by having thought out beforehand any accident or situation that might occur, so that you know the right thing to do at the right moment, and are willing to do it.
Be Prepared in Body by making yourself strong and active and able to do the right thing at the right moment, and do it.
— Lieut. Gen. Baden Powell C.B., Scouting for Boys (1908), "Camp Fire Yarn.—No. 4. Scout Law." (Part I, p. 48)スカウトのモットーは私の頭文字から来ています。
BE PREPARED(備えよ)
これは、常に心身ともに準備万端で、義務を遂行する準備を整えていることを意味します。
「心の準備」とは、あらゆる命令に従うよう自らを律し、また、起こりうるあらゆる事故や状況を事前に想定しておくことで、適切な時に適切な行動をとれるようになり、それを実行する意志を持つことです。
「体の準備」とは、自らを強く、活動的にし、適切な時に適切な行動をとれるようにし、そしてそれを実行することです。
—ベーデン・パウエル中将、C.B.『スカウティング・フォー・ボーイズ』(1908年)、「キャンプファイヤー・ヤーン第4号 スカウト法」(第1部、48ページ)
あらゆる状況に応じられるようになるために想像力を駆使し、「あらゆる状況」を想定していく過程は、僕の人生において屈指の楽しい活動です。そしてただ想像するだけでなく、個々の状況を深堀りしながら最適解であると自分が出した結論に応じた行動をし、その結果がまたデータとして蓄積され、次の分析につながる。これを延々と繰り返していくことによって、物事の理解が進み、自らが出した疑問や仮説への自分なりの答えを得ることができ、さらに望んだ成果に近づいていく。
僕にとって世界は大きな実験場であり、好奇心のままに何でもできる自由空間。
新しい生命を預かることになり、三人の個性ある息子が自立に向けて成長していく過程を見守る機会に恵まれました。
すべてにおいて「常に備える」ということは、ミクロでもマクロでも通用します。
そうすることで人生には喜び以外になにもない。僕は僕の子たちだけでなく、世界中の子どもたちがそうした自由を獲得する力をつけ、自らの貴重な人生を楽しみまくれるようになってくれることを心から願っています。
生まれた赤ちゃんは、僕が願っていることが現実に通用することを証明できるチャンス。
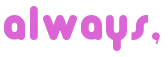



コメント