病院の大部屋で、会話に参加する気になれない。
本院にいた時はもう少し明るかった。今は、話をするだけでも疲れるし、明らかに疲れる相手と仲良くする義理もない。
研修医に『昨日はうるさくしてすみませんでした』と話しかけられた。一瞬『ん?なんのこと?』って思って、ああ、僕のお隣のベッドのおじさんのことだねってわかった。
この大部屋のおじさんたちは基本的に自己中である。まず、窓際のよく喋る丁寧で腰の低いおじさん。他人に余計なお世話ばかりして自己満足している。糖尿病なのにお菓子がやめられない。定期的に来るコンビニのワゴン販売でお菓子を買い込む。無理して生きてるからその反動が出てる。聖人ぶる必要なんてないのに。
そのおじさんと僕の間のおじさん。入院も病気もすべて他人のせいのような扱い。愚痴と言い訳ばっかりで、周りに合意を求めるタイプ。お近づきになりたくない。
かくいう僕も、病になりこの大部屋にいるのだから、何かしら気づけてない自分の嫌なところがあるんだろう。このおじさんたちのように、何かあるのだろう。未熟だから『これだ!』って確信持てないでいるけど。
病気して、様々な人にお見舞いの言葉とか実際のお見舞いとかしてもらって、その言葉一つや、態度一つからいろんなものが見える。
すべては行動で決まる。
友達だと思い込んでた相手がそうじゃなかったケース。結局僕自身、何かの利益のためにその相手と仲良くしようとしてたエゴがこの結果を導いたわけで、誰にも責任転嫁するつもりもない。
今回の入院を通じて、多くの人に愛されていることに改めて気づくと同時に、多くの愛に似た何かにも囲まれてきた事にも気づいた。
愛に似た何か。冷たくて、絶望的で、重くて、胸がぎゅっと苦しくなって、エネルギーを吸われて、それでいて、麻薬的なやつ。僕はかつてそれにもっと慣れ親しんでいた。それが暖かさだと勘違いするほどに、僕はもっと冷えていて重かった。でも当時の冷え切った僕が温かみを感じていたあの感覚は忘れ得ないから、多くの人がこれを愛と勘違いしてしまう流れもよくわかる。
本物の愛は、温度の低すぎる存在には当たり前すぎて見えないようだ。
太陽の光が燦々と頭上から光と熱の恵みを注いでくれている事にも意識せねば気づけないようなものだ。
愛はさりげなくあり、主張しないから。
交換条件に相手の常識に収まる生き方を所望されるのならば、それを叶えてあげられるのは自分ではない。
暖かい太陽のような優しい関係性が。あの海に囲まれた町の思い出。たくさんの共有した思い出。
いつも海があった。そうだ。
今年の夏は海に行くと言い続けてたっけ。
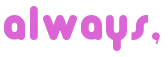

コメント