この話題は、避けて通ってきた気がする。
あえて話題にしない、そんな雰囲気でいた。
でも、父のことを思い出さない日はなかった。
自分の家族もこのブログを見ているだろうが、あえてここに書くことにする。
時がたつのは早いものだ。最後に父の顔を見てからもう何年経っただろうか。
いまでもまだまだ未熟で、もがき続けている自分だが、あの頃の自分は今よりもっと若くて、未熟で、寛容さも経験も足りなかった。
だから父を許せずに、この空白の年月を自分自身に許してしまった。
どこから切り出したらいいだろうか。
思いつくままに書いていこう。
父はいま、地球のどこか、そう遠くはないであろう場所で、内縁の妻とふたりの子供と共に暮らしている。(と伝え聞いている)
ふたりの子供とは、つまり僕にとって腹違いの兄弟ということになる。内縁の妻とも、その子供たちとも会った事はない。
その存在が僕ら家族に知られたとき、すでに上の子供は小学校の6年生だと聞いた。
つまり、(妊娠期間も含めると)少なくとも13年以上もの間、父は二重生活を隠してきたのだ。
当時の僕は20代後半。まだ結婚もしていなかった。
これを知ったとき、心の中で何かが割れる音が確かにした。
しかし、自分は長男である、父がこのような状態である以上、家族を取りまとめなければならないという意識が先にたち、冷静でいようと努めた。
まずこの事実を知った直後、僕の記憶に残っているいくつかの経験のうち不可解だったものが見事に連結した。
ひとつめ。
小学校1年生の記憶。
ある日曜。父の会社に連れて行ってもらった。
休日だったので、会社には誰もおらず、ここが父のデスクなんだ、とか興味深々でオフィスを駆け回ってた。
その後、オフィスと同じフロアにある(たぶん会社内にあった)バーのようなところにいった。
社内にそんなものある会社あるんですかね?いまさら疑問なんですが……、でも記憶は鮮明で、確かに社内にバーがあった。カウンターもあって、お酒がたくさんあった。
そこには父の同僚とか部下みたいな人がたくさんいて、知らないおじさんやおばさんにたくさん挨拶しなければならなかった。
そこに一人、髪の長いお姉さんがいた。やたらと僕に馴れ馴れしかったのでよく覚えている。彼女は僕の父にも、子供が見て変だと思うくらいに馴れ馴れしかった。
ふたつめ。
小学校2年生の記憶。
当時、父は会社所有の車を使って通勤していて、それを自家用としても使っていた。白い車ばっかりだった当時としては珍しい、緑色のカリーナだった。
電動ウインドウが珍しかったのもよく覚えている。(我ながらよくこんなことまで覚えてるな)
ぼくはその車に父とふたりで乗っていた。
どこに向かっていたかはよく覚えていない。たしか父の会社だった気がする。
そこで、女性が乗ってきた。髪の長いお姉さんだった。父は会社の人だといって紹介してくれたが、僕は以前会った事があるのを覚えていた。
その女性は助手席に座って、僕は後部座席に移った。
どこかに向かってドライブしていた。
僕はトイレにいきたくてたまらなくて、父に車をとめてトイレに連れて行ってくれとせがんだ。
でも父は、もうちょっと我慢しろって言い続けた。
後部座席から前の座席の背もたれにしがみついて、必死で我慢しながら、早くトイレ!トイレ!といい続けた。
でも車はいつまでたってもトイレにはたどり着かず、僕は我慢の限界を超え、車内でおしっこをもらしてしまった。
車をとめてくれなかった父に「どうして?」という思いが残った。
知らない女性のいる前でおしっこをもらしてしまい、自己嫌悪に陥った。
その女性は、口では優しい言葉をかけてくれるけど、なんだか冷たい感じのする人だった。
みっつめ。
何歳の頃か、よくおぼえてない。たぶんこれも、小学校2年生くらいだったとおもう。
父の会社の研修会だか社員旅行のようなものに、連れて行かれた。泊りがけだった気がする。
あのときもなぜか、母も妹も弟もいなかった気がする。
観光バスに乗った。
あの女性が、またいた。
大きな大きなダムの上をバスが通った。
ダムが怖かった。ダムは嫌いだとおもった。
よっつめ。
小学校4年生の記憶。
あいかわらず仕事が忙しいことを理由に、週末しか帰ってこないような仕事のしかたを続ける父。
ぼくはその点については信じて疑わなかった。どこの家もそんなもんだと思い込んでいたから。
その日、父はいつものようにとても遅い時間に帰ってきた。
父が帰ってきて、駐車場に車をいれる音がすると、起きているときはいつでも階段を駆け下りて父に「お帰りなさい」を言いにいったものだ。
その日、ぼくら3兄弟は、もう床についていた。
父が帰ってきたことがいつものように自動車の音で分かった。
妹と弟は眠っていた。
僕は下に降りていって顔を見せようかと思ったが、なにやら夫婦で話し込んでいる音がもごもごと聞こえてきたので、やめた。
そのうち、父と母が尋常じゃない雰囲気で言い争っている声が聞こえてきた。
2階から1階の音を聞いているだけだから、何を言っているのかわからなかったけど、母が泣いている、と気づいた。
どうしようかとドキドキしていたら、意外なことに、母が子供部屋まできて、すっと引き戸を開けて、僕が起きているかどうか尋ねた。
起きているよ、と答えると、大事な話があるから、遅い時間で済まないけど下まで来てくれる?と聞かれた。
何が起きるのかわからないまま、バクバクと打つ心臓を抱えて降りていった。
父は腕を組んだまま目を瞑り、上を向いて座っていた。
母は泣きながら下を向いていた。
母が唐突に言った。
「あのね、お父さん、ほかに好きな人がいるんだって」
「それでね、お母さんとはもう一緒に暮らせないんだって」
それだけ言うと、母は泣き崩れてしまった。
僕は、言われたことを理解するのにだいぶ時間が必要だった。でも心の中では赤いパトライトとウーウーというサイレンが鳴り響いていた。
両親が、別々に暮らす!?考えられなかった。理解したくなかった。夢じゃないのかこれは。
夜中にそんなこといきなり言われても!!
「どうして!?一緒に住めないの?一緒に住もうよ」
そんなことを言った気がする。
何度も何度も言って、何度も何度も否定された気がする。
それから、僕は聞いた。
「ぼくたちは、どうなるの」
僕の中でもう心は決まっていた。父と暮らすなんて考えられない。母と暮らすのだ。父はどこでも好きなところへ行けばいい。
しかし母は、逆のことを言った。
「お母さんひとりでは、3人も食べさせていけないから、お父さんと一緒に暮らしてね……」
なんてことだ!?
母がこんなことを言うなんて、嘘に決まってる!!
「でもお母さん、お金があったら僕たちと一緒に住んでくれるの?」
「だめなのよ……」
「いやだ、僕、お母さんと一緒に暮らすよ!」
何度も何度も頼んだ。泣きじゃくりながら。
その間、父は一言も発せず、腕を組んだまま、上を向いて目を瞑ったまま。
僕は繰り返し、頼み込んだ。頼むから……。
何時間経っただろう。そこでふと、終始無言だった父が
「ひとりなら、なんとかなるかもしれないだろう……」
そんなことを言った。
兄弟が離れ離れ!?そんなの解決じゃない!!!
僕ら兄弟に、別々に暮らせというのか!!!
そこで父が僕に言った。忘れられない台詞だ。
「ひとりだけ連れて行くなら、どっちを連れて行く」
何を言っているんだ!!!選べるわけがないだろう!!!
両方だ!!!!!両方連れて行くんだよ!!!!!
僕は突如、妹と弟のこの先のことが心配で、そのことで頭がいっぱいになった。
まだ小さい妹と弟。僕しか我慢できる人はいないじゃないか。
そして両親に懇願した。
「お願い、ぼくがひとりで、お父さんと暮らすから、妹と弟はいっしょにお母さんが連れて行ってあげて!!」
もう完全に、僕の中では父を悪人扱いしてた。
でもそんなの気にしてる余裕なんてなかった。
そこに突然。
僕のうしろから、泣き声が。
ぼくらの必死のやり取りで、妹と弟が起きてきてしまっていたのだ。
ふたりは、玄関で僕たちの話をきいていたのだろう。
ふたりは泣きながら部屋に入ってきて、妹が叫んだ。
「お母さん、どっかいっちゃうの!?いやだぁあああ!」
なんの会話をしているかも分かっていないだろう小さな弟まで、つられて泣いている。
ぼくら3人は、泣き叫んだ。泣き疲れるまで。
・・・
最後に、母が言った。
「お母さん、もういちど、お父さんと話をしてみるからね。お母さん一生懸命やるから。ごめんね。だから今日はもう寝なさいね」
僕たちは、泣きながら、寝床へ戻った。
翌朝。
父は出かけてしまい、いなかった。
母が、言った。
「お父さん、もう一度考え直してくれるって」
ぼくはそれがどんな意味かも深く考えず、ただただ、みんなまた一緒に暮らしていけるという事実だけで、いっぱいだった。
それからしばらくして、母は、僕に言った。
もうこの話をするのは、やめようと。
お父さんは反省しているから、もうやめようと。
言うとおりにした。
それからまた、我が家には平和が訪れた。
どうしてあのとき、遺恨を残さず、家族がまたひとつに戻れたのか、いまだによくわからない。
父は父なりに、父でいつづけることの葛藤や努力が、あったのかもしれない。
とにかくそうして、その事件は、封印された。
これを妹や弟が覚えているのかどうかすら、僕は知らない。
なぜなら、僕はいまこの瞬間まで、この詳しい記憶を封印してきたからだ。
今日はここまで。
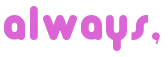

コメント
年齢だけ重ねてオトナになったことで必死に消化しようとしても、子供の頃に受けた傷は癒えない。
今からでも本心から「あの時は悪かった」と謝ってもらえたら…、子供の心に戻ってそれを受け止め、涙を流すことができたら、そこではじめて消化できるものになるのかもしれない。
「長男なんだから」「お兄ちゃんなんだから」なんて言葉は欲しくないよね。
ちょっと先に生まれたくらいで、甘えたくても甘えられないなんて辛かったよね。
忘れることはできないけれども、心に溜め込んでしまった辛い思いはなるべく吐き出して、自分にとって何が辛くて、どう苦しかったのか理解していくのはいいことだと思う。