三島由紀夫の「若きサムライのために」が文庫化されてから今年で39年になる。
三島由紀夫がこの中で書いた「若者」とは、年代的にちょうど僕の親たちの世代、つまり団塊の世代になる。団塊ジュニアの僕たちが若者ではなくなりつつある今日、内容には現代との多少のずれがあることは致し方ないが、それでもこの作品からあふれ出るものは、時代を超えて心を打つ。
命を懸けて生きることが難しくなって久しい。我々の世代どころか、親の世代ですら戦争を覚えているものはごくわずかだ。そんな「僕たち」に今こそ必要とされているのが、サムライ魂なのではないだろうかと、常々考えている。
時代錯誤と言われようが構わない。僕はこれが僕の思想にぴったりくるし、必要だと思うから、伝えたい。
この作品、そして三島由紀夫へのオマージュとして、この作品の各章をひとつずつ、現代に即した僕なりの解釈を、これから書いていこうと思う。
このブログを読んでいる皆さんはそう多くは無いことを知っているが、機会があったら是非読んでみて欲しい。三島由紀夫の、「若きサムライのために」だ。
「勇者について」
この間、トム・クルーズ主演の「ラスト・サムライ」という映画が来たが、日本人が「外国人には侍魂は通じない」と思い込んでいたものが、いかに上手くスクリーンで再現されていたか、驚きとともにこの映画を観た。逆に言えば、僕たちの世代がどれほど侍魂を知り、実践しているのだろうか。何も知らない者がほとんどではないか。
今日でも欧米をはじめとした諸外国では、日本に対して「サムライ」のイメージを強く持っているのだということを強調したい。この事実は、国を出て日本を代表するひとりとして外国人と接してみなければ、決して分からない感覚だろう。
われわれにとって「サムライ」はわれわれの父祖の姿であるが、西洋人にとっては、いわゆるノーブル・サヴェッジ(高貴なる野蛮人)のイメージでもあろう。われわれはもっと野蛮人であることを誇りにすべきである。
日本人の社会は基本的にいまでもサムライの魂を色濃く残していると思う。あなたがそれを感じなくても、あなたが無意識に従っている日本独特の商習慣や風習の多くには、サムライの心がある。しかしそれを理解せずにそれらの習慣に接すると、「意味のない無駄なもの」とか「めまぐるしい変化を要求される現代に即しない」などという理由で否定をする傾向にあるのだと思う。
さて、「サムライ」といえば、われわれはすぐ勇気ということを考える。勇気とは何であろうか。また勇者とは何であろうか。
ここで三島は、金嬉老事件(きんきろうじけん)を取り上げる。金嬉老事件とは1968年に、金嬉老(キム=ヒロ:日本語読みできんきろう)が起こした殺人、監禁、篭城事件のことだが、詳しくはWikipediaの記事を読むとわかる。
三島は、この事件で人質にとられた13名の中に二十代初期の青年が数人いたことを指摘する。彼らは日本人として「サムライ」的な行動をすべきだったものが、ついに人質になっていた四日間にわたり、ひとつも金嬉老に手を出すことができなかったと言う。
われわれはかすり傷も負いたくないという時代に生きているので、そのかすり傷も負いたくないという時代と世論を逆用した金嬉老は、実にあっぱれな役者であった。そしてこちら側にはかすり傷も負いたくない日本青年が、四人の代表をそこへ送り出していたのである。
これは今でもまったく同じことが言える。それどころか、今や「かすり傷のことを考えたくも無い」「かすり傷を自ら負うようなことをするほうがおかしい」などという意見がたくさん見受けられる。
あんまり無駄に引用ばかりすると著作権の問題になるから、引用はほどほどにしておく。三島が言いたいのはこういうことだ。
われわれは、腰抜武士であると。
平和が続くと、人は戦乱を忘れる。
これは現代では、戦乱を想像することすら難しい世の中になってしまっている。
とくに、日本しか知らない者は。若者に限らず。
このような状況は、若者だけではなく、我々の親の世代からずっと続いていることなのだ。戦乱を知らない者に、戦乱を想像することは難い。
とくにいまの日本の教育は、そのようにできていると思う。
周辺諸国のほうが的確に日本の像を把握している部分が少なからずあることを、われわれ日本人は知らなければならない。
戦乱を忘れたのではなく、平和「しか」知らないということは、非常の事態においてどうあるべきかということを「忘れてしまう」以前に、「知らない」ことになる。
しかしそこから導き出される結果は同じだ。
三島は「男」という言葉を使う。そう、サムライとは本来男の役割。こんなことを書くと反論する方もいるかもしれないし、自分はジェンダーにも疎いから自分の信念だけで書かせていただくが、男と女の社会的に可能な役割の範囲は違うという点は、三島の主張も僕の信じるところもなんら変わりは無い。いまは、非常の事態の話をしている。非常の事態とは、極端な例でいえば戦争だ。戦場で前線に掘った塹壕に身を隠しつつ、少ない水と食料で渇きと飢えをしのぎながら、戦意を維持して敵を倒す。これは、巣を守る男の本能なくしてはできない行動だと思う。あえて書いておくが、僕は右でも左でもない。単純に、肉体的、精神的、生理的な構造の差異によるものであると思っている。
しかし、それはあくまで観念と空想の上のできごとで、現実の日本には、なかなかそのような徴候も見られない。そしていまは女の勢力が、すべてを危機感から遠ざけている。
危機を考えたくないということは、非常に女性的な思考である。なぜならば、女は愛し、子供を生み、子供を育てるために平和な巣が必要だからである。平和でありたいという願いは、女の中では生活の必要なのであって、その生活の必要のためには、何ものも犠牲にされてよいのだ。
平和だからといって非常事態を意識しない生き方は、男の思考ではないと言う。
危機に備えるのが男であって、平和を脅かす危機に、男は力を持って対処する。それを女性がすることはできない。
男が頼りなくなることによって、女性は自分の力で平和を守れるという自信をつけた。
それは、勇者と呼べる男がいなくなってしまい、そのような男の像を見ることはおろか、男女問わず想像すらできない世の中になってしまったからだろう。
今の日本では、大勢に順応するということは、戦時体制下のアメリカとはちがって、別に徴兵制度を意味しない。何とか世の中をうまく送って、マイホームをつくるために役立つ道を歩むことである。それでは大勢に順応しないということは、何を意味するであろうか。
大勢に順応するということの内容については、三島の指摘通りだったと思う。
僕らの親の世代は、マイホームのために大勢に順応した。そのためには勇者である必要はなく、企業戦士であればよかったのだ。勇者であるところを家庭にすら見せる機会がない現代において、いかにして女性は男性の勇敢な姿を想像できるだろうか。巣を守るための英雄的、男性的ともいえる行動の必要がない平和な今日、女性は男に対して必然的に、優しさだとか家庭的であるとか子供の面倒を見てくれるだとか、女性がいままで持っていた部分を持ってくれる男性を求めるのではないか。
そしてそれは、決して否定されるべきことではないし、三島もそう書いている。
したがって、いまの日本では勇者が勇者であることを証明する方法もなければ、不勇者が不勇者であることを見破られる心配もない。最終的には、勇気は死か生かの決断においてきめられるのだが、われわれはそのような決断を、人には絶対に見せられないところで生きている。
「何のために死ぬ」「命をかけてやる」ということを言うことはたやすい。
しかし現代においては、それを言うことすらはばかられるような風潮はないだろうか。
そして、三島の時代と変わらないのは、それが口だけなのか真実の言葉なのかを判断する機会は、普通に平和に生活している限り、絶対に訪れないのだ。
そしてここからが本題だ。
三島は、現代において若い「サムライ」であるわれわれが、勇者なのか不勇者なのか判断するためには、もっと別のところを見なければならないと言う。
――それは何であろうか。
それは非常事態と平常の自体とを、いつもまっすぐに貫いている一つの行動倫理である。危機というものを、心の中に持ち、その危機のために、毎日毎日の日常生活を律してゆくという男性の根本的な生活に返ることである。
危機を想像し、身近に感じることができますか。
そしてそれを現実の可能性として、対処すべき方法を意識して生活していますか。
男性が平和に生存理由を乱すときには、男のやることよりも女のやることを手伝わなければならない。危機というものが男性に与えられた一つの観念的役割であるならば、男の生活、男の肉体は、それに向って絶えず振りしぼられた弓のように緊張していなければならない。私は町に、緊張を欠いた目をあまりに多く見過ぎるような気がする。しかし、それも私の取り越し苦労かもしれない。
いいえ、それが取り越し苦労だとしたら、僕の目は節穴だ。
そしてこれは、決して満足に実現できてはいないが僕の心の根底を無意識に流れていた人生観を見事に言い表していたので、感動のあまり震える思いだった。
そうだ。危機感を感じて生きていなければならないのだ。
そして危機感がなくとも生きられるということに気づき、それに甘えるように体調を崩し、それに甘えるように、男としての性分を忘れ、さらに言うならば、女性のやることも満足にできていないという、不勇者になりつつある自分に気づき、深く反省した。
かつてイタリアの有名な小説家モラビアが来たときに、モラビアは私に言った。
「日本の町は青年であふれている。そして東南アジアの国々を回ってくると、日本へ来て非常に驚く特色は、それら若い人たちが皆、ウォーリアー(戦士)のように見えることだ」と。
これこそが、いままさに社会の第一線から引退しようとしている団塊の世代が、われわれの世代にうまく残しきれなかったものに違いない。
僕はこのブログで団塊の世代について何度も意見を述べたが、尊敬すべき点は、彼らが企業戦士であるという点だ。これは、勇者・不勇者の判断以前の問題で、平和を前提とした世界における男の役割に限定した話になるが、その点においてすら、現代の若い世代、われわれの世代からあとの世代、もっと細かく感じていることを言うならば、オイルショック以降の世代に、足りないものではないのか。団塊の世代から、学び取ることがまず、たくさんあるのではないか。あっちを見ても、こっちを見ても、そんなことは聞きたくもないという人があまりに多い。こんな戯言は、このブログで個人的に書くくらいしか表現のしようがないのだ。
しかし僕はこれを戯言だとは決して思ったことは無い。
アジアの各国から日本へやってきた多くの人たちと一緒に仕事をした。
西洋からやってきた多くの人たちと一緒に仕事をした。
彼らの多くはもう、日本人のサムライ魂というものを信じない。
とくに日本に来て、日本の企業と一緒に仕事をした人は、そこにサムライ魂は感じない。残っているのは、その抜け殻だけだ。抜け殻によってがんじがらめにされたルールと戒律だけで、その根拠となる思想が追いついていない。だから尊敬されることもないし、さすがサムライの民族であると感嘆されることもないのだ。
アジアに行くたびに思う。僕は誇りある日本人でありたいと。
政府の掲げる「美しい日本」だとか、愛国主義だとか、そういうものではない。
日本が育んできたサムライの魂。僕はときに、日本特有の習慣を「これは日本の企業文化がサムライ魂に基づいているからだ」と海外のエンジニアに説明するほかない状況に何度か遭遇した。しかしそこにあったのは、サムライの名残りで、サムライの心を持った戦士によって運営されているわけではないことに、一抹の寂寥感を覚えたのだ。
今日、日本人よりも政情の不安定な国の人たちのほうが、強い。
まず前提の前提として、見掛けだけで判断してはいけない。
これはもう西洋の人たちは乗り越えてきたところだ、日本は大変に遅れている。
心の目を持って外国人と接し、その外国人のレンズ(パラダイム)をもって、日本を見つめなおし、自分を見つめなおすことを強く勧める。自分もそうしていく。
そこに見えるものは、僕たちを驚かせるだろう。
危機感をもって、常に張りつめた弓のように生きていてこそ、生きていることを実感できる。これは、「死」をぶつけなければ「生」をリアルに感じることができないということだ。
常に自分を律すること。疑問をもつこと。反省をすること。危機感を持つこと。死を意識すること。
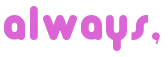


コメント